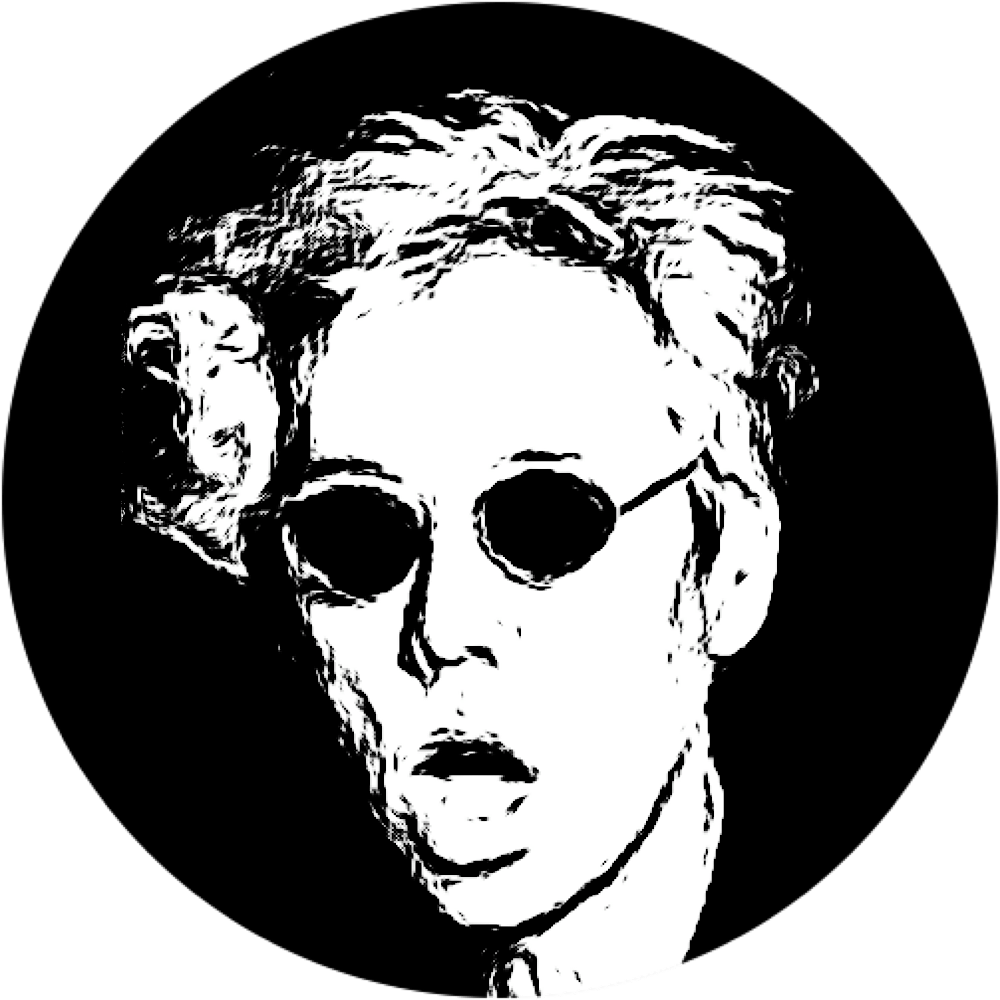2023年2月28日
市田君
「勝手に死ぬことは許されない」かよ。勝手に死ぬのは難しい。勝手気ままな性癖は一生をふいにしたかもしれないな。
ところで、君があとがきを書いた岡崎次郎『マルクスに凭れて六十年』(航思社)を読み始めた。こんな言い方は著者に対して失礼かもしれないが、とても好感のもてる書きっぷりだと感じる。マルクス学者はこうでなくっちゃ。旧制高校の気風とかだけでなく、演劇や寄席から西行まで、とても趣味嗜好もはっきりしていて、広いし、今では珍しい「まっとう」に面白い人だったのだろうと思う。最後の自殺、奥さんと一緒に海の藻屑と消えたということを考え合わせれば、それがあり得たかもしれない「作品」であり、君が言うように今ではそれがほとんど意味を欠いたものであるとしても、印税で大金を稼いだ一人の先輩として(何の先輩?!)、僕にとっては彼の生涯に興味以上のものを抱いてしまう。君のあとがきは原稿段階で読ませてもらったが、もう一度しっかり読もうと思っている。
僕はマルクスをそんなに読んだわけではないけれど(岡崎次郎訳は大月書店だったのでたぶん少ししか持っていなかったはずだし、どんな訳だったかよく覚えていないが、書庫にあるのか、この部屋をちょっと見ただけでは見当たらない、本が溢れていて探せない)、別の訳者で読んだ限りのマルクスの翻訳には疑問と物足りなさをずっと感じてきた。マルクス自身の文章はといえば、何というか、煽動家であることがわかるていのものだとずっと思っていた。文章は上手いし、何しろ小気味いい。鼓舞されるようなリズムがある。フランス語訳で読んでもそれがわかる。レヴィ=ストロースが自分の本を書く前に必ずマルクスの『ブリュメール』を読んだらしいが、その気持ちはよくわかる。でも日本のマルクス学者の文章ときたら……。こんなことは正直僕にとってはどうでもいいことだが、これは日本へのマルクス「受容」のあれこれにも関わる由々しき事態だったのではないか。
日本にもかつてボードレール好きがたくさんいたが、今は流行らなくなったとはいえ、ボードレール好きは「ボードレールの世界」が好きなんだ。ボードレールの世界があると思っているし、ヒステリックなボードレール自身がたぶんそれを性急に望んだ節がある。つまり君が言うように、読み手を含めて「逸脱」を楽しんでいる。ゲームのルールは誰にも関わりのない「芸術」なるものであって、この場合の逸脱も芸術的行為だと愛好者たちは思っている。そこに中身はない。愛好者たちにとってでさえ。ただボードレール本人の最後はかなり興味深いよ。借金で首が回らなくなってベルギーに逃げて、梅毒で頭がおかしくなるのだが、『赤裸の心』のなかに「痴呆の翼の風が私の上を通り過ぎる」というようなことを書いている。彼は痴呆の翼の影を見たんだ! ある意味で落としまえをつけているところがある。
ボードレールのことは脇に置くとして、さて、君の言うステファヌ・マラルメだが、「マラルメの世界」というものはないと僕は思っている。少なくともそのようなものとしての彼の仕事全体を捉えることは非常に困難だ。「ランボーの世界」がないのと同じ意味ではないが、「ボードレールの世界」があるようには「マラルメの世界」はない。
君の言うマラルメに関する「流行」だが、それにピリオドを打つとして、はたして連綿たる、もしくはたった一つの「作品」なるものは、マラルメの言う「危機」のなかで明確に成立したのだろうか。「アヴァンギャルド」の永遠の宿題だが、マラルメはピリオドを打つことで「新しい」ことをやったのだろうか。ブランショ的にはそうではないような感じがする。「あの暗いレースの襞」! 謎はそのまま残された。ブランショの評判が落ちているということだが、ブランショ的な「不可能性」の高みに関して、あれをひたすら希求すると癌になるなと僕はあるとき思った。しかしマラルメについてであれ、アルトーについてであれ、僕にとってブランショを読むことはまさにそれだった。実際に読者が癌になることも含めて、ブランショ的な「癌化の空間」があると思う。僕はあるとき意識的にそこから逃げた。だからブランショを読んでも、正直に言えば、僕はマラルメがよくわからなかった。というか、むしろマラルメには僕の理解を寄せつけないところがあって、それはどちらかといえば僕にとって今でもわだかまりになっている。
マラルメは手紙のなかだったか、ランボーについて興味深いことを言っている。あいつはただのとんでもない彗星のようなもので、何ももたらさなかったし、ただ自分たちの前を通り過ぎただけだ、と。ランボーはヴェルレーヌたちによって勝手に『ヴォーグ』誌などに紹介され、まさに「流行」となった頃だ。それまで詩集は一冊『ある地獄の季節』だけで、しかも自費出版の金を使い込んだので本は出ず、十冊くらいを友だちに配っただけで世間には出回っていない。つまりまったくの無名だった。「流行」した頃は、すでに詩を捨ててアフリカにいたランボー自身は、それにまったく興味を示さず、「君があのランボーなんだろ?」と同国人に問われても、完無視、眉ひとつ動かさなかったらしい。
ところで、君があとがきを書いた岡崎次郎『マルクスに凭れて六十年』(航思社)を読み始めた。こんな言い方は著者に対して失礼かもしれないが、とても好感のもてる書きっぷりだと感じる。マルクス学者はこうでなくっちゃ。旧制高校の気風とかだけでなく、演劇や寄席から西行まで、とても趣味嗜好もはっきりしていて、広いし、今では珍しい「まっとう」に面白い人だったのだろうと思う。最後の自殺、奥さんと一緒に海の藻屑と消えたということを考え合わせれば、それがあり得たかもしれない「作品」であり、君が言うように今ではそれがほとんど意味を欠いたものであるとしても、印税で大金を稼いだ一人の先輩として(何の先輩?!)、僕にとっては彼の生涯に興味以上のものを抱いてしまう。君のあとがきは原稿段階で読ませてもらったが、もう一度しっかり読もうと思っている。
僕はマルクスをそんなに読んだわけではないけれど(岡崎次郎訳は大月書店だったのでたぶん少ししか持っていなかったはずだし、どんな訳だったかよく覚えていないが、書庫にあるのか、この部屋をちょっと見ただけでは見当たらない、本が溢れていて探せない)、別の訳者で読んだ限りのマルクスの翻訳には疑問と物足りなさをずっと感じてきた。マルクス自身の文章はといえば、何というか、煽動家であることがわかるていのものだとずっと思っていた。文章は上手いし、何しろ小気味いい。鼓舞されるようなリズムがある。フランス語訳で読んでもそれがわかる。レヴィ=ストロースが自分の本を書く前に必ずマルクスの『ブリュメール』を読んだらしいが、その気持ちはよくわかる。でも日本のマルクス学者の文章ときたら……。こんなことは正直僕にとってはどうでもいいことだが、これは日本へのマルクス「受容」のあれこれにも関わる由々しき事態だったのではないか。
日本にもかつてボードレール好きがたくさんいたが、今は流行らなくなったとはいえ、ボードレール好きは「ボードレールの世界」が好きなんだ。ボードレールの世界があると思っているし、ヒステリックなボードレール自身がたぶんそれを性急に望んだ節がある。つまり君が言うように、読み手を含めて「逸脱」を楽しんでいる。ゲームのルールは誰にも関わりのない「芸術」なるものであって、この場合の逸脱も芸術的行為だと愛好者たちは思っている。そこに中身はない。愛好者たちにとってでさえ。ただボードレール本人の最後はかなり興味深いよ。借金で首が回らなくなってベルギーに逃げて、梅毒で頭がおかしくなるのだが、『赤裸の心』のなかに「痴呆の翼の風が私の上を通り過ぎる」というようなことを書いている。彼は痴呆の翼の影を見たんだ! ある意味で落としまえをつけているところがある。
ボードレールのことは脇に置くとして、さて、君の言うステファヌ・マラルメだが、「マラルメの世界」というものはないと僕は思っている。少なくともそのようなものとしての彼の仕事全体を捉えることは非常に困難だ。「ランボーの世界」がないのと同じ意味ではないが、「ボードレールの世界」があるようには「マラルメの世界」はない。
君の言うマラルメに関する「流行」だが、それにピリオドを打つとして、はたして連綿たる、もしくはたった一つの「作品」なるものは、マラルメの言う「危機」のなかで明確に成立したのだろうか。「アヴァンギャルド」の永遠の宿題だが、マラルメはピリオドを打つことで「新しい」ことをやったのだろうか。ブランショ的にはそうではないような感じがする。「あの暗いレースの襞」! 謎はそのまま残された。ブランショの評判が落ちているということだが、ブランショ的な「不可能性」の高みに関して、あれをひたすら希求すると癌になるなと僕はあるとき思った。しかしマラルメについてであれ、アルトーについてであれ、僕にとってブランショを読むことはまさにそれだった。実際に読者が癌になることも含めて、ブランショ的な「癌化の空間」があると思う。僕はあるとき意識的にそこから逃げた。だからブランショを読んでも、正直に言えば、僕はマラルメがよくわからなかった。というか、むしろマラルメには僕の理解を寄せつけないところがあって、それはどちらかといえば僕にとって今でもわだかまりになっている。
マラルメは手紙のなかだったか、ランボーについて興味深いことを言っている。あいつはただのとんでもない彗星のようなもので、何ももたらさなかったし、ただ自分たちの前を通り過ぎただけだ、と。ランボーはヴェルレーヌたちによって勝手に『ヴォーグ』誌などに紹介され、まさに「流行」となった頃だ。それまで詩集は一冊『ある地獄の季節』だけで、しかも自費出版の金を使い込んだので本は出ず、十冊くらいを友だちに配っただけで世間には出回っていない。つまりまったくの無名だった。「流行」した頃は、すでに詩を捨ててアフリカにいたランボー自身は、それにまったく興味を示さず、「君があのランボーなんだろ?」と同国人に問われても、完無視、眉ひとつ動かさなかったらしい。