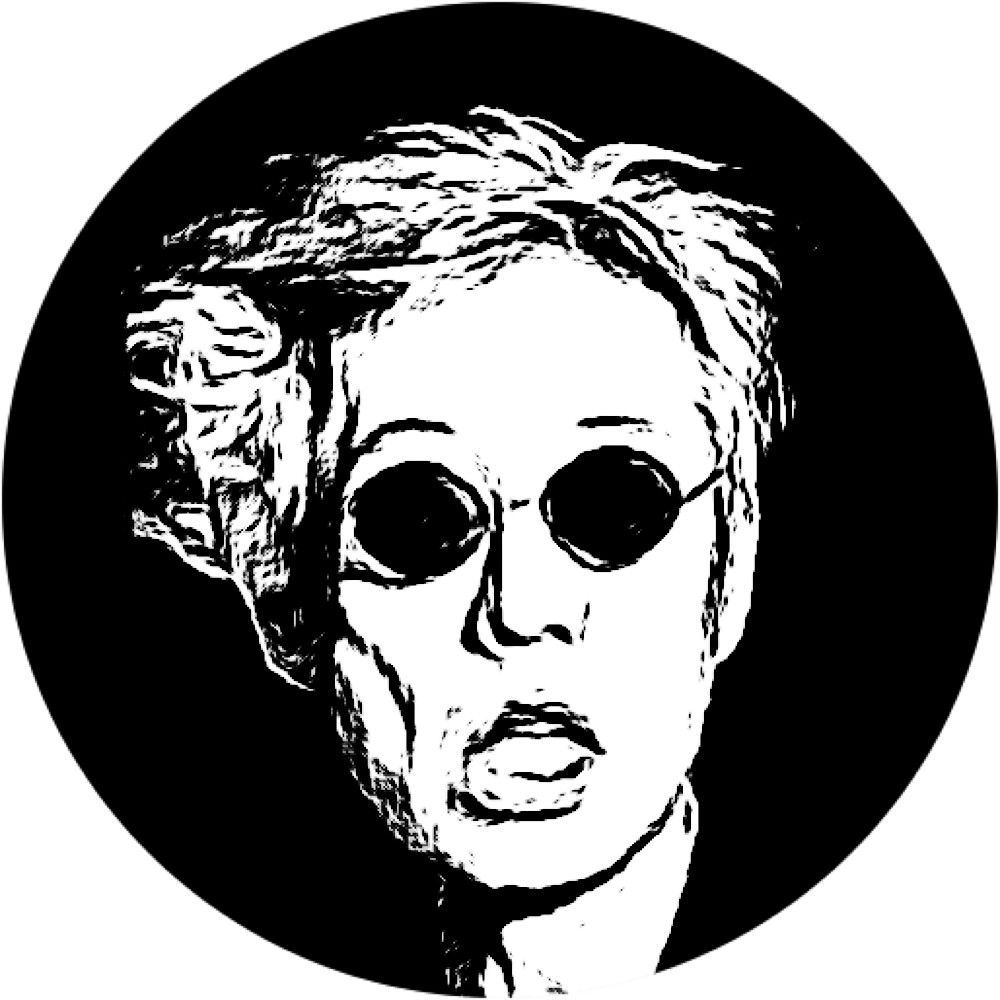2023年4月30日
学兄どの、
前回の君の手紙を理解できているかどうか、はなはだ心もとないが、思いついたことを書いてみる。
君が最後に引用したドルフィーの発言、「音楽はいったん終われば空中に去ってしまう。二度とそれを捕まえることはできない」。これこそまさにドルフィーの演奏そのものだった。ドルフィーのフルートにもサックスにも消え入るような何かが歴然とあった。すべてが消えればいい。ドルフィーはほとんど逃亡寸前だった。モンクだってそうだ。みんな逃げてやろうと待ちかまえている。それが演奏。理想的だ! はじめからすべてが消えてなくなるように演奏できればどんなにいいだろう。僕にとってもドルフィーは理想の音楽家のひとりかもしれない。でもドルフィーのようにはできないし、そうはいかないときがある。
常識文化史的なよけいな「言葉」が残るんだ。つまらない言葉から不可解なものまでいろいろあるが、しかし「音楽を知らない客人」にとってそれは「隠された言語」なのだろうか。ショパンの楽曲を言語と受けとったとする、君の引用した寓話を僕はよく理解できない。これは何かの喩えになってはいまいか。この寓話の述べる「言語」というのがすでに隠喩に思える。だったらむしろ彼はそれを抽象的な意味での「歌」と思うのではないか。それが隠されているかどうかはわからないが、そのときにこそ彼の「歌」は発生するか、ショパンの曲をつまらない「歌」と思うのではないか。なぜならそれ以前に音楽を聴いたことがなかったとしても、音を言語と解すればそれは言語になるのだろうが、彼の耳にはいろんな音や雑音がすでに聞こえたていたはずだからだ。音楽を知らなくても、音を聞いているはずだからだ。ラジオのノイズを含めたこの「音」には歌の原型、萌芽があると思うが、言語とは言えないものではないか。それにそもそも僕には「音楽を聞いたことがない」状態を想像できない。原始社会にあってさえも人類にそんな事態はなかっただろう。それどころか「音楽」はとてつもなく古い。だから我々の聴覚の体系にはすでに「隠された歌」が入り込んでいるのではないかと僕は思う。それを旋律として捉えることができるかどうかはわからないにしても、しかしそれは「言語」なのだろうか。
それとは反対の意味で、〈「ワーグナーの世界」はあるが、「シェーンベルクの世界」はない〉とはいえないと思う。シェーンベルクにはあまりにもワーグナー的なところがあるからだ。常識的文化史に反論するようだが、僕にとってそこに断絶はまったく感じられない。それがかえって「シェーンベルクの世界」を醸し出してしまっている。絶対音楽には欠損というか、瑕瑾があって、その欠点をつくり出しているものがそのままその音楽の魅力になったりする。むしろ絶対音楽の動機にそれがないとは言えないように感じる。しかも僕にとってそもそも標題音楽と絶対音楽の区別に意味があるとは思えない。彼ら音楽家たちは絶対音楽を創造する前に、言葉の比喩ではない「音」を聞いていたことに変わりはないからだ。楽曲に言葉を使う使わないを別にすれば、作曲というものにそれほど違いがあるとは思えない。いずれにせよ、たとえ表現されなくても「ノイズ」の領域がどちらの音楽にも存在してしまう。どんな「音階」にもそれがあるし、そのような感覚の領域が否応なく存在してしまう。僕はそれを聴こうとしてしまう。だけどこんなことは理論化できない。「シェーンベルク」を「ヴェーベルン」に置き換えても同じだとは言えないからだ。だから常識的文化史、音楽史では音楽を捉えることはできないのではないかと思う。最近、森田潤がつくった『GATHERING OF 100 REQUIEMS』を聴くとそれがよくわかる。モーツァルトのレクイエムの演奏を100重ねたものだが、モーツァルトのレクイエムはそのままで恐ろしい音楽だよ。
君が最後に引用したドルフィーの発言、「音楽はいったん終われば空中に去ってしまう。二度とそれを捕まえることはできない」。これこそまさにドルフィーの演奏そのものだった。ドルフィーのフルートにもサックスにも消え入るような何かが歴然とあった。すべてが消えればいい。ドルフィーはほとんど逃亡寸前だった。モンクだってそうだ。みんな逃げてやろうと待ちかまえている。それが演奏。理想的だ! はじめからすべてが消えてなくなるように演奏できればどんなにいいだろう。僕にとってもドルフィーは理想の音楽家のひとりかもしれない。でもドルフィーのようにはできないし、そうはいかないときがある。
常識文化史的なよけいな「言葉」が残るんだ。つまらない言葉から不可解なものまでいろいろあるが、しかし「音楽を知らない客人」にとってそれは「隠された言語」なのだろうか。ショパンの楽曲を言語と受けとったとする、君の引用した寓話を僕はよく理解できない。これは何かの喩えになってはいまいか。この寓話の述べる「言語」というのがすでに隠喩に思える。だったらむしろ彼はそれを抽象的な意味での「歌」と思うのではないか。それが隠されているかどうかはわからないが、そのときにこそ彼の「歌」は発生するか、ショパンの曲をつまらない「歌」と思うのではないか。なぜならそれ以前に音楽を聴いたことがなかったとしても、音を言語と解すればそれは言語になるのだろうが、彼の耳にはいろんな音や雑音がすでに聞こえたていたはずだからだ。音楽を知らなくても、音を聞いているはずだからだ。ラジオのノイズを含めたこの「音」には歌の原型、萌芽があると思うが、言語とは言えないものではないか。それにそもそも僕には「音楽を聞いたことがない」状態を想像できない。原始社会にあってさえも人類にそんな事態はなかっただろう。それどころか「音楽」はとてつもなく古い。だから我々の聴覚の体系にはすでに「隠された歌」が入り込んでいるのではないかと僕は思う。それを旋律として捉えることができるかどうかはわからないにしても、しかしそれは「言語」なのだろうか。
それとは反対の意味で、〈「ワーグナーの世界」はあるが、「シェーンベルクの世界」はない〉とはいえないと思う。シェーンベルクにはあまりにもワーグナー的なところがあるからだ。常識的文化史に反論するようだが、僕にとってそこに断絶はまったく感じられない。それがかえって「シェーンベルクの世界」を醸し出してしまっている。絶対音楽には欠損というか、瑕瑾があって、その欠点をつくり出しているものがそのままその音楽の魅力になったりする。むしろ絶対音楽の動機にそれがないとは言えないように感じる。しかも僕にとってそもそも標題音楽と絶対音楽の区別に意味があるとは思えない。彼ら音楽家たちは絶対音楽を創造する前に、言葉の比喩ではない「音」を聞いていたことに変わりはないからだ。楽曲に言葉を使う使わないを別にすれば、作曲というものにそれほど違いがあるとは思えない。いずれにせよ、たとえ表現されなくても「ノイズ」の領域がどちらの音楽にも存在してしまう。どんな「音階」にもそれがあるし、そのような感覚の領域が否応なく存在してしまう。僕はそれを聴こうとしてしまう。だけどこんなことは理論化できない。「シェーンベルク」を「ヴェーベルン」に置き換えても同じだとは言えないからだ。だから常識的文化史、音楽史では音楽を捉えることはできないのではないかと思う。最近、森田潤がつくった『GATHERING OF 100 REQUIEMS』を聴くとそれがよくわかる。モーツァルトのレクイエムの演奏を100重ねたものだが、モーツァルトのレクイエムはそのままで恐ろしい音楽だよ。