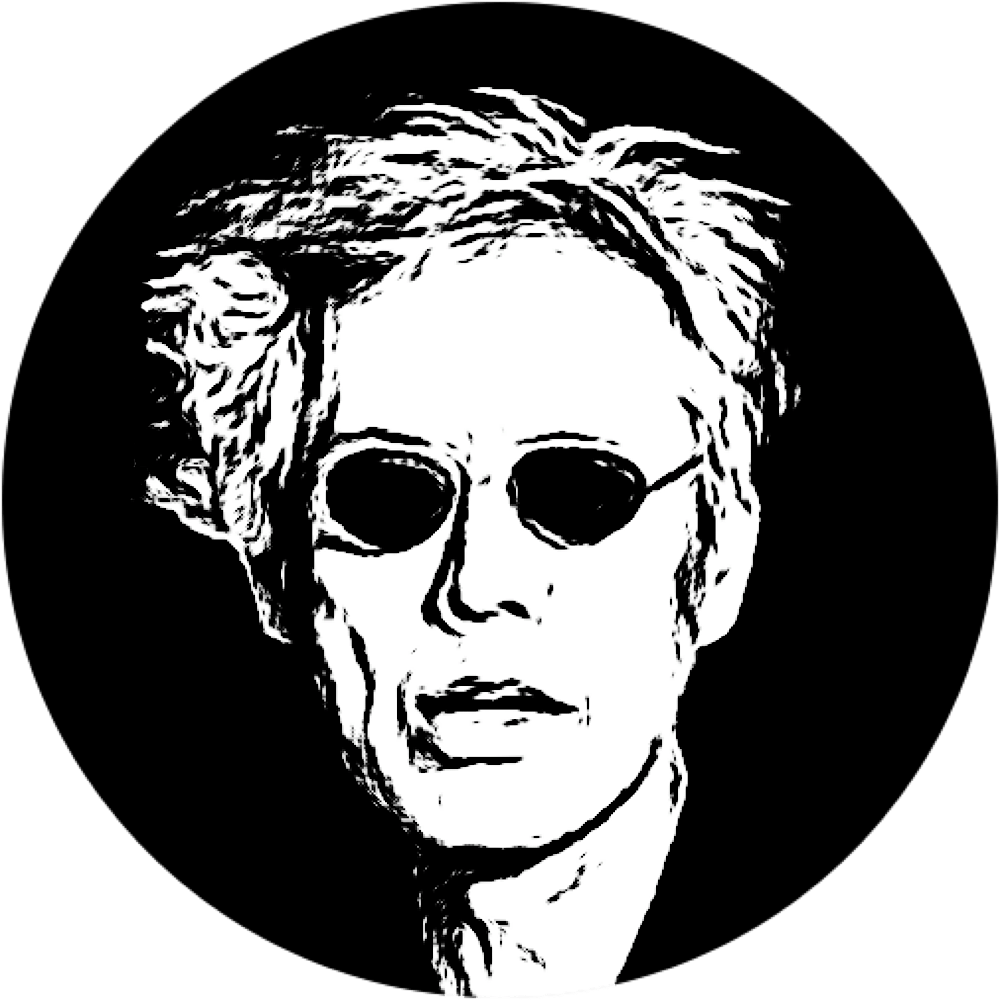2023年6月28日
良彦さま、
我々の聴覚体系に入り込んだ「隠された歌」はまだ言語ではないかもしれない。この歌は僕にとって「言葉」を伴っているのか、あるいは「言葉」そのものであるのかどうかいまだ確信がもてないと僕は言った。演奏中のミュージシャンとしては、とりわけそう言わざるを得ない。「言葉」以前に「音」がある? 世界に満ちている音の無限の連鎖は、世界が過ぎ去り、消え失せることを連続的に構成するが、これは世界の歴史がその成り立ちにおいて示唆しているような「言葉」のうちにあるのだろうか。一方、それに対して、言葉と音楽は同時的なものであり、分身的関係にあり、そのような「歌」があるとするなら、すでにそれは立派な「言語」である、と君は言う。そしてこの双子にはもう一人分身がいて、それはアルトーが思考を開始した「思考の不可能性」であり、「思考の中心にあいた空虚」、「穴」である、と。そして何かを語るという可能性は「狂人である」ことと同時的である、と君は言う。
君の言いたいことは全部わかるよ。反論のしようがない。君の言いたいことを全部認めた上で、しかしその同時性においてフーコーは、「狂人である」こと、思考の不可能性から思考を開始し、そこからしか言葉を語ることができない、あるいはそこにしか言葉の実質とその営為を見つけられない状態を、「無為」あるいは「作品の不在」とも呼んでいた。そうであれば、「言葉」は「作品の不在」と同時的なのだろうか。だけど正直に言えば、このことは僕にとってずっと解決できていないし、いまだ答えを出せていない問題としてあるんだ。自分は断片的に狂っているだけで、自分は狂人ではないと思うことがある、というような証言は、デカルトの理性をめぐるフーコーとデリダの論争に決着がつかない限り、自分が狂人ではないという証明にはならないし、その逆もまたしかりである。僕が理解するニーチェも、そのような事柄と無関係ではなく、それについて、『ユリイカ』だったか『現代思想』だったか、以前「ニーチェの狂気?」と題した文章を書いたことがある。それを再録した本はずばり『分身入門』という本だ。狂った分身が、理解不能性・決定不能性において狂っていない分身に入門するわけだ。あるいはその逆のケースも。ニーチェは古代文明の瞠目すべき人物たちが辿った運命に想いを馳せて語っている、「気狂いではなく、気狂いの振りをする勇気もないとき、人はいかにして自ら気狂いになるのか?」。
「音楽」に戻ろう。君が引用する『リグ・ヴェーダ』の「ヴァーチュ」、つまりまさしく「声」だ。ああ、たぶん「声」が最初にあるのかもしれない……。それは、実際、神の声なのか。人間の声なのか。ジャングルにも浜辺にも砂漠にも「声」が響いていたし、洞窟の中でも聞こえていた。新約のヨハネが言うように、最初にあったそれって「言葉」だったのだろうか。自分が物書きであるという事実について、つまり言葉を書く人間であるということについて、同時にミュージシャンとして、この「声」は屹立する「壁」であり(ヘブライの「嘆きの壁」のようなものであり、ユダヤ人たちはその壁の前で「雅歌」の朗誦をいまでも無駄に延々と繰り返している、いったい何のためなのか?)、それでいてこの「原初の歌」、あるいは「言葉のていをなさない得体の知れない呪文あるいは単なる音」は、僕の中に知らぬ間に絶えず入り込む不可解な「音楽」の謎であり続けている。ヴァーチュ。僕にとってそれは神の声ではなく、この声はたしかに「身体」から発せられながら、この「声」から逆に「身体」が出てくるのだ。そう、いろんなところで何度も言ったことだが、そんな感じだ。この声の身体を僕は何度も見て体験している。音楽しかり、舞踏しかり……。声から出てくる体がある。物質が非物質的様態を有するとすれば(分身はまさにそれだろう)、その分身的身体とはこれらの様態だけが凝集したものであり、その化身だ。この声は「歌」なのだろうか。歌だったのだろうか。歌になるのだろうか。この「歌」が僕を引きずり回し、それがいまでも僕をさいなんでいる。もちろん僕にとってネガティヴな状態だけがあるわけではないが(人がうたう歌を聞いてうっとりすることもある)、益体もないが、それにミュージシャンとして鼻面を引きまわされていることは自分でもわかっている。だからこそノイズは必然的なものとなるが、白状すれば、ミュージシャンとしてまだ何の解決にも至っていないというところだろう。だが演奏するとき、告白など何の意味もなさないのだけれど。
君の言いたいことは全部わかるよ。反論のしようがない。君の言いたいことを全部認めた上で、しかしその同時性においてフーコーは、「狂人である」こと、思考の不可能性から思考を開始し、そこからしか言葉を語ることができない、あるいはそこにしか言葉の実質とその営為を見つけられない状態を、「無為」あるいは「作品の不在」とも呼んでいた。そうであれば、「言葉」は「作品の不在」と同時的なのだろうか。だけど正直に言えば、このことは僕にとってずっと解決できていないし、いまだ答えを出せていない問題としてあるんだ。自分は断片的に狂っているだけで、自分は狂人ではないと思うことがある、というような証言は、デカルトの理性をめぐるフーコーとデリダの論争に決着がつかない限り、自分が狂人ではないという証明にはならないし、その逆もまたしかりである。僕が理解するニーチェも、そのような事柄と無関係ではなく、それについて、『ユリイカ』だったか『現代思想』だったか、以前「ニーチェの狂気?」と題した文章を書いたことがある。それを再録した本はずばり『分身入門』という本だ。狂った分身が、理解不能性・決定不能性において狂っていない分身に入門するわけだ。あるいはその逆のケースも。ニーチェは古代文明の瞠目すべき人物たちが辿った運命に想いを馳せて語っている、「気狂いではなく、気狂いの振りをする勇気もないとき、人はいかにして自ら気狂いになるのか?」。
「音楽」に戻ろう。君が引用する『リグ・ヴェーダ』の「ヴァーチュ」、つまりまさしく「声」だ。ああ、たぶん「声」が最初にあるのかもしれない……。それは、実際、神の声なのか。人間の声なのか。ジャングルにも浜辺にも砂漠にも「声」が響いていたし、洞窟の中でも聞こえていた。新約のヨハネが言うように、最初にあったそれって「言葉」だったのだろうか。自分が物書きであるという事実について、つまり言葉を書く人間であるということについて、同時にミュージシャンとして、この「声」は屹立する「壁」であり(ヘブライの「嘆きの壁」のようなものであり、ユダヤ人たちはその壁の前で「雅歌」の朗誦をいまでも無駄に延々と繰り返している、いったい何のためなのか?)、それでいてこの「原初の歌」、あるいは「言葉のていをなさない得体の知れない呪文あるいは単なる音」は、僕の中に知らぬ間に絶えず入り込む不可解な「音楽」の謎であり続けている。ヴァーチュ。僕にとってそれは神の声ではなく、この声はたしかに「身体」から発せられながら、この「声」から逆に「身体」が出てくるのだ。そう、いろんなところで何度も言ったことだが、そんな感じだ。この声の身体を僕は何度も見て体験している。音楽しかり、舞踏しかり……。声から出てくる体がある。物質が非物質的様態を有するとすれば(分身はまさにそれだろう)、その分身的身体とはこれらの様態だけが凝集したものであり、その化身だ。この声は「歌」なのだろうか。歌だったのだろうか。歌になるのだろうか。この「歌」が僕を引きずり回し、それがいまでも僕をさいなんでいる。もちろん僕にとってネガティヴな状態だけがあるわけではないが(人がうたう歌を聞いてうっとりすることもある)、益体もないが、それにミュージシャンとして鼻面を引きまわされていることは自分でもわかっている。だからこそノイズは必然的なものとなるが、白状すれば、ミュージシャンとしてまだ何の解決にも至っていないというところだろう。だが演奏するとき、告白など何の意味もなさないのだけれど。