2024年2月29日
市田君
プルーストの「同じだが、違う」を見つけ出す絶妙さは、ほとんど無意志的であることを「装う」ように、突発的、あるいは、言ってみれば即興的(こちらは無意志的だ)にやって来るところにあるように思われる。そのことは、作家にはわりと珍しいといえるプルーストの「耳」のよさ(なぜなのかはわからないが、もともとの音楽的素養とはほとんど無関係だ)、あるいは音楽に対する全く新しいといえる珍しい見解(例えば後期のベートーヴェンについて)のなかにうかがうことができる。ここには明らかに同じ記号(シーニュ)とは違う記号、だが決定的には違わない記号がある。決定的には違わないで、違っているもの。もちろん、あのダサいお経か独り言のような「差異の反復」でも、「反復としての差異」でもないもの。ともあれ、この記号は発せられたものだ。二重奏が一人で成り立っているように、もちろん、互いの「幻想」のなかで発せられる? 君は反論するかもしれないが、この幻想は、果てや境界を確定できないという点で「存在の一義性」に類しているのではないか。
しかし、たしかに「s’entendre parler」という「分裂」がある。だけど、そのように見えたとしても、演奏のときになかなか語り合えないのが通常だよ。分裂が最初にあったのであれば、「ミュージシャン」は普通に記号を発しているつもりでも、相手のほうはそれを受け取りたくない場合がある。否認ではなく、拒否だ。演奏の途中、ロックンロールの人たちは別にして、意味内容だけではなく意味作用に対する拒絶はわりとひんぱんに起きている。ループから逃げるというわけではないが、特に僕の場合は、そのことが基本になっているといっていいくらいだ。見てのとおりだよ。君が言うように、音楽が言語であるとすれば、意味内容がそこにあっても、それ自体が他処または外を予感させる一個の「穴」であるし、ループはつくられては消えていくだけであるからかもしれない。それ自体として「意味内容」を受け取ることができない。これはゲーデルの「世界観」、彼の言う「不完全性定理」の簡単明瞭な結論じゃないか? つまりこちら側だけでの証明はありえない。だから音楽の場合、そこに形式の発展というものは見られない。形式の破綻という点で、ベートーヴェンの晩年に起きたのはまさしくそれだった。テオドール・アドルノも似たようなことを言っていた。作曲の際にベートーヴェンの耳が聞こえていなかったこととはたぶん無関係だと思う。それだけではただ「破綻」が起きているだけだと言う人もいるだろうが、はっきり言って、この破綻は誰にでもできる芸当ではない。今までのところ、僕は、無理は無理なりに、それを無手勝流に考えていたし、楽しんでさえいる。
「我は聴く、故に我あり」かな……。そんな風に言いたいときがある。今にして思えば、耳を澄ませてずっと聞いていた感じがするよ。いろんな音が聞こえる。テレビを消して、ラジオを消して、音楽も聞かず、何もしない。馬鹿のように耳をすます。僕の手法だ。今でもたまにやることがある。音がしてくる。いろんな数少ない音。どこかの原住民は虹にも音があると言っていなかったっけ。子供の叫び声だって聞こえる。向こうの建設現場や隣の作業所の音とか。鳥の囀りとか。雨、車、足音、風。そしてひとつの音。あるいはひとつの音階、半音階。どちらかを選ぶのではない。ピアノの一音と一音の間。ファとファ♯の間。それを確固として在るはずの「分身」が聞いているかもしれない。何かを聞いているとき、「我思わない、故に我あり。しかるに分身は存在する」。意識は関係ない。自分の成れの果てだよ。どうしようもない。つまらない音楽。ひょっとしたらいい音楽は聞いたことがないかもしれない。だからと言って、いい文学、いい哲学って、何なんだろう。それが本当に「人生」と関わりがなければいいのだけれど、君は反論したくなるだろうが、我々というか僕のような、初学者、初心者には、そうもいかないところがある。謙遜しているのではない。人生には伝えることがない。
「俺の義務は免除されている。それを考えることさえしてはならない」、ランボーはあえてそう言った。彼の結論はこうだ、「俺は実際に墓の彼方にいるが、伝言などない」。そう、音楽にも「伝言」はないはずだ。
しかし、たしかに「s’entendre parler」という「分裂」がある。だけど、そのように見えたとしても、演奏のときになかなか語り合えないのが通常だよ。分裂が最初にあったのであれば、「ミュージシャン」は普通に記号を発しているつもりでも、相手のほうはそれを受け取りたくない場合がある。否認ではなく、拒否だ。演奏の途中、ロックンロールの人たちは別にして、意味内容だけではなく意味作用に対する拒絶はわりとひんぱんに起きている。ループから逃げるというわけではないが、特に僕の場合は、そのことが基本になっているといっていいくらいだ。見てのとおりだよ。君が言うように、音楽が言語であるとすれば、意味内容がそこにあっても、それ自体が他処または外を予感させる一個の「穴」であるし、ループはつくられては消えていくだけであるからかもしれない。それ自体として「意味内容」を受け取ることができない。これはゲーデルの「世界観」、彼の言う「不完全性定理」の簡単明瞭な結論じゃないか? つまりこちら側だけでの証明はありえない。だから音楽の場合、そこに形式の発展というものは見られない。形式の破綻という点で、ベートーヴェンの晩年に起きたのはまさしくそれだった。テオドール・アドルノも似たようなことを言っていた。作曲の際にベートーヴェンの耳が聞こえていなかったこととはたぶん無関係だと思う。それだけではただ「破綻」が起きているだけだと言う人もいるだろうが、はっきり言って、この破綻は誰にでもできる芸当ではない。今までのところ、僕は、無理は無理なりに、それを無手勝流に考えていたし、楽しんでさえいる。
「我は聴く、故に我あり」かな……。そんな風に言いたいときがある。今にして思えば、耳を澄ませてずっと聞いていた感じがするよ。いろんな音が聞こえる。テレビを消して、ラジオを消して、音楽も聞かず、何もしない。馬鹿のように耳をすます。僕の手法だ。今でもたまにやることがある。音がしてくる。いろんな数少ない音。どこかの原住民は虹にも音があると言っていなかったっけ。子供の叫び声だって聞こえる。向こうの建設現場や隣の作業所の音とか。鳥の囀りとか。雨、車、足音、風。そしてひとつの音。あるいはひとつの音階、半音階。どちらかを選ぶのではない。ピアノの一音と一音の間。ファとファ♯の間。それを確固として在るはずの「分身」が聞いているかもしれない。何かを聞いているとき、「我思わない、故に我あり。しかるに分身は存在する」。意識は関係ない。自分の成れの果てだよ。どうしようもない。つまらない音楽。ひょっとしたらいい音楽は聞いたことがないかもしれない。だからと言って、いい文学、いい哲学って、何なんだろう。それが本当に「人生」と関わりがなければいいのだけれど、君は反論したくなるだろうが、我々というか僕のような、初学者、初心者には、そうもいかないところがある。謙遜しているのではない。人生には伝えることがない。
「俺の義務は免除されている。それを考えることさえしてはならない」、ランボーはあえてそう言った。彼の結論はこうだ、「俺は実際に墓の彼方にいるが、伝言などない」。そう、音楽にも「伝言」はないはずだ。
鈴木創士
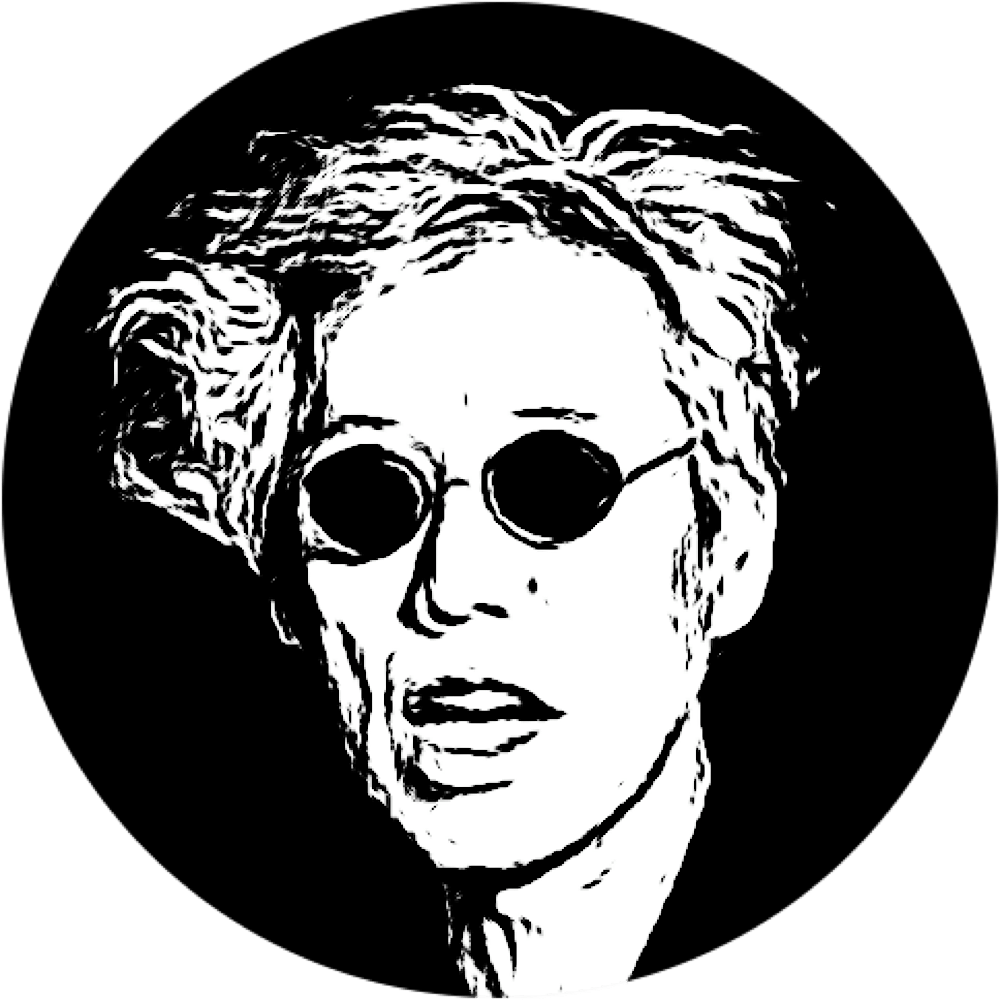
鈴木 創士(すずき そうし)
作家、フランス文学者、評論家、翻訳家、ミュージシャン──著書『アントナン・アルトーの帰還』(河出書房新社)、『中島らも烈伝』(河出書房新社)、『離人小説集』(幻戱書房)、『うつせみ』(作品社)、『文楽徘徊』(現代思潮新社)、『連合赤軍』(編・月曜社)、『芸術破綻論』(月曜社)他、翻訳監修など
【Monologue】3月9日、神戸、「本の栞」で山本精一氏とデュオをやります。






