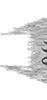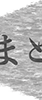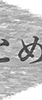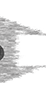2025年4月30日
創士くん、
最近知って感動した一文がある。「本書は小説であるので、最初のページではじまり、最後のページで終わらねばならない」。「著者」による「告」として、ある小説の扉に書かれている。はじまりがあって、終わりがある。あたりまえのことなのだが、それを作品がはじまるまえに「告avis」として読者に読ませ、なおかつ、「ねばならない」と結ぶと、もはやあたりまえではない。この往復書簡の第一葉で書いたことを思い出した。「最初の一行はむつかしい」。いったいどうやってきみとのやりとりをはじめればいいのか、ぼくは途方に暮れていた。ことは小説にかぎらないわけだ。音楽家は最初の一音をどうやって決めるのか。そんなことに悩むのは素人だと玄人は言うかもしれないが、そこへのこだわりがぼくに「騒音書簡」を書かせてきたと言っていいし、今またきみの前葉に「終わり」の予感が記されているのを目にし、思う。いったいどうやって、はじめたものを終えればよいのか。この疑問が共有されていることを知り、ぼくはレーモン・ルーセル『代役』の「告」に感動したわけだ。
第一葉ではこうも書いた。「最初のフレーズは、紙に書かれようが空間に放たれようが、ノイズだ」。つまり、世界になくてよいもの。それがなくても世界は十分になりたっているし、むしろないことが「自然」であるようなもの。それをぼくたちははじめなければならず、いつか終えねばならなかった。いったいどのように、その仕方を決めればよいのか。
バッハに構造はあるのか、という前葉できみが発した問いに引きつけて言えば、はじまりがあって終わりがあるかぎり、ぼくにとっては、そこには「言語的」構造がある。そのほかの「規則」に類することは派生的、二次的なものにすぎない。たった一言や一音でも発せられれば、それは「はじまり」であって、「終わり」を予期させる。あとに続く言葉や音がなければ、それは同時に「終わり」でもある。「はじまり」と「終わり」で切り取られるものは、すべて「言語」ではないかとさえ思っている。この往復書簡でもいいのだが、この「言語」を日常言語から区別するほとんど唯一の指標は、ルーセルの「告」にある「ねばならない」を引き受けるかどうかにある。いつもやっていることを強い自覚のもとに、つまりあたりまえをあたりまえと切り捨てずに、遂行するかどうか。
バッハを組曲や曲集の単位で連続して聴くと、しばしば、この曲(ピース)はどうやって終わるのだろうと思えたり、気づかないうちに──曲中にある「間」と区別がつかず──次のピースに移っていたりすることがある。もっと言えば、この終わり方はいかにも取ってつけた終わり方で、適当に処理しただろう、と文句を言いたくなることも多い。要するに、はじまったものが「終わり」に抵抗していると感じる。総じて、ロマン派時代になるとそんなことは少ない。起承転結のような別種の構造が、はじまって終わるという最小構造にかぶさり、それをほとんど占領し、終わり方も終わり方として工夫されているのが分かる。同じバッハでも、ポリーニの弾くそれは、「歴史哲学徒」というありがたい看板を頂戴した者として言わせてもらえば、ロマン派的に流麗に流れて、一つ一つの「終わり」を納得させる。彼は終わらせようと思って終わらせている。けれどもグールドの弾くバッハは、一つ一つの音が粒立っていて──あの打鍵の強さ!──「変化」しかない。曲の「終わり」も次の曲に移行する「間」でしかない。逆説的なことに、聞く「体験の流れ」を純粋に感じさせてくれるのはグールドのほう。はるか昔、ぼくが知らないあいだにそれははじまり、いつ終わるかの予測を拒み、ぼくはその「只中」にいる。
ここで「変化」とぼくが言うのは、なにかの変化ではない。風景のように変わる「なにか」が、只中にいては同定できない。風景なら風景として持続しているけれども、ここには持続するものがなにもないんだ。「同じ」と「違う」の行き来、入れ替わりが、「変わらないなにか」の同定を妨げる。それは知覚された「音」の状態ですらもはやない。ぼくはスイフトの小説の主人公さながら、言葉も風習もまったく知らない土地に流れ着いた異郷の人として、ただバッハ/グールドの「体験」を観察しているだけ。ぼくはこの「体験」を自分では「経験」していない。ぼくには、真にそこにあると思えるものを、たった今そうしているように、ただ記述することしかできない。「終わり」に抵抗している! と。いったいこのお喋りはいつまで続くのか? これは「終わり」? それとも「休止」? この「言語」は言語であることがかろうじて分かるだけで(それが分かるのは「はじまって-終わる」から)、ぼくの知っている言語には翻訳できない。音楽は音楽どうしでしか「会話」できないだろう。ああ、音楽家になれたら「言葉」を返すのに! と思うだけ。それはぼくがドイツ人と「会話」できないのと本質的に変わりない。
でもそれでよいのだと、今は思える。ぼくは少なくとも、自分が観察している彼らの「体験」においては、「体験」と「経験」は一致している、と知っている。彼らには「体験の内容」と「体験された経験」の分離がない。音楽言語を繰り出すときの「真」がある。それを観察することのできる幸福を、ぼくは味わっている。これ以上の贅沢はあるかね。
第一葉ではこうも書いた。「最初のフレーズは、紙に書かれようが空間に放たれようが、ノイズだ」。つまり、世界になくてよいもの。それがなくても世界は十分になりたっているし、むしろないことが「自然」であるようなもの。それをぼくたちははじめなければならず、いつか終えねばならなかった。いったいどのように、その仕方を決めればよいのか。
バッハに構造はあるのか、という前葉できみが発した問いに引きつけて言えば、はじまりがあって終わりがあるかぎり、ぼくにとっては、そこには「言語的」構造がある。そのほかの「規則」に類することは派生的、二次的なものにすぎない。たった一言や一音でも発せられれば、それは「はじまり」であって、「終わり」を予期させる。あとに続く言葉や音がなければ、それは同時に「終わり」でもある。「はじまり」と「終わり」で切り取られるものは、すべて「言語」ではないかとさえ思っている。この往復書簡でもいいのだが、この「言語」を日常言語から区別するほとんど唯一の指標は、ルーセルの「告」にある「ねばならない」を引き受けるかどうかにある。いつもやっていることを強い自覚のもとに、つまりあたりまえをあたりまえと切り捨てずに、遂行するかどうか。
バッハを組曲や曲集の単位で連続して聴くと、しばしば、この曲(ピース)はどうやって終わるのだろうと思えたり、気づかないうちに──曲中にある「間」と区別がつかず──次のピースに移っていたりすることがある。もっと言えば、この終わり方はいかにも取ってつけた終わり方で、適当に処理しただろう、と文句を言いたくなることも多い。要するに、はじまったものが「終わり」に抵抗していると感じる。総じて、ロマン派時代になるとそんなことは少ない。起承転結のような別種の構造が、はじまって終わるという最小構造にかぶさり、それをほとんど占領し、終わり方も終わり方として工夫されているのが分かる。同じバッハでも、ポリーニの弾くそれは、「歴史哲学徒」というありがたい看板を頂戴した者として言わせてもらえば、ロマン派的に流麗に流れて、一つ一つの「終わり」を納得させる。彼は終わらせようと思って終わらせている。けれどもグールドの弾くバッハは、一つ一つの音が粒立っていて──あの打鍵の強さ!──「変化」しかない。曲の「終わり」も次の曲に移行する「間」でしかない。逆説的なことに、聞く「体験の流れ」を純粋に感じさせてくれるのはグールドのほう。はるか昔、ぼくが知らないあいだにそれははじまり、いつ終わるかの予測を拒み、ぼくはその「只中」にいる。
ここで「変化」とぼくが言うのは、なにかの変化ではない。風景のように変わる「なにか」が、只中にいては同定できない。風景なら風景として持続しているけれども、ここには持続するものがなにもないんだ。「同じ」と「違う」の行き来、入れ替わりが、「変わらないなにか」の同定を妨げる。それは知覚された「音」の状態ですらもはやない。ぼくはスイフトの小説の主人公さながら、言葉も風習もまったく知らない土地に流れ着いた異郷の人として、ただバッハ/グールドの「体験」を観察しているだけ。ぼくはこの「体験」を自分では「経験」していない。ぼくには、真にそこにあると思えるものを、たった今そうしているように、ただ記述することしかできない。「終わり」に抵抗している! と。いったいこのお喋りはいつまで続くのか? これは「終わり」? それとも「休止」? この「言語」は言語であることがかろうじて分かるだけで(それが分かるのは「はじまって-終わる」から)、ぼくの知っている言語には翻訳できない。音楽は音楽どうしでしか「会話」できないだろう。ああ、音楽家になれたら「言葉」を返すのに! と思うだけ。それはぼくがドイツ人と「会話」できないのと本質的に変わりない。
でもそれでよいのだと、今は思える。ぼくは少なくとも、自分が観察している彼らの「体験」においては、「体験」と「経験」は一致している、と知っている。彼らには「体験の内容」と「体験された経験」の分離がない。音楽言語を繰り出すときの「真」がある。それを観察することのできる幸福を、ぼくは味わっている。これ以上の贅沢はあるかね。