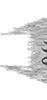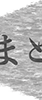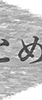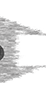2025年3月31日
歴史哲学徒たる君へ
非常に難解な手紙をありがとう。君の言葉を吟味して、ない知恵を絞って少し考えてみた。構造……後からわかる構造…そして構造の全体。だが、そのようにバッハを聞いているのだとは確信がもてない。僕はいつもそれから落っこちる。僕はこの構造から脱落する。全体に爆発が起きたとしても、構造が街路に降りてくるのではなく、知らぬ間にこちらが構造の外にある街路に立っていることを自覚してびっくりする。何かがそれらすべてを一瞬にして全滅させる。
ところで、バッハに構造があるとすれば、そこには数があるということだ。数はそのまま構成を意味するわけではない。1と2と3が現れる。2は1に割れることもあるが、時間を逆向きに考え、曲を逆にたどってまた元に戻ると、すでに2が1に割れたのだとすれば、それゆえに3になる。詳細は省くが、0+1=1+1=2-1=1+1=2+1=3これがバッハの構造を予想するものの最初の現れであり、基盤となる。ポリフォニーだけでは構造は出現しない。ほぼ同時代のイタリアやイギリスのルネサンス音楽と聴き比べてみれば、そういう風に思わざるを得ない。バッハにマドリガーレが入る余地はないと言っていい。2と3は矛盾した様態として関係づけられると同時に、それは1、究極的には3を予表させる非関係として把握できる。しかし合一も統一もなされないし、全体はそういうものとは別のものだし、それは常に一瞬にして逃げていくのがわかる。音は奥行きをもつが、僕にはむしろそれぞれ分解されて聞こえる。僕にとってバッハの音楽はそのようなものだとしか言いようがない。他の音楽とは全然違う。だがそこに構造はあるのだろうか。そしてそれぞれの音がそれ自体において重層的な重なりをもとうとするものだとしても、そこに空間は生まれるのだろうか。誰もがそれを空間のように捉えるのだろうが、そうだとしても、はたしてこの空間は構造であるのだろうか。僕にはいまだにわからない。それが構造であれば、それは言語だということになる。我々の騒音書簡は終わりに近づいているらしいが(自分でもそう感じている)、このやりとりでずっと言ってきたように、君が言うようには、僕にはそう言い切れない感覚がいつも残ってしまう。言葉を喋り思考するという経験があり、言葉を書くという経験があり、音を聞くという経験があり、音を演奏するという経験がある。言語を扱う作家として、ミュージシャンとして、いつも僕はそのはざまで引き裂かれている。この矛盾が豊かなものと思えるときもあれば、空虚を強く感じることもある。不可能なコミュニケーションがあり、いつもそれは不可能であり、音と音は不可能性においてしか出会わないが、それは狂気の表象でもない。だから戦いを続行しなければならない。
だが言語以前のものがある。言葉が、あるいは言語の体系が内側から侵食されるとすれば、フーコーが言うように、それは言語の崩壊を示していて、そのような経験があるということだ。またアルトーに戻るようで気が引けるが、僕の音楽についての考え方、感じ方が、いつの間にかアルトーの「残酷の演劇」(『演劇とその分身』)に影響されていることに後になって気づいたという経緯がある。それは第一に「言葉の空虚」、その分裂を示すものだったが、これが何かを宙吊りにする。何をだろう? 我々の経験そのものを宙吊りにするのだ。その厚みのなかを僕はさまよっている。それが希薄な厚みであったり、極端に薄いこともあるが、それを表現形態と呼んでいいのかどうかいまだによくわからない。現実が乖離する。妄想が乖離する。空虚が現れる。僕はそこにいる。どうしようもない。音楽? 言葉や音のオペレーション? 狂気が言語であるように、表現の混乱という意味でなら、音楽はまず言語であると言える。しかし言葉が言語の単位であるとすれば、音は言葉なのだろうか。音は言葉、または文字であり、あるいは音声、声の原型なのか。つまりそれは「歌」なのか。わからない。アルトーが言うように(「アルフレッド・ジャリ劇場」)、在るのは「その発話行為がかき立てる空気の移動、ただそれだけだ」と感じるときがある。あるいはダンス。踊れるダンス、踊ろうにも踊れないダンス。暴力と非暴力。象徴的な操作がどこにあるのかいつも見当がつかない。失敗であってもアルトーは演劇を成し遂げたが、僕は何も成し遂げていない。賭けをしているだけ。僕が演奏するとして、客が気分が悪くなって帰ってくれればいい。もちろん観客の死を望んでいるわけではないが、嫌がらせをやっている。はい。ここは音楽劇場です。入り口が見えるでしょ。古い舞台があって、真紅の緞帳がかかっています。床に小さな明かりが灯っています。足元に気をつけてください。こびとの司会者が口をもぐもぐやっていますが、何も聞こえませんし、そもそも何かを喋っているのでしょうか。破けた外国語のポスターが外の汚れた壁に貼られている。夜のとばりが降り始める。夕暮れの大気は少し冷えてきたようだ。観客は入り口に入ろうとしてそれがどこだったのかわからず、きょろきょろしている。あれ、劇場なんかそこにはなかったのだ。
ところで、バッハに構造があるとすれば、そこには数があるということだ。数はそのまま構成を意味するわけではない。1と2と3が現れる。2は1に割れることもあるが、時間を逆向きに考え、曲を逆にたどってまた元に戻ると、すでに2が1に割れたのだとすれば、それゆえに3になる。詳細は省くが、0+1=1+1=2-1=1+1=2+1=3これがバッハの構造を予想するものの最初の現れであり、基盤となる。ポリフォニーだけでは構造は出現しない。ほぼ同時代のイタリアやイギリスのルネサンス音楽と聴き比べてみれば、そういう風に思わざるを得ない。バッハにマドリガーレが入る余地はないと言っていい。2と3は矛盾した様態として関係づけられると同時に、それは1、究極的には3を予表させる非関係として把握できる。しかし合一も統一もなされないし、全体はそういうものとは別のものだし、それは常に一瞬にして逃げていくのがわかる。音は奥行きをもつが、僕にはむしろそれぞれ分解されて聞こえる。僕にとってバッハの音楽はそのようなものだとしか言いようがない。他の音楽とは全然違う。だがそこに構造はあるのだろうか。そしてそれぞれの音がそれ自体において重層的な重なりをもとうとするものだとしても、そこに空間は生まれるのだろうか。誰もがそれを空間のように捉えるのだろうが、そうだとしても、はたしてこの空間は構造であるのだろうか。僕にはいまだにわからない。それが構造であれば、それは言語だということになる。我々の騒音書簡は終わりに近づいているらしいが(自分でもそう感じている)、このやりとりでずっと言ってきたように、君が言うようには、僕にはそう言い切れない感覚がいつも残ってしまう。言葉を喋り思考するという経験があり、言葉を書くという経験があり、音を聞くという経験があり、音を演奏するという経験がある。言語を扱う作家として、ミュージシャンとして、いつも僕はそのはざまで引き裂かれている。この矛盾が豊かなものと思えるときもあれば、空虚を強く感じることもある。不可能なコミュニケーションがあり、いつもそれは不可能であり、音と音は不可能性においてしか出会わないが、それは狂気の表象でもない。だから戦いを続行しなければならない。
だが言語以前のものがある。言葉が、あるいは言語の体系が内側から侵食されるとすれば、フーコーが言うように、それは言語の崩壊を示していて、そのような経験があるということだ。またアルトーに戻るようで気が引けるが、僕の音楽についての考え方、感じ方が、いつの間にかアルトーの「残酷の演劇」(『演劇とその分身』)に影響されていることに後になって気づいたという経緯がある。それは第一に「言葉の空虚」、その分裂を示すものだったが、これが何かを宙吊りにする。何をだろう? 我々の経験そのものを宙吊りにするのだ。その厚みのなかを僕はさまよっている。それが希薄な厚みであったり、極端に薄いこともあるが、それを表現形態と呼んでいいのかどうかいまだによくわからない。現実が乖離する。妄想が乖離する。空虚が現れる。僕はそこにいる。どうしようもない。音楽? 言葉や音のオペレーション? 狂気が言語であるように、表現の混乱という意味でなら、音楽はまず言語であると言える。しかし言葉が言語の単位であるとすれば、音は言葉なのだろうか。音は言葉、または文字であり、あるいは音声、声の原型なのか。つまりそれは「歌」なのか。わからない。アルトーが言うように(「アルフレッド・ジャリ劇場」)、在るのは「その発話行為がかき立てる空気の移動、ただそれだけだ」と感じるときがある。あるいはダンス。踊れるダンス、踊ろうにも踊れないダンス。暴力と非暴力。象徴的な操作がどこにあるのかいつも見当がつかない。失敗であってもアルトーは演劇を成し遂げたが、僕は何も成し遂げていない。賭けをしているだけ。僕が演奏するとして、客が気分が悪くなって帰ってくれればいい。もちろん観客の死を望んでいるわけではないが、嫌がらせをやっている。はい。ここは音楽劇場です。入り口が見えるでしょ。古い舞台があって、真紅の緞帳がかかっています。床に小さな明かりが灯っています。足元に気をつけてください。こびとの司会者が口をもぐもぐやっていますが、何も聞こえませんし、そもそも何かを喋っているのでしょうか。破けた外国語のポスターが外の汚れた壁に貼られている。夜のとばりが降り始める。夕暮れの大気は少し冷えてきたようだ。観客は入り口に入ろうとしてそれがどこだったのかわからず、きょろきょろしている。あれ、劇場なんかそこにはなかったのだ。
鈴木創士

鈴木 創士(すずき そうし)
作家、フランス文学者、評論家、翻訳家、ミュージシャン──著書『アントナン・アルトーの帰還』(河出書房新社)、『中島らも烈伝』(河出書房新社)、『離人小説集』(幻戱書房)、『うつせみ』(作品社)、『文楽徘徊』(現代思潮新社)、『連合赤軍』(編・月曜社)、『芸術破綻論』(月曜社)他、翻訳監修など
【Monologue】鈴木創士『冒険者たち 特権的文学のすすめ』(水声社)が出ました。