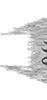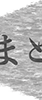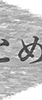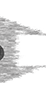2025年4月30日
市やん、
前回、君は「君の音楽」の歴史を語った。あの頃のNのことを思い浮かべながら、読んだ。君たちは京大生だった、やばい京大生だったけれど……。政治活動は音楽とともにあったとは言えないにしても、極左暴力性(!)と音楽があった、とは言える。僕の音楽の歴史はどうなのか。回顧すべきものはないし、クラシック音楽の後、それと並行してロックやジャズが登場したはずだが、そんな「歴史」もほとんど思い出すことができない。僕にとっては、何もかもが一緒くただった。「進歩」はなかった。それどころか、いままでずっと同じ音を聞いている気がする。「同じ音」が鳴っているのだけれど、それをしかと聴き取ったぞと言い切ることができない。森田潤と一緒にやるようになって、いっそうそう感じることがある。〈音楽は「経験」に対し直角に交わり、それぞれの「いま」から僕を離脱させる〉。それはそのとおりだと思う。最近、バッハの『フランス組曲』を聞いている。マイナーで始まるこの構成には脱帽してしまう。しかしこのバッハのつくり出す幾何学風の音は僕に対して垂直に、あるいは直角にしか交わることはない。円も接線もない。それで、たとえ音楽的経験にしろ、経験は豊かになったのか。いや、豊かになったはずの「経験」にはそのつどそれらしい実体が消えてしまっている。我々はそれを反省することも吟味することもできない。これに構造があったとしても創造行為、または制作なるものは、それから何らかの形式、内容、ましてや恩恵を何も受け取ることはない。
我々の書簡はなるほど「対話」形式だが、対話とはいったいなんだろう。我々の対話はかなり風変わりであるし、それにこれを読む人たちもきっとそう感じているだろうが、笑ってしまうが、対話としてはほぼ成立していないように思われる。君にとっても僕にとっても、それを示し合わせたわけではないし、もちろんそれが狙いというわけではなかったが、我々だけの問題提起(?)としてはそれでいいのではないか。そこにはいつも第三者だっている。いわゆる「対話」は当然のように不毛に終わるしかない。特筆すべきことは、お互い個人的に電話して話しをしても、この書簡については一切何も話さなかったことだ。事前の打ち合わせはまったくなしだった。お互いそうしようと決めたわけではないのに、自然にそうなった。だが、我々がそれぞれ無言で感知した瞬間がきっとあったのかもしれない。つまり、いいコンビじゃないか! 往復書簡なのだから考える時間はあったのか? 音楽と言語の関係をめぐっては、自分自身いまだに歯切れの悪い思いをしたままだ。だが、君にとっての「哲学」について僕が口を差し挟むことはないし、そんなことは僕には無理だが、僕にとって、「文学」、「書くこと」は、バルトが言うように、「言語活動の転倒」によってしか成立しないと頑固に確信している。それに自分の書くものはけっして「発言」や「意見」ではないし、「描写」でも、たとえ昔のことを書いたとしても「回想」でもないし、そのようなものはそのようなもの自体として、自分の書くもののなかで価値を有することはない。だから「作家」の「発言」には気をつけよう! そこにはいつも端的に悪い意味で「不正」(「不正の神秘」ではない)の臭いを嗅ぎ取らざるを得ない。表現の機能をそれに与えるなどもってのほかだし、まずもってどっちらけだ。書くという行為にとって、映画がやる「不正」と同じことができたらきっと面白いが、それをやり遂げた者はまだいないし、方法としてはかなり無理な話だ。
我々の対話は、つまりこの往復書簡は、終わりに近づいているらしい。始まりがあれば終わりがある。この観念論に何らの同一性を見つけることは難しいのだろうし、差異は反復されるものでもあるが、それを永遠に続けるわけにはいかないだろう。ある一点から先に帰還はないのだし、回帰するものは、現実と妄想がほとんど一致するあの地点にしか存在できないだろう。ブランキやニーチェが思い出されるが、その話はやめておこう。君はまた戻ってくるのだろうか。それこそばらばらになって、バルバラの歌のように、「戻ってくるのがいつなのか言ってくれ」とは言えない。突然、どこかで往復書簡が再開されるかもしれない? 俺は出発した。俺はまたぞろ出発をやり直す。出発は次の出発のためにしかなかったし、出発しただけで、いつもどこかにたどり着けたのではない。俺は出発したのか。ああ、たぶん。ランボーは、出発を新たな「騒音」と言った。そうかもしれない。そうであればどんなにいいだろう。
鈴木創士
我々の書簡はなるほど「対話」形式だが、対話とはいったいなんだろう。我々の対話はかなり風変わりであるし、それにこれを読む人たちもきっとそう感じているだろうが、笑ってしまうが、対話としてはほぼ成立していないように思われる。君にとっても僕にとっても、それを示し合わせたわけではないし、もちろんそれが狙いというわけではなかったが、我々だけの問題提起(?)としてはそれでいいのではないか。そこにはいつも第三者だっている。いわゆる「対話」は当然のように不毛に終わるしかない。特筆すべきことは、お互い個人的に電話して話しをしても、この書簡については一切何も話さなかったことだ。事前の打ち合わせはまったくなしだった。お互いそうしようと決めたわけではないのに、自然にそうなった。だが、我々がそれぞれ無言で感知した瞬間がきっとあったのかもしれない。つまり、いいコンビじゃないか! 往復書簡なのだから考える時間はあったのか? 音楽と言語の関係をめぐっては、自分自身いまだに歯切れの悪い思いをしたままだ。だが、君にとっての「哲学」について僕が口を差し挟むことはないし、そんなことは僕には無理だが、僕にとって、「文学」、「書くこと」は、バルトが言うように、「言語活動の転倒」によってしか成立しないと頑固に確信している。それに自分の書くものはけっして「発言」や「意見」ではないし、「描写」でも、たとえ昔のことを書いたとしても「回想」でもないし、そのようなものはそのようなもの自体として、自分の書くもののなかで価値を有することはない。だから「作家」の「発言」には気をつけよう! そこにはいつも端的に悪い意味で「不正」(「不正の神秘」ではない)の臭いを嗅ぎ取らざるを得ない。表現の機能をそれに与えるなどもってのほかだし、まずもってどっちらけだ。書くという行為にとって、映画がやる「不正」と同じことができたらきっと面白いが、それをやり遂げた者はまだいないし、方法としてはかなり無理な話だ。
我々の対話は、つまりこの往復書簡は、終わりに近づいているらしい。始まりがあれば終わりがある。この観念論に何らの同一性を見つけることは難しいのだろうし、差異は反復されるものでもあるが、それを永遠に続けるわけにはいかないだろう。ある一点から先に帰還はないのだし、回帰するものは、現実と妄想がほとんど一致するあの地点にしか存在できないだろう。ブランキやニーチェが思い出されるが、その話はやめておこう。君はまた戻ってくるのだろうか。それこそばらばらになって、バルバラの歌のように、「戻ってくるのがいつなのか言ってくれ」とは言えない。突然、どこかで往復書簡が再開されるかもしれない? 俺は出発した。俺はまたぞろ出発をやり直す。出発は次の出発のためにしかなかったし、出発しただけで、いつもどこかにたどり着けたのではない。俺は出発したのか。ああ、たぶん。ランボーは、出発を新たな「騒音」と言った。そうかもしれない。そうであればどんなにいいだろう。