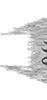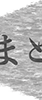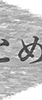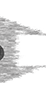2025年5月29日
Sô-siくん、
かくしてコーダ(終結部)である。終わりはいやがおうでも訪れる。終わらせ方を考えねばならない。このひと月つらつらと、しかしずっと、それを考えてきた。しかしなにの終わりなのだろう。対話だとして、この対話はどう終わるのがふさわしい? いつのころからだろうか、僕はこの連載を続けるコツのようなものを掴んだ気がしていた。「対話としてはほぼ成立していない」と前葉できみは書いたが、成立した対話は、その範例であるプラトンを読めばすぐに分かるように、第三者が「書いた」ものだ。観察者である彼が、ソクラテスと弟子たちの会話から展開と終わりを引き出したカッコ付きの「対話」。実際のやりとりがあんなに「読める」ものになっていたとは想像しがたい。僕たちの対話にはプラトン役を果たせる観察者がいない。いや、正確には佐藤薫がもの言わぬ司会者として後ろに控えていることで、僕たちは第三者のいない対話の現場に放り出されてきた。ずっと、「さあ語りたまえ」とだけ言われてきた。その結果僕は、きみの言葉からその都度、それについてならこう言える、言いたいと思えるなにか──書かれた「内容」とはかぎらない──を拾いだして反応してきた。だからきみからの言葉があるかぎり、僕はいつまでもこの対話を続けることができるような気がしていた。要するに、そんなに難しいことではなくなっていたのだ。「次回」を書くことが。僕は前回「終わり」について書いたけれども、それさえ「次回」のためであり、今回もまたそうだ。きみの次葉を待ちつつ、僕はいまこれを書いている。いつまでも続けられることの悪しき副産物が、終わらせ方を見失う、というこのひと月の僕の状態である。これまでとは別のなにかをコーダとして導入しなければ、僕にはこの対話を終えられない。
それはフーガと同じだろう。僕たちは互いのあとを追いかけあってきた。つまり、互いの先を走ってもいた。〈騒音〉という主題の存在すること──それは連載がはじまる前に与えられていた──がそれぞれに変奏を可能にし、二つの旋律のズレと同時性を一つの曲にしていた。その意味ではジャズのユニットとも似ていたかもしれない。いずれにしても、終わりへと向かう流れは、それとして、第三者にも分かるように「導入」されなければならず、僕たちの場合、それは「終わり」が話題になったこと自体だった。ではどう終わらせる? と読者がきっと問うに違いない一言をきみが発したと僕が思い、僕がそれに反応することで「終わり」が〈騒音〉とは一定別の主題として成立し、僕たちは最後の一音を同時に発するという課題を自分たちに与えた。フーガはまさにそんなふうにしてしか終わらない。互いに追いつく時間をもつわけだ。二つの旋律の最後の音、二つの文の最後のピリオドは、それぞれが別々に打っても同時に「鳴る」。いかに噛み合わない旋律を奏でてきたとしても、あるいは、ここで僕が終えることを拒否する旨を記したとしても、きみが筆を置けば僕は反応すべきものを失い、そのあともう一回だけソロを聴かせることになり、それは読者にはそのままコーダになる。
しかし、プラトンが記録したソクラテスたちの対話も、その最後の最後は同じようなものだったではないか、とふと思う。死を前にした彼が弟子のクリトンに向かって発した言葉だ。〈我々はアスクレピオスに雄鶏一羽の借りがある〉(『パイドン』)。その〈借り〉を返しておいてくれたまえ。〈借り〉の中身がはっきりしないため数多の読者を困惑させ、勝手な解釈を可能にし、それがまた苛立ちのたねとなって別の解釈を生みだし、いつのまにか「哲学」そのものである伝統を作ってしまった最後の言葉。つまり、終わること、終えることに失敗してしまったピリオド。それは「神は神託によってほんとうのことを語り、人間は歌によって感謝する」という構図だけをあとに残す。語られた〈ほんとうのこと〉の内容も、したがって〈借り〉の中身もついに明かさない、さらにしたがって、なにが「終わった」のかという問いそのものを無効にする「終わり」。
「終わり」を考えるとはどうやら、それまで現場にいなかった観察者=第三者に自分がなる行為であるようだ。いやおうなしにこれまでを振り返らされ、「はじまり」に連れ戻される。僕はいま異邦人のように僕たちのやり取り全体を眺めている。「歴史」にしている。すると最初の一葉も、ゲンズブールがジェーン・バーキンに歌わせたショパン前奏曲4番のように聞こえてくる。そこにはジミー・ペイジが弾いた同曲の音色も被さっているから、〈同じ〉と〈違う〉はいっそう〈同じ〉にもいっそう〈違う〉にもなる。だから僕は──僕「たち」とは言うまい──はじめることができた。最初から、僕自身が第三者でもあったのだ。いまになってそう気づく。そうでなければはじめることができただろうか。きみの言葉に反応する、とは僕が僕のなかにある〈同じ〉や〈違う〉を発見する作業にほかならず、僕は言わばきみを鏡にしてそれをやっていたにすぎない。だからこれは対話ではなかった、と言うきみは正しい。しかし、そうではない即興二重奏など聴いていて面白いはずがなかろう、とも思う。僕たち──今度ははっきり「たち」と言う──に必要であったのは、互いの独奏を許す寛容さだけであったろう。それを知っていたから、僕はときに思い切った異音を挟むこともできた。いままでありがとう。これでようやく、対話する友人の関係に戻ることができるね。対話なんて他人に聞かせるものではない、とつくづく思う。しかしそう語るかぎり、僕は対話の道を踏み外し、「騒音書簡」season2をすでにはじめたのも同然であるわけだが。
それはフーガと同じだろう。僕たちは互いのあとを追いかけあってきた。つまり、互いの先を走ってもいた。〈騒音〉という主題の存在すること──それは連載がはじまる前に与えられていた──がそれぞれに変奏を可能にし、二つの旋律のズレと同時性を一つの曲にしていた。その意味ではジャズのユニットとも似ていたかもしれない。いずれにしても、終わりへと向かう流れは、それとして、第三者にも分かるように「導入」されなければならず、僕たちの場合、それは「終わり」が話題になったこと自体だった。ではどう終わらせる? と読者がきっと問うに違いない一言をきみが発したと僕が思い、僕がそれに反応することで「終わり」が〈騒音〉とは一定別の主題として成立し、僕たちは最後の一音を同時に発するという課題を自分たちに与えた。フーガはまさにそんなふうにしてしか終わらない。互いに追いつく時間をもつわけだ。二つの旋律の最後の音、二つの文の最後のピリオドは、それぞれが別々に打っても同時に「鳴る」。いかに噛み合わない旋律を奏でてきたとしても、あるいは、ここで僕が終えることを拒否する旨を記したとしても、きみが筆を置けば僕は反応すべきものを失い、そのあともう一回だけソロを聴かせることになり、それは読者にはそのままコーダになる。
しかし、プラトンが記録したソクラテスたちの対話も、その最後の最後は同じようなものだったではないか、とふと思う。死を前にした彼が弟子のクリトンに向かって発した言葉だ。〈我々はアスクレピオスに雄鶏一羽の借りがある〉(『パイドン』)。その〈借り〉を返しておいてくれたまえ。〈借り〉の中身がはっきりしないため数多の読者を困惑させ、勝手な解釈を可能にし、それがまた苛立ちのたねとなって別の解釈を生みだし、いつのまにか「哲学」そのものである伝統を作ってしまった最後の言葉。つまり、終わること、終えることに失敗してしまったピリオド。それは「神は神託によってほんとうのことを語り、人間は歌によって感謝する」という構図だけをあとに残す。語られた〈ほんとうのこと〉の内容も、したがって〈借り〉の中身もついに明かさない、さらにしたがって、なにが「終わった」のかという問いそのものを無効にする「終わり」。
「終わり」を考えるとはどうやら、それまで現場にいなかった観察者=第三者に自分がなる行為であるようだ。いやおうなしにこれまでを振り返らされ、「はじまり」に連れ戻される。僕はいま異邦人のように僕たちのやり取り全体を眺めている。「歴史」にしている。すると最初の一葉も、ゲンズブールがジェーン・バーキンに歌わせたショパン前奏曲4番のように聞こえてくる。そこにはジミー・ペイジが弾いた同曲の音色も被さっているから、〈同じ〉と〈違う〉はいっそう〈同じ〉にもいっそう〈違う〉にもなる。だから僕は──僕「たち」とは言うまい──はじめることができた。最初から、僕自身が第三者でもあったのだ。いまになってそう気づく。そうでなければはじめることができただろうか。きみの言葉に反応する、とは僕が僕のなかにある〈同じ〉や〈違う〉を発見する作業にほかならず、僕は言わばきみを鏡にしてそれをやっていたにすぎない。だからこれは対話ではなかった、と言うきみは正しい。しかし、そうではない即興二重奏など聴いていて面白いはずがなかろう、とも思う。僕たち──今度ははっきり「たち」と言う──に必要であったのは、互いの独奏を許す寛容さだけであったろう。それを知っていたから、僕はときに思い切った異音を挟むこともできた。いままでありがとう。これでようやく、対話する友人の関係に戻ることができるね。対話なんて他人に聞かせるものではない、とつくづく思う。しかしそう語るかぎり、僕は対話の道を踏み外し、「騒音書簡」season2をすでにはじめたのも同然であるわけだが。