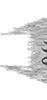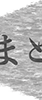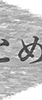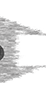2024年12月27日
Sôくん、
きみの新しい本はどんなものになるのかな。おっと、不意打ちを楽しみにしているので、出来上がるまで教えないでくれ。こちらはすでに書きはじめている。それなりに長いものにしたいので、それなりに準備もしてきたのだが、準備しすぎるといつまでもはじめられないのではないかという危惧も生まれてきた──なにしろ無職になると時間の後門が開いたままになってしまう──ので、とりあえず固まったと思しきところまではかたちにしてしまおう、と。しかし、このはじまりの時間はいつはじまったのかとも、いざ書きはじめると思ってしまうもので、前門はどんどん過去に遡っていって、これも開いたままになる。そんな時間を過ごしていると、〈歌〉が聴けなくなる。言葉の意味が与える〈いま〉の時間が煩わしくなる。昔の歌であっても、意味が伝わるのは〈いま〉であって、そこに時間が固着してしまうことが、流れているこの〈書いているいま〉を寸断してしまい、なにか邪魔をされた気分になる。そんなわけで、ここのところバッハの「イギリス組曲」とクセナキスの「ペルセポリス」を交互に繰り返し聴いている。展開がドラマチックな音楽は、その構成が、自分の構成しつつある〈作品〉の構成途上性とぶつかる。といって、まったくの環境音楽のようなものは、そのだらしなさ、無構成性がこちらの足を引っ張り、書かない時間へと連れ戻される気分になる。というわけで、構成が次第に〈図〉として浮かび上がってくるものの、それは別の構成のなかからであって、新しい〈図〉は古い構成を〈地〉の位置に沈める、という構図の反転を微妙に、かつ聴き直すたびに別様に聞かせる曲が、この〈いま〉には相応しい。それがどうして「イギリス組曲」と「ペルセポリス」なのかと言われると、分析的には、また歴史的にも、いろいろ書けるだろうが、そんな暇もこの〈いま〉にはない。要は、ぼくにおける言語の状態と同調するような曲を選んでいる──「イギリス組曲」のような、「ペルセポリス」のような〈作品〉にしたい!──ので、客観的分析と主観的記述の隙間を埋めるべく説明するのは、まさにそんな暇はないという次第。
そこへ閑話休題、まあ一休みしたまえ、という感じで、きみたちの新しいアルバムが届いた。日本語を全面的にフィーチャーした『帝国は滅ぶ──俺たちは決して働かないだろう』。まったくもう、こちらの状況を知って邪魔をするつもりか? とも一瞬思ったが、なるほどよい休息になった。いや、なんかきみたちがぼくのここでの挑発に応じてくれたような気がして、すなおに嬉しかった。別段、挑発したつもりはなかったのだが、そうか、ぼくはきみたちに対し、言葉と音楽の関係はきみたちにおいてどうなっているのだ? と問うてきたのかも、と事後的に気づかせてくれた。
ずいぶん以前のことになるが、どんなバンドも歴史の総括だ、といったようなことをぼくはここで書いた。別の言い方をすれば、どんな新曲もある意味カバー。そう思っているので、ぼくはカバー・アルバムの類がけっこう好きで、独自のサウンドを作ってきたバンドが、その色でどう自分たちの過去を調理するのだろう、という興味でよく手を伸ばす。というか、ロック史の全体を自分たちの色に染め直すことができてようやく、バンドは「完成」するような気がしている。エアロスミスのHonkin’ on Boboとか、レイジ・アゲインスト・ザ・マシーンのRenegadesとか。ストーンズのBlue & Lonesomeはカバーというより原点回帰で、好きではあるけれどあまり面白味はなく(というより、ずっとこれだったじゃん、という確認)、パティ・スミスのTwelveは「大御所」がやってみせましょうという嫌味が際立つ。エアロスミスとレイジの二作にはそんなところが微塵もない。自分たち風味のアレンジを歴史に施して、音楽史に一本の線を引いてみせる。〈俺たちはここまで来たぞ〉。きみたちの新アルバムも、ああこれがきみのいう「偽古典主義」ね、とストレートに受け取ることができた。18世紀オペラから、パンク、ラップ、レゲエまでを文字どおりきみたち色にカバーしている。鈴木創士はここでは言葉の人に徹し、森田潤による「編集による作曲」と、棲み分けることで協働している。詩と音がちゃんと「結婚」(©ワグナー)
ぼくは現代のラップミュージックはパンクの後継だと思ってきたが、それを実証された気分だね。ただし、その連続性はぼくのなかでは「街頭」で果たされてきた。ザ・スターリンがその昔、戸村選挙(三里塚空港反対同盟の代表・戸村一作が参院選に出た)のときにトラックの上でやった演奏、Lofoforaがパリの人種差別反対集会でやったライブ、映画Do the Right ThingのなかのPublic Enemyが一直線に並んでいる。そしてこの線が、現代の特にレゲエにおいて、ダンスのためのトラック・メイキングの技法に「昇華」されていることに、一抹の寂しさを感じてきた。聞くことが、スタジオと、大きさはさておき「箱」のなかを結ぶ回路に閉じ込められては、それを「カルチャー」と呼ぶ気にはもうなれない。サウンド・デモをサウンド・デモと呼んでもねえ……。しかし、きみたちの「ラップ帝国は滅ぶ」はカニエ・ウェストのPowerと充分張り合えるぞ。ぜひかっこいいMVを作ってYouTubeにあげてくれたまえ。それがヒットすれば、新たな「街頭」が生まれたと思えるかもしれない。空中へと、そとへ向かう線が伸びるかもしれない。ぼくの〈いま〉はそういう空想で、ペルセポリス神殿とつながっている。そのアルバムに付属した、数々のDJ的介入によるリミックスの試みは、クセナキスによる構成を台無しにしているようにしか思えず、一度聴いておしまいにした。
そこへ閑話休題、まあ一休みしたまえ、という感じで、きみたちの新しいアルバムが届いた。日本語を全面的にフィーチャーした『帝国は滅ぶ──俺たちは決して働かないだろう』。まったくもう、こちらの状況を知って邪魔をするつもりか? とも一瞬思ったが、なるほどよい休息になった。いや、なんかきみたちがぼくのここでの挑発に応じてくれたような気がして、すなおに嬉しかった。別段、挑発したつもりはなかったのだが、そうか、ぼくはきみたちに対し、言葉と音楽の関係はきみたちにおいてどうなっているのだ? と問うてきたのかも、と事後的に気づかせてくれた。
ずいぶん以前のことになるが、どんなバンドも歴史の総括だ、といったようなことをぼくはここで書いた。別の言い方をすれば、どんな新曲もある意味カバー。そう思っているので、ぼくはカバー・アルバムの類がけっこう好きで、独自のサウンドを作ってきたバンドが、その色でどう自分たちの過去を調理するのだろう、という興味でよく手を伸ばす。というか、ロック史の全体を自分たちの色に染め直すことができてようやく、バンドは「完成」するような気がしている。エアロスミスのHonkin’ on Boboとか、レイジ・アゲインスト・ザ・マシーンのRenegadesとか。ストーンズのBlue & Lonesomeはカバーというより原点回帰で、好きではあるけれどあまり面白味はなく(というより、ずっとこれだったじゃん、という確認)、パティ・スミスのTwelveは「大御所」がやってみせましょうという嫌味が際立つ。エアロスミスとレイジの二作にはそんなところが微塵もない。自分たち風味のアレンジを歴史に施して、音楽史に一本の線を引いてみせる。〈俺たちはここまで来たぞ〉。きみたちの新アルバムも、ああこれがきみのいう「偽古典主義」ね、とストレートに受け取ることができた。18世紀オペラから、パンク、ラップ、レゲエまでを文字どおりきみたち色にカバーしている。鈴木創士はここでは言葉の人に徹し、森田潤による「編集による作曲」と、棲み分けることで協働している。詩と音がちゃんと「結婚」(©ワグナー)
ぼくは現代のラップミュージックはパンクの後継だと思ってきたが、それを実証された気分だね。ただし、その連続性はぼくのなかでは「街頭」で果たされてきた。ザ・スターリンがその昔、戸村選挙(三里塚空港反対同盟の代表・戸村一作が参院選に出た)のときにトラックの上でやった演奏、Lofoforaがパリの人種差別反対集会でやったライブ、映画Do the Right ThingのなかのPublic Enemyが一直線に並んでいる。そしてこの線が、現代の特にレゲエにおいて、ダンスのためのトラック・メイキングの技法に「昇華」されていることに、一抹の寂しさを感じてきた。聞くことが、スタジオと、大きさはさておき「箱」のなかを結ぶ回路に閉じ込められては、それを「カルチャー」と呼ぶ気にはもうなれない。サウンド・デモをサウンド・デモと呼んでもねえ……。しかし、きみたちの「ラップ帝国は滅ぶ」はカニエ・ウェストのPowerと充分張り合えるぞ。ぜひかっこいいMVを作ってYouTubeにあげてくれたまえ。それがヒットすれば、新たな「街頭」が生まれたと思えるかもしれない。空中へと、そとへ向かう線が伸びるかもしれない。ぼくの〈いま〉はそういう空想で、ペルセポリス神殿とつながっている。そのアルバムに付属した、数々のDJ的介入によるリミックスの試みは、クセナキスによる構成を台無しにしているようにしか思えず、一度聴いておしまいにした。