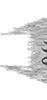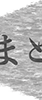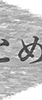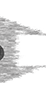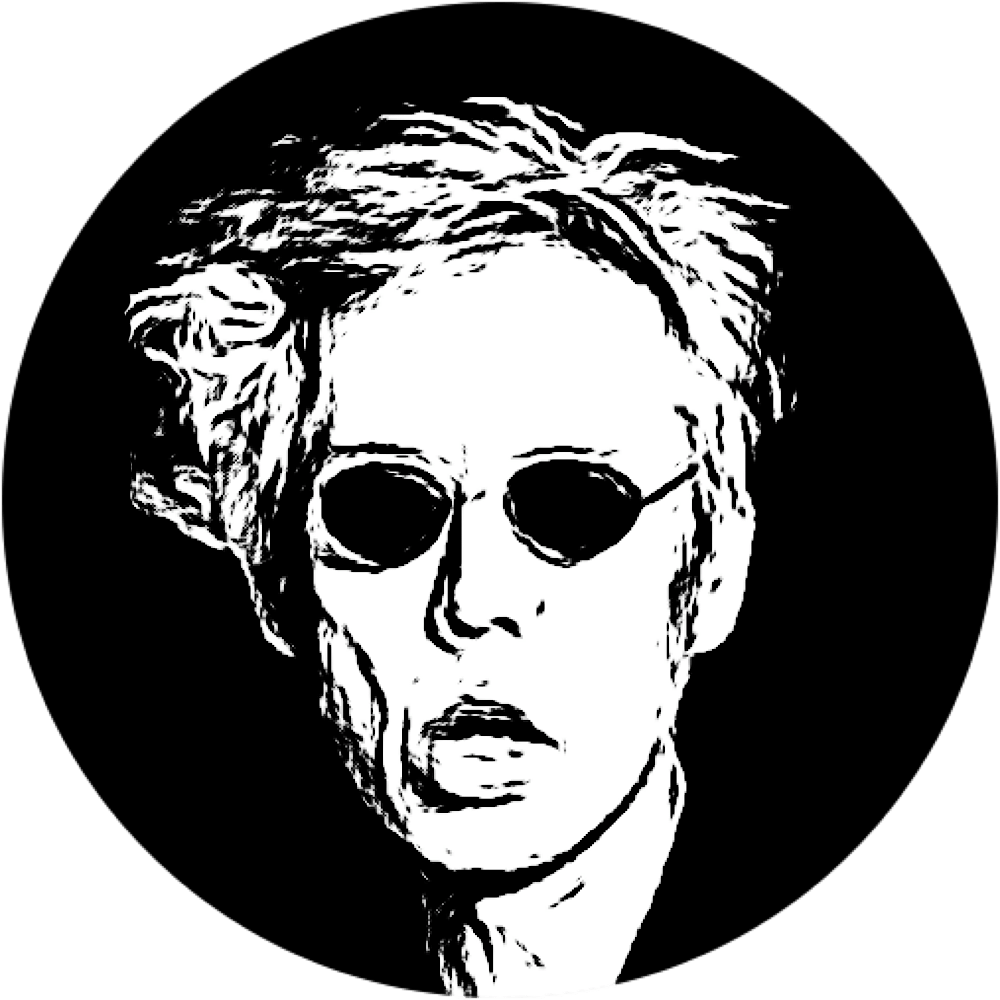2023年8月31日
Mon cher ami,
君が言うように、「作品」とはゼロから出発してすべてをつくることであれば、「狂気=作品の不在」とはゼロから出発して「全て」をつくれないということになる。ところで、フーコーが「狂気=作品の不在」と考えたとき、念頭にあったのは間違いなくアルトーだった。だからといって、フーコーが「作品」をそのまま擁護したとは思えないし、僕にとってはフーコーのあの論文の結論がどうもわからないというか、大きな謎のまま残されたのだが(後のデリダとの論争を読んでもいまいちよくわからなかった)、アルトーの作品と生涯の出来事を勘案すれば、たしかに「作品の不在」と「作品」、二つの事態が起きていたのは事実だ。実際、「狂っている」とき、たとえ「言葉」を失っていなかったにしろ、アルトーは何も書くことができなかった。その後、アルトーは書くことができた。事実、言葉を取り戻すようにしてなのか? しかもそれは「手紙」だけではなかった(ロデーズの精神病院で書かれた手紙は、語られた内容あるいは内容の変遷は別としても、文章としてはすでに明晰なものだった。臨床的に言って、他の分裂症患者の手記などと比べれば、これはほぼあり得ないことだと思われる)。「ロデーズ手帖」、「イヴリー手帖」といった殴り書きのノートやデッサンだけではなかった。精神病院監禁から解放された後、晩年のアルトーは自分の「本」の構成まで考えていたし(それはオペラ的構想、ノイズ・オペラだ!)、晩年の作品のなかには傑作と呼ぶことのできるものがある。ブルトンは超明晰であるなどと賛辞を送っていたが、作品として傑作だと思えるものがたしかにある。僕はアルトーの翻訳者のひとりであるから、手前味噌になるので、それが何という作品であったかは言わないでおく。
ともあれ、それは「作品」の「はじまり」ではなく、「作品」の「完成」、「終わり」じゃないか。フーコーが、アルトーは我々の言語の土壌に属していると言ったのは、そう言う意味ではないのか。では、それならアルトーは精神医学的に治癒したのか。世間で言われる言葉を使えば、アルトーは病気から癒えたのか。彼はついに狂気を免れたのか。僕自身どうか考えていいのかわからなかったし、便宜上、そのように言ったこともあった。しかし本当にそうなのか。実際には何が起きていたのか。アルトーのように狂気から非狂気へ移行する(移行?)なんてことができるのか。そう言うことができるのか。すぐにニーチェやヘルダーリンの生涯と晩年の「作品の不在」が思い浮かぶ。彼らの場合、文字どおりの「無為」しかなかったことはよく知られている。アルトー自身が自分と同じケースとして引き合いにするのはヴァン・ゴッホだけだが、ニーチェもネルヴァルもエドガー・ポーもロートレアモンも、最後には、アルトー言うところの「社会」、「社会の呪い」にやられてしまったと名前を挙げて力説している。つまり「作品」は破壊され、不在となった。ニーチェたちにあっては、アルトー自身のように狂気から非狂気、作品の不在から作品への移行は生起しなかった。
したがって、君が言うようにそこに「大差」はないのかもしれないが、それでも、実際どう考えても「作品の不在」と「作品」は同時的ではないように僕には思われる。それとも「私は狂人ではない」からそのような観点をもたざるを得ず、そう言うことができると私は信じているだけなのか。あるいは、ほんとうは、「言葉」を使うのであれば、日常的にだけではなく、作家であると、物を書く人間であると意識してそれを用いていると信じ込み、それを私は書いているのだと能天気に思っているのであれば、しかもさらに何かが「見えている」、「私は見ている」と「我思う」がゆえに信じているのであれば、そこにあるのは「狂気」だけなのかもしれない……。ふと、そのように思うことがある。明晰であること? 狂人の明晰さ? 君はマラルメもヘルダーリンもカフカもブランショにとっては同じような扱いになっていると言ったが、カフカの小説には「はじまり」しかないように思えるときがある。多くの読者がカフカの「日記」が面白いと感じるのは、日記は一日が終われば、何もかもが終わるからだ。つまり「一日」は「狂気」ではないということになる。
ともあれ、それは「作品」の「はじまり」ではなく、「作品」の「完成」、「終わり」じゃないか。フーコーが、アルトーは我々の言語の土壌に属していると言ったのは、そう言う意味ではないのか。では、それならアルトーは精神医学的に治癒したのか。世間で言われる言葉を使えば、アルトーは病気から癒えたのか。彼はついに狂気を免れたのか。僕自身どうか考えていいのかわからなかったし、便宜上、そのように言ったこともあった。しかし本当にそうなのか。実際には何が起きていたのか。アルトーのように狂気から非狂気へ移行する(移行?)なんてことができるのか。そう言うことができるのか。すぐにニーチェやヘルダーリンの生涯と晩年の「作品の不在」が思い浮かぶ。彼らの場合、文字どおりの「無為」しかなかったことはよく知られている。アルトー自身が自分と同じケースとして引き合いにするのはヴァン・ゴッホだけだが、ニーチェもネルヴァルもエドガー・ポーもロートレアモンも、最後には、アルトー言うところの「社会」、「社会の呪い」にやられてしまったと名前を挙げて力説している。つまり「作品」は破壊され、不在となった。ニーチェたちにあっては、アルトー自身のように狂気から非狂気、作品の不在から作品への移行は生起しなかった。
したがって、君が言うようにそこに「大差」はないのかもしれないが、それでも、実際どう考えても「作品の不在」と「作品」は同時的ではないように僕には思われる。それとも「私は狂人ではない」からそのような観点をもたざるを得ず、そう言うことができると私は信じているだけなのか。あるいは、ほんとうは、「言葉」を使うのであれば、日常的にだけではなく、作家であると、物を書く人間であると意識してそれを用いていると信じ込み、それを私は書いているのだと能天気に思っているのであれば、しかもさらに何かが「見えている」、「私は見ている」と「我思う」がゆえに信じているのであれば、そこにあるのは「狂気」だけなのかもしれない……。ふと、そのように思うことがある。明晰であること? 狂人の明晰さ? 君はマラルメもヘルダーリンもカフカもブランショにとっては同じような扱いになっていると言ったが、カフカの小説には「はじまり」しかないように思えるときがある。多くの読者がカフカの「日記」が面白いと感じるのは、日記は一日が終われば、何もかもが終わるからだ。つまり「一日」は「狂気」ではないということになる。