2023年12月+28日
Mon camarade Yoshi,
リスナーは怖い存在だけど、正直に言えば、敵に見えることがある。リスナーを憎んでいるわけではないよ。それならリスナー、観客とは、そもそも仮想敵なのか? だがそれは僕にとってひとつの仮説ではない。寺山修司の天井桟敷を意識していたわけでは全くないが、ライブではとにかくリスナーとのある種の緊張関係がなければ、音楽的にいいライブとは思えなかった。今でもその考えは変わらない。リスナーの側で考えても、クラシック音楽のコンサートでも同じようなことが言えると思う。たとえばクラシックのピアニストは原則として弾き間違えたりできないのだから、なおさらその負荷は大きい。観客は固唾を飲んでそれを凝視している。これは一種の敵対関係だ。
以前、山本精一と二人でライブをやったとき、少しだけ話し合って互いに了解したことがあった。「今日は、嫌がらせの音楽をやろう!」。彼は爆音ノイズ・ギター、僕は主にオルガンを弾いた。僕の方は、曲調としてすべてがノイズ・キーボードだったわけではないが(シンセは使わなかった)、ちょうど京都のお盆の最終日だったから、地獄の蓋が開いたようだった。お客のなかにもそのように言う人がいた。それは「誉めている」のではなく、軽い当惑だった。地獄にもいろいろある。この合図があらかじめあったから、お互いの演奏はかなりうまくいったように自分たちでは思った。その日はやっていて、久しぶりにかなり面白かったんだ。
君が言うように、たとえこんな感じであっても、なるほどそこには「言語」が全反射のように行き交っていたし、観客の反応も、当惑を含めて、それとは無関係ではあり得なかったのだろう。「敵対」はもちろんそれ自体言語的なものであるが、しかしこのような敵対としての演奏を「自然」(?)に、無意思的にやれるなら、ミュージシャン側の「言語」は「音」との関係においてさらに曖昧に、抽象的なものになっていくような感じがする。音楽の言語からじょじょに解放されている……? いま思えば、昔、EP-4のライブのときの僕の印象では、そのままで政治的言語ということではないが、この敵対関係はもっと政治的ニュアンスがぴりぴりと感じられた。まあ、ポスト・パンクの時代だったしね。だがこの日の山本精一氏とのライブはそれとも全く違った。このライブでは「敵対関係」の内と外があって、挑発とは違う関係が成立するかのようだった。うまく言えないが、喧嘩腰ではなく、山本と僕はその「内部」的状態を楽しんでいたと言えばいいのか……。
音楽において、僕にはたしかに「言語的」構想がある。それは認めるよ。僕が一方では作家もどきをやっているのだし、そのような人間であることしか元々できないのだから、それぞれの音楽的動機の基盤にはなおさら「言語」があることは承知しているし、それどころか、全然そういう問題でないこともわかっている。だけど演奏は? 演奏しているときはどうなのか? 君の唯物論的観点からすれば、それこそが言語的だと解することを理解しているつもりだが、自分では実感としてよくわからないんだ。「穴」に入っているみたいな感じがするときがある。「穴」は「間隙」だけではなく「陥穽」でもある。レーモン・ルーセルの『ロクス・ソルス』仕様のようには「作品」として成り立たないところがあって、身動きできないことがある。「作品」化について、「作品」を目前にして、僕は何かの言い訳をしているのだろうか。何かをかわして(esquiver)いるのだろうか。それは巧みに逃れることなのか。後は、「さようなら」と言えばいいのか。
君は前回の手紙で「音から派生する必然」と言った。それは「偶然性唯物論」によるものかもしれないと思ったりもする。チャンス・オペレーションのことではない。八卦でもない。偶然性唯物論ならやれるかもしれない。それならまだやる気が出るかもしれない。循環的であることによる突発的な派生。ミニマル・ミュージックのことを言っているのではない。「同じ音」! 同じ音がないことによる「同じ音」を目指して、それを聴くためだ。はたして人は「同じ音」を聞いたことがあったのだろうか……。
以前、山本精一と二人でライブをやったとき、少しだけ話し合って互いに了解したことがあった。「今日は、嫌がらせの音楽をやろう!」。彼は爆音ノイズ・ギター、僕は主にオルガンを弾いた。僕の方は、曲調としてすべてがノイズ・キーボードだったわけではないが(シンセは使わなかった)、ちょうど京都のお盆の最終日だったから、地獄の蓋が開いたようだった。お客のなかにもそのように言う人がいた。それは「誉めている」のではなく、軽い当惑だった。地獄にもいろいろある。この合図があらかじめあったから、お互いの演奏はかなりうまくいったように自分たちでは思った。その日はやっていて、久しぶりにかなり面白かったんだ。
君が言うように、たとえこんな感じであっても、なるほどそこには「言語」が全反射のように行き交っていたし、観客の反応も、当惑を含めて、それとは無関係ではあり得なかったのだろう。「敵対」はもちろんそれ自体言語的なものであるが、しかしこのような敵対としての演奏を「自然」(?)に、無意思的にやれるなら、ミュージシャン側の「言語」は「音」との関係においてさらに曖昧に、抽象的なものになっていくような感じがする。音楽の言語からじょじょに解放されている……? いま思えば、昔、EP-4のライブのときの僕の印象では、そのままで政治的言語ということではないが、この敵対関係はもっと政治的ニュアンスがぴりぴりと感じられた。まあ、ポスト・パンクの時代だったしね。だがこの日の山本精一氏とのライブはそれとも全く違った。このライブでは「敵対関係」の内と外があって、挑発とは違う関係が成立するかのようだった。うまく言えないが、喧嘩腰ではなく、山本と僕はその「内部」的状態を楽しんでいたと言えばいいのか……。
音楽において、僕にはたしかに「言語的」構想がある。それは認めるよ。僕が一方では作家もどきをやっているのだし、そのような人間であることしか元々できないのだから、それぞれの音楽的動機の基盤にはなおさら「言語」があることは承知しているし、それどころか、全然そういう問題でないこともわかっている。だけど演奏は? 演奏しているときはどうなのか? 君の唯物論的観点からすれば、それこそが言語的だと解することを理解しているつもりだが、自分では実感としてよくわからないんだ。「穴」に入っているみたいな感じがするときがある。「穴」は「間隙」だけではなく「陥穽」でもある。レーモン・ルーセルの『ロクス・ソルス』仕様のようには「作品」として成り立たないところがあって、身動きできないことがある。「作品」化について、「作品」を目前にして、僕は何かの言い訳をしているのだろうか。何かをかわして(esquiver)いるのだろうか。それは巧みに逃れることなのか。後は、「さようなら」と言えばいいのか。
君は前回の手紙で「音から派生する必然」と言った。それは「偶然性唯物論」によるものかもしれないと思ったりもする。チャンス・オペレーションのことではない。八卦でもない。偶然性唯物論ならやれるかもしれない。それならまだやる気が出るかもしれない。循環的であることによる突発的な派生。ミニマル・ミュージックのことを言っているのではない。「同じ音」! 同じ音がないことによる「同じ音」を目指して、それを聴くためだ。はたして人は「同じ音」を聞いたことがあったのだろうか……。
鈴木創士
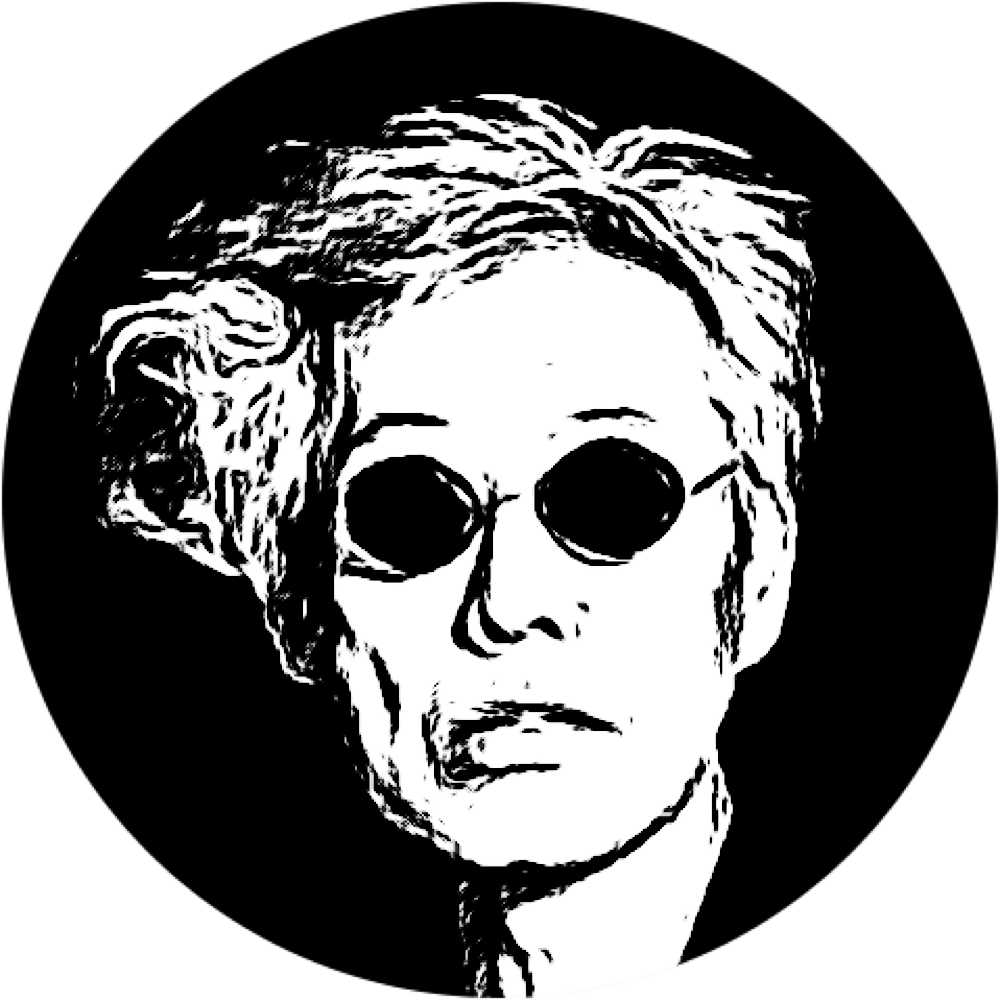
鈴木 創士(すずき そうし)
作家、フランス文学者、評論家、翻訳家、ミュージシャン──著書『アントナン・アルトーの帰還』(河出書房新社)、『中島らも烈伝』(河出書房新社)、『離人小説集』(幻戱書房)、『うつせみ』(作品社)、『文楽徘徊』(現代思潮新社)、『連合赤軍』(編・月曜社)、『芸術破綻論』(月曜社)他、翻訳監修など
【Monologue】今年はやけに寒い。2023年生まれだからなのか。






