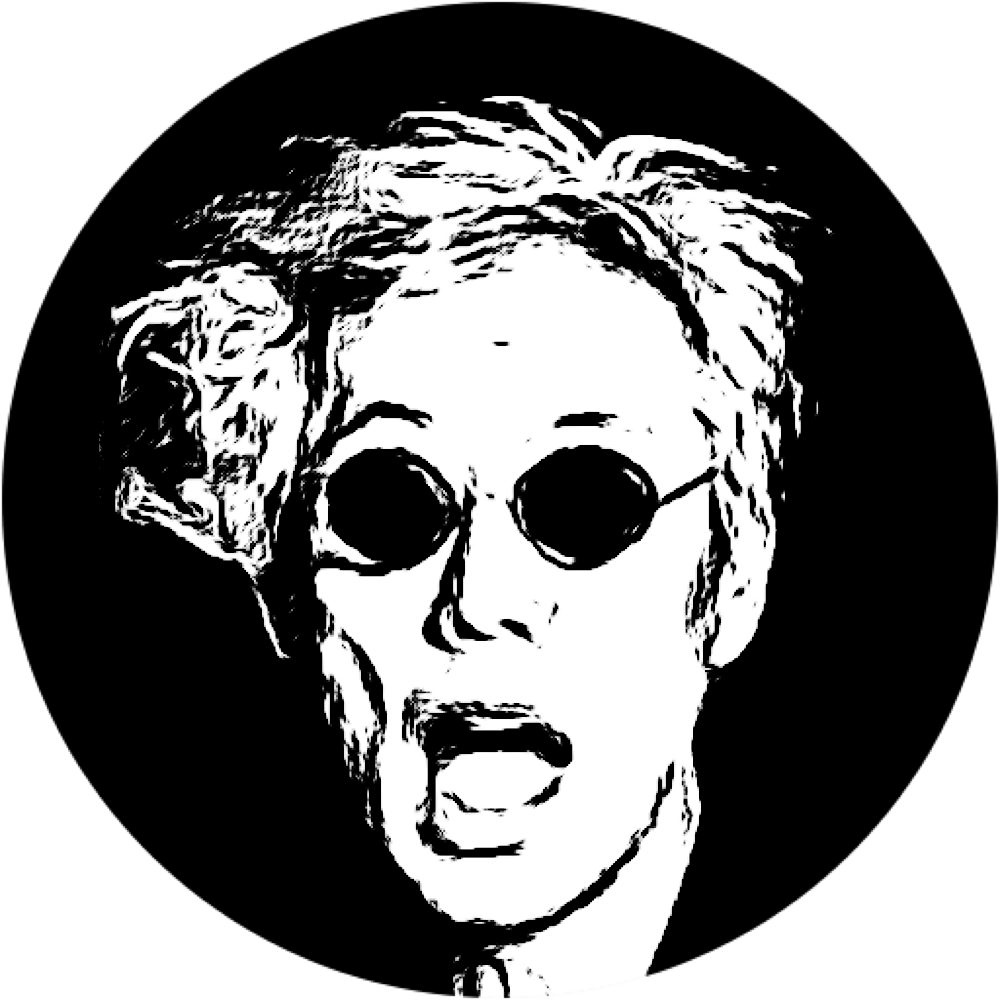2023年5月21日
親愛なる市田
前回の君の手紙に答えるべきことが色々あるようだ。
無関係のあり方も千差万別。僕は勝手にその一つをアラン・バディウ風に「非-関係」と呼んでいる。サルトルの話はすごく腑に落ちるし、怒るどころか、光栄だよ。サルトルの哲学や文学に影響は受けなかったが、彼が毛沢東派とつるんでいた『人民の大義』の頃も嫌な感じはしなかった。彼のピアノ! とても興味深い。延々と続いてとぐろを巻く文章、覚醒剤的効果にも思えるあのサナダ虫のようなセンテンスとの違いか。なるほどね。それならサルトルの文章のなかにも言うところの「非-関係」を探してみるべきかもしれない。何か発見があるかもしれない。
サルトルの歩く姿が目に浮かぶ。ラスパイユ通りだった。たぶん彼の住まいの近くだったと思う。薄茶色のジャンパーを着て、背の低い、藪睨みの老人とすれ違った。近くにはたしかロダン作のバルザック像があった。眼鏡をかけたちっちゃなサルトルと腹を突き出した堂々たるバルザック。しかも「人間喜劇」だ! 対照的人間喜劇。コントラストをなしている。できすぎだとは思ったよ。僕は若かったし、映画を見ているみたいだった。舞台装置はそろっていたが、「人間喜劇」にしては、サルトルは憮然として歩いていた。サルトルは、何ていうか、共同体から離脱した、それでいて市井の人のようだった。
ごめん。誤解させたね。君が見たとおり、5・21に女性ヴォーカルはなしでした。いくら何でもまだ一緒に演奏は無理だと思っていたので、まだ先の話だと思っていた矢先、この話はお流れになった。向こうの事情によるのだけれど、僕のほうから若い彼女に無理強いは絶対にしたくなかった。先走りすぎたけど、彼女を見ていて、やらない可能性があることを考慮に入れてはいたけどね……。残念だけど、仕方がない。バンドには色々ある。しかしヴォーカルがいようがいまいが、「歌」なるものをどうするのか? 「歌」なのね、結局は。君が言う意味で。EP-4 unitPに若い女性のヴォーカル(我々はじじいバンドなので)というか、ヴォイスが欲しいとは前々から思っていた。ヴィジュアル的にというわけではなかったが(きっと人はそう思うだろう)、ぼんやりとした音楽的構想はあったんだ。それにしても大変な課題を僕は背負ってしまった。僕自身の演奏の質も変わらざるを得ないだろう。すでにその感覚があるにはある。実際、先日の5・21の「演奏」にはそうとは聞こえない「歌」が少し入っていたと思うんだけど、どうかな。エイミー・ワインハウスか。たしかに彼女はニーナ・シモンより弱々しいし、痛々しい。歌手としての人格もずれているし、言葉が浮いて歌詞からずれ始めるかのようだ。そこが彼女の本質であるのだろうし、魅力なのだろう。早死にする感じがすでにあったなあ。でもunitPに必要な女性ヴォーカルはエイミーではないかもしれないが、『鑑識レコード倶楽部』のあの謎のウェイトレスがエイミーだとする君の意見はわかる気がする。我々の歌姫はみんな病んでいる。森田潤との第二弾をつくっているが、それには女性の声が入る予定だよ。こちらはもう録音済み。
君の見立てというか直観は鋭いね。白状すれば、君の言うとおりだよ。かつてEP-4とThe Pop Groupは音楽的に似たところはないのに、当時、少なくとも僕にとって切り離せない関係だった。僕はひそかにThe Pop Groupを意識していた(ステージで覆面するのはマーク・スチュアートより我々のほうが早かったはずだけど)。この意識化はどこからやって来ていたのか。僕にとってお手本となったのは、ヴェーベルン、ヴァレーズ、シュトックハウゼンだった。決してブーレーズやフランス人たちではない。ベルクでもなければ、ケージでもない。アメリカ人なら、ヴェルベッツだったけれど、EP-4はロック・ミュージックではない(そういえば、unitPは印象としてEP-4本隊よりロック的かもしれないな、それからついでに君の質問に答えるなら、PはpseudoのP、つまり「偽」のユニット、もしくはチンピラのPだ)。そしてこの意識化の裏には佐藤薫によるブラック・ミュージックがきっちり潜在的リズムとして控えていなければならなかった。だけどミュージシャンとして彼の考えや思惑を演奏に生かすことは、正直言って、とても難しかった。それに君の言う「昭和崩御」や“We are all prostitutes”という言葉をEP-4の「言葉」として「抽象的」な手段としてさえ佐藤薫に歌わせてはならないと僕は思っていたのだから。EP-4に「歌詞」があったとしても、それは「音」と入れ子状になっている。それが君の言う佐藤のうまいやり方だったし、「発明」だったからだ。
無関係のあり方も千差万別。僕は勝手にその一つをアラン・バディウ風に「非-関係」と呼んでいる。サルトルの話はすごく腑に落ちるし、怒るどころか、光栄だよ。サルトルの哲学や文学に影響は受けなかったが、彼が毛沢東派とつるんでいた『人民の大義』の頃も嫌な感じはしなかった。彼のピアノ! とても興味深い。延々と続いてとぐろを巻く文章、覚醒剤的効果にも思えるあのサナダ虫のようなセンテンスとの違いか。なるほどね。それならサルトルの文章のなかにも言うところの「非-関係」を探してみるべきかもしれない。何か発見があるかもしれない。
サルトルの歩く姿が目に浮かぶ。ラスパイユ通りだった。たぶん彼の住まいの近くだったと思う。薄茶色のジャンパーを着て、背の低い、藪睨みの老人とすれ違った。近くにはたしかロダン作のバルザック像があった。眼鏡をかけたちっちゃなサルトルと腹を突き出した堂々たるバルザック。しかも「人間喜劇」だ! 対照的人間喜劇。コントラストをなしている。できすぎだとは思ったよ。僕は若かったし、映画を見ているみたいだった。舞台装置はそろっていたが、「人間喜劇」にしては、サルトルは憮然として歩いていた。サルトルは、何ていうか、共同体から離脱した、それでいて市井の人のようだった。
ごめん。誤解させたね。君が見たとおり、5・21に女性ヴォーカルはなしでした。いくら何でもまだ一緒に演奏は無理だと思っていたので、まだ先の話だと思っていた矢先、この話はお流れになった。向こうの事情によるのだけれど、僕のほうから若い彼女に無理強いは絶対にしたくなかった。先走りすぎたけど、彼女を見ていて、やらない可能性があることを考慮に入れてはいたけどね……。残念だけど、仕方がない。バンドには色々ある。しかしヴォーカルがいようがいまいが、「歌」なるものをどうするのか? 「歌」なのね、結局は。君が言う意味で。EP-4 unitPに若い女性のヴォーカル(我々はじじいバンドなので)というか、ヴォイスが欲しいとは前々から思っていた。ヴィジュアル的にというわけではなかったが(きっと人はそう思うだろう)、ぼんやりとした音楽的構想はあったんだ。それにしても大変な課題を僕は背負ってしまった。僕自身の演奏の質も変わらざるを得ないだろう。すでにその感覚があるにはある。実際、先日の5・21の「演奏」にはそうとは聞こえない「歌」が少し入っていたと思うんだけど、どうかな。エイミー・ワインハウスか。たしかに彼女はニーナ・シモンより弱々しいし、痛々しい。歌手としての人格もずれているし、言葉が浮いて歌詞からずれ始めるかのようだ。そこが彼女の本質であるのだろうし、魅力なのだろう。早死にする感じがすでにあったなあ。でもunitPに必要な女性ヴォーカルはエイミーではないかもしれないが、『鑑識レコード倶楽部』のあの謎のウェイトレスがエイミーだとする君の意見はわかる気がする。我々の歌姫はみんな病んでいる。森田潤との第二弾をつくっているが、それには女性の声が入る予定だよ。こちらはもう録音済み。
君の見立てというか直観は鋭いね。白状すれば、君の言うとおりだよ。かつてEP-4とThe Pop Groupは音楽的に似たところはないのに、当時、少なくとも僕にとって切り離せない関係だった。僕はひそかにThe Pop Groupを意識していた(ステージで覆面するのはマーク・スチュアートより我々のほうが早かったはずだけど)。この意識化はどこからやって来ていたのか。僕にとってお手本となったのは、ヴェーベルン、ヴァレーズ、シュトックハウゼンだった。決してブーレーズやフランス人たちではない。ベルクでもなければ、ケージでもない。アメリカ人なら、ヴェルベッツだったけれど、EP-4はロック・ミュージックではない(そういえば、unitPは印象としてEP-4本隊よりロック的かもしれないな、それからついでに君の質問に答えるなら、PはpseudoのP、つまり「偽」のユニット、もしくはチンピラのPだ)。そしてこの意識化の裏には佐藤薫によるブラック・ミュージックがきっちり潜在的リズムとして控えていなければならなかった。だけどミュージシャンとして彼の考えや思惑を演奏に生かすことは、正直言って、とても難しかった。それに君の言う「昭和崩御」や“We are all prostitutes”という言葉をEP-4の「言葉」として「抽象的」な手段としてさえ佐藤薫に歌わせてはならないと僕は思っていたのだから。EP-4に「歌詞」があったとしても、それは「音」と入れ子状になっている。それが君の言う佐藤のうまいやり方だったし、「発明」だったからだ。