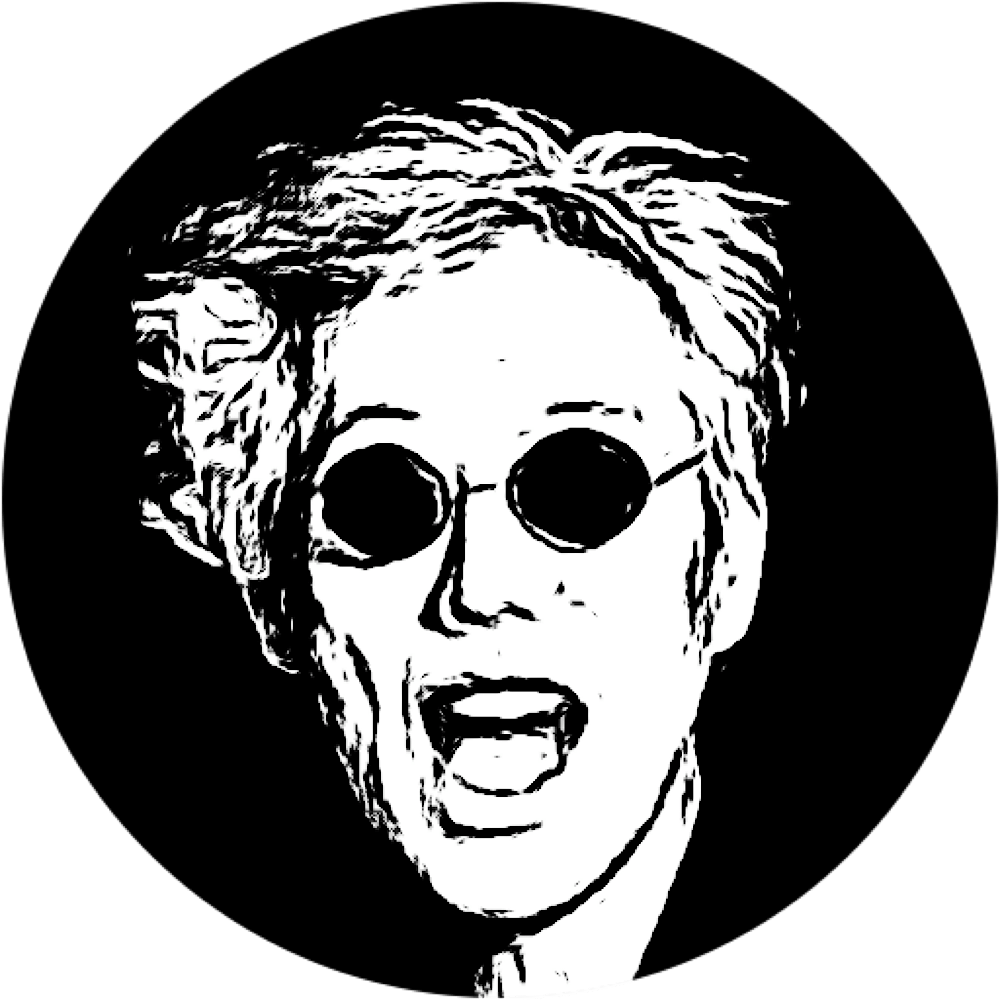2024年7月29日
市田大兄
記憶というものは不確かである。そこに自分がいたかどうかも定かではない。私は思い出す。丘の上に月が昇っていた。私は月を見たのか、そして同時に見なかったのか。丘なんかなかったのだ。エニシダの小道だけが続いて、大気には嫌な臭いが漂っていた。おお、忘却のなかでこそ大気は動かない、と詩人は言っていたではないか。歩くたびに、向こうへ世界の果てが遠のいた。私は思い出す、そして思い出せない。
前葉で君の言う「体験」と「経験」の違い。混濁した「体験」、逃れ去ることを特徴としているばかりか、主体の位置そのものが消えてしまう。その表面に浮かび上がるもの、むしろ忘却の形をとることもある「無知」。君の言うとおりだ。それなら「無知」から始めるしかない。無知を知るしかない。無知を解釈するしかない。君の言う「経験」が現れる。記憶の古層を探したわけではないのに、探しているものはすでに見つかっている。パスカルの言うとおりだ。君の書いていたルーセルの「栄光」は、パスカルの「喜び」、ヌイイの橋の上での、「喜び、喜び、喜び」に似たところがあるように思える。それがいつ起ったか、時間的な順序が逆なだけかもしれない。ピカソの言い方はちょっと違う。「私は探さない。私は見つけるのだ」。ピカソらしいマッチョな言葉とも受け取れるが、とにかく探しても始まらないということだろう。僕も探さない。聞こえない音を必ずしも探しているのではない。だが聞こえない音がそのまま「在る」ようにできるなら……
それでも意に反して僕も探してみることがある。ランプを掲げて、無いものを。それは、存在したかもしれないが、存在しなかったものだろうか。存在したかもしれないものとは何だろう。それは存在することができたものであるに違いないが、知らぬまに過去が現在にすり替わる。ほとんど存在しかけていたもの。ほとんど無。可能性でも潜在性でもない存在の鏡の箔裡、裏面のようなもの。別の裏面? 別の表面? 深さの破れ? 表層を突き破る別の底? それが雪崩のように、あるいは一瞬の映像の現前のようにこだまするが、結局それは「存在」していたとも言える。ああ、そうだとも、まさに無知のまっただなかに。「経験」としてなのか? この「経験」において、空間が残るのであれば、時間も残存する。時間が残ったのであれば、空間も残存したのだ。
記憶をめぐるエピソードをひとつ。それは「経験」となったのか。君の意見を踏まえると、やはり「体験」と「経験」の間で人は揺れ動いている。そこを漂っている。最近、岐阜のポスト・パンク女子高生バンド『伸展のずる』のCDが40年ぶりにリリースされた(WINE AND DINE 26)。そのCDのために「オフェリアみゃっぴー」というエッセイを書いた。彼女たちは跡形もなく消えたと思われていたが、経過しなかった40年は「経験」として何かをもたらしたのだろうか。たぶん。走る、キャッ、キャッ、キャッーを。走る、ギョッ、ギョッ、ギョッ。エリマキトカゲ。エリマキトカゲとは、走るキャッ、キャッ、キャッーだ。走っている奴は過去も現在も未来ももたない。エリマキトカゲは探されないままに、すでに見つかっていた。朝起きて、グニョー。それからガチャガチャしたもの。見逃したと思っていたが、誰もが見つけていたものだった。そのために音楽が必要だった。いまも必要である。生意気な女子高生であることはほとんど必要最低限のことだった。
エッセイの最後の節を再録する。
言葉はいつか発せられたのだ。かつてであるとは言えない、これからとも言えない。いまとも言えない。泣きたくなった女の子がいた。そんな感じだった。こんなことはほとんど無意味だろうか。
前葉で君の言う「体験」と「経験」の違い。混濁した「体験」、逃れ去ることを特徴としているばかりか、主体の位置そのものが消えてしまう。その表面に浮かび上がるもの、むしろ忘却の形をとることもある「無知」。君の言うとおりだ。それなら「無知」から始めるしかない。無知を知るしかない。無知を解釈するしかない。君の言う「経験」が現れる。記憶の古層を探したわけではないのに、探しているものはすでに見つかっている。パスカルの言うとおりだ。君の書いていたルーセルの「栄光」は、パスカルの「喜び」、ヌイイの橋の上での、「喜び、喜び、喜び」に似たところがあるように思える。それがいつ起ったか、時間的な順序が逆なだけかもしれない。ピカソの言い方はちょっと違う。「私は探さない。私は見つけるのだ」。ピカソらしいマッチョな言葉とも受け取れるが、とにかく探しても始まらないということだろう。僕も探さない。聞こえない音を必ずしも探しているのではない。だが聞こえない音がそのまま「在る」ようにできるなら……
それでも意に反して僕も探してみることがある。ランプを掲げて、無いものを。それは、存在したかもしれないが、存在しなかったものだろうか。存在したかもしれないものとは何だろう。それは存在することができたものであるに違いないが、知らぬまに過去が現在にすり替わる。ほとんど存在しかけていたもの。ほとんど無。可能性でも潜在性でもない存在の鏡の箔裡、裏面のようなもの。別の裏面? 別の表面? 深さの破れ? 表層を突き破る別の底? それが雪崩のように、あるいは一瞬の映像の現前のようにこだまするが、結局それは「存在」していたとも言える。ああ、そうだとも、まさに無知のまっただなかに。「経験」としてなのか? この「経験」において、空間が残るのであれば、時間も残存する。時間が残ったのであれば、空間も残存したのだ。
記憶をめぐるエピソードをひとつ。それは「経験」となったのか。君の意見を踏まえると、やはり「体験」と「経験」の間で人は揺れ動いている。そこを漂っている。最近、岐阜のポスト・パンク女子高生バンド『伸展のずる』のCDが40年ぶりにリリースされた(WINE AND DINE 26)。そのCDのために「オフェリアみゃっぴー」というエッセイを書いた。彼女たちは跡形もなく消えたと思われていたが、経過しなかった40年は「経験」として何かをもたらしたのだろうか。たぶん。走る、キャッ、キャッ、キャッーを。走る、ギョッ、ギョッ、ギョッ。エリマキトカゲ。エリマキトカゲとは、走るキャッ、キャッ、キャッーだ。走っている奴は過去も現在も未来ももたない。エリマキトカゲは探されないままに、すでに見つかっていた。朝起きて、グニョー。それからガチャガチャしたもの。見逃したと思っていたが、誰もが見つけていたものだった。そのために音楽が必要だった。いまも必要である。生意気な女子高生であることはほとんど必要最低限のことだった。
エッセイの最後の節を再録する。
洗練ではなく、むしろ野蛮が。野蛮ではなく、むしろ放逸が。放逸ではなく、むしろ苛立ちが。だが季節はめぐらない。循環するものはない。とってつけた反復もない。最低限の言葉は素朴に下降線をたどっていたが、空虚は何とかもちこたえられる。いい感じじゃないか!
(……)その後、彼女は忽然と消えた。消息はわからない。若いオフェリアは下流の向こうに見えなくなった。水辺に青い夏草が咲いているのが見えた。
言葉はいつか発せられたのだ。かつてであるとは言えない、これからとも言えない。いまとも言えない。泣きたくなった女の子がいた。そんな感じだった。こんなことはほとんど無意味だろうか。