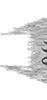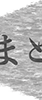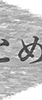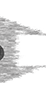2023年3月28日
創士兄、
「ボードレールの世界」はあるが「マラルメの世界」はない、か。その通りだと思う。しかし自分の理解がちょっと常識的文化史にもたれすぎているかも、と危惧するから、擦り合わせのためにその理解を疑問の形で書いてみる。これは前回のこちらからの手紙の続きでもある。簡単に言えば、それは「ワーグナーの世界」はあるが「シェーンベルクの世界」はないと言い換えても同じなのか、違うのか。「ワーグナー」と「シェーンベルク」はそれぞれ別の名前でもいいのだが、対としてはとりあえず標題音楽(または実用音楽)と絶対音楽という程度の差異(この二つに厳密な定義があるのかどうか知らないが)と思ってもらっていい。常識的文化史と重なる所以である。しかし僕にとってこの差異は、百年ほど前にあるオーストリア人が書き残した次の寓話的な場面に送り返される(少しだけ脚色して引く)。
こんな場面を想像してみてほしい。音楽というものに触れたことがなく、音楽なるものがこの世にあるとも知らない人が我が家にやってくる。居間では私の兄が瞑想的なショパンの曲を弾いている。客人はどう思うだろうか。こう思うのではないか。これは言語だろう。ただその意味を私に隠しておきたいのだろう。兄弟だけの話をしているのだろう。
この客人はショパンを聞いて、「瞑想」の世界はおろかおよそいかなる「世界」も思念できず、それを、分からない何かを言っている言語として受け取る。二種類の音楽の違い(標題/絶対)が問題なのではない。客人は音楽なるものをまったく知らず、音列を音楽として受け取ることができないのだから。音楽として聴ける音列は多少なりとも「世界」を聴き手の頭の中に作り出すだろう。フランス語を読めなくとも多少の教養があれば、ボードーレールの詩は「世界」──「悪の華」!「パリの憂愁」!──を読者の頭に作りやすい。ワーグナーのオペラなど、歌詞の内容をほとんど理解できずとも粗筋だけ知っていれば、その舞台はこれ見よがしに「世界」──「これこそドイツ人の歴史である!」──を差し出すだろう。
それに対しマラルメの詩は、言語であることは分かるものの、何について何を語っているのかよく分からない。客人の言う「意味」があるのかないのか分からず、言語だから意味は「ある」のだろうが、ではその意味は?と問えば詩をほぼそのまま繰り返す──説明せずに記述する──ことぐらいしかできないし、「賽の一擲」に至ってはその記述さえおぼつかない。まさに、それを日本語にして何の「意味」があるのか。彼の詩の「世界」はあくまで自己充足的で、そのとき「世界」という語は「作品」の同義語でしかない。絶対音楽なる理念を体現していると言われたりするブラームス以降の音楽も、その「世界」がどのようであるかを言おうとすれば、曲を最後まで聞いて「このようである」とただ指差すか、曲を成り立たせる規則や技法を記述するしかない。これも「このようである」と言うことのバリエーションだろう。そこに作品外の「世界」などない。
それでも、そこが上の寓話の面白いところだと僕は思うのだが、客人は「世界」を伴わない音列を言語だとは認識する。これは絶対音楽を「音楽」として聴く──「聞く」ではない──こととどこか似ていないか。とりあえず無調の12音技法を使っていることは分かる類の絶対音楽は、ここでの例としてあまり適当でないかもしれない。音に規則がある──言語に文法があるように──と実感できるのだから。ここでの例としてはむしろ、φononの数々のアルバムを考えてみるべきだろう。僕たちはラジオのぶちぶち音や肺の呼吸音まで「音楽」として聴くことができる。上の寓話を知って、僕は何よりまずそれらのことを思い出した。僕はこの客人としてあれらの音を受け取っていた。
「世界」を欠いた音楽や詩にも「語っている」ことはある。それらは「私は語る」とは語っている。「私は語る」とそれらが「語っている」、と僕はそれらを読む/聴く。その「私」に「おまえ」と呼ばれている気がする。この「私」は作者でも演者でもない。僕がそれを聴いたり読んだりしている間だけ、語られている「私は語る」なるフレーズの発話主体として、その語られていることの中かつ外にいる〈人物〉だ。だからその「私」を三人称で「彼」と呼んでもいい。ブランショがそうしたように(『私についてこなかった男』)。
そんな「私は語る」の持続が、前回の手紙で僕の言った「歌」であるのかもしれない。だとすれば「歌」に「内容」があってはいけないのかもしれない。しかし僕としては言いたい。詩を欠いた器楽曲に逃げるのは極めて安易なやり方だと思う。音楽を詩のメタファーにして「世界」を捏造させてしまうから。「私は語る」は言わば、あらゆる小説の冒頭の一行だ。それを音楽家にも詩人にも持続させてほしいとひたすら願っている。その持続の締めくくりには、エリック・ドルフィーの「言葉」あるのみ。「音楽はいったん終われば空中に去ってしまう。二度とそれを捕まえることはできない」。
それに対しマラルメの詩は、言語であることは分かるものの、何について何を語っているのかよく分からない。客人の言う「意味」があるのかないのか分からず、言語だから意味は「ある」のだろうが、ではその意味は?と問えば詩をほぼそのまま繰り返す──説明せずに記述する──ことぐらいしかできないし、「賽の一擲」に至ってはその記述さえおぼつかない。まさに、それを日本語にして何の「意味」があるのか。彼の詩の「世界」はあくまで自己充足的で、そのとき「世界」という語は「作品」の同義語でしかない。絶対音楽なる理念を体現していると言われたりするブラームス以降の音楽も、その「世界」がどのようであるかを言おうとすれば、曲を最後まで聞いて「このようである」とただ指差すか、曲を成り立たせる規則や技法を記述するしかない。これも「このようである」と言うことのバリエーションだろう。そこに作品外の「世界」などない。
それでも、そこが上の寓話の面白いところだと僕は思うのだが、客人は「世界」を伴わない音列を言語だとは認識する。これは絶対音楽を「音楽」として聴く──「聞く」ではない──こととどこか似ていないか。とりあえず無調の12音技法を使っていることは分かる類の絶対音楽は、ここでの例としてあまり適当でないかもしれない。音に規則がある──言語に文法があるように──と実感できるのだから。ここでの例としてはむしろ、φononの数々のアルバムを考えてみるべきだろう。僕たちはラジオのぶちぶち音や肺の呼吸音まで「音楽」として聴くことができる。上の寓話を知って、僕は何よりまずそれらのことを思い出した。僕はこの客人としてあれらの音を受け取っていた。
「世界」を欠いた音楽や詩にも「語っている」ことはある。それらは「私は語る」とは語っている。「私は語る」とそれらが「語っている」、と僕はそれらを読む/聴く。その「私」に「おまえ」と呼ばれている気がする。この「私」は作者でも演者でもない。僕がそれを聴いたり読んだりしている間だけ、語られている「私は語る」なるフレーズの発話主体として、その語られていることの中かつ外にいる〈人物〉だ。だからその「私」を三人称で「彼」と呼んでもいい。ブランショがそうしたように(『私についてこなかった男』)。
そんな「私は語る」の持続が、前回の手紙で僕の言った「歌」であるのかもしれない。だとすれば「歌」に「内容」があってはいけないのかもしれない。しかし僕としては言いたい。詩を欠いた器楽曲に逃げるのは極めて安易なやり方だと思う。音楽を詩のメタファーにして「世界」を捏造させてしまうから。「私は語る」は言わば、あらゆる小説の冒頭の一行だ。それを音楽家にも詩人にも持続させてほしいとひたすら願っている。その持続の締めくくりには、エリック・ドルフィーの「言葉」あるのみ。「音楽はいったん終われば空中に去ってしまう。二度とそれを捕まえることはできない」。