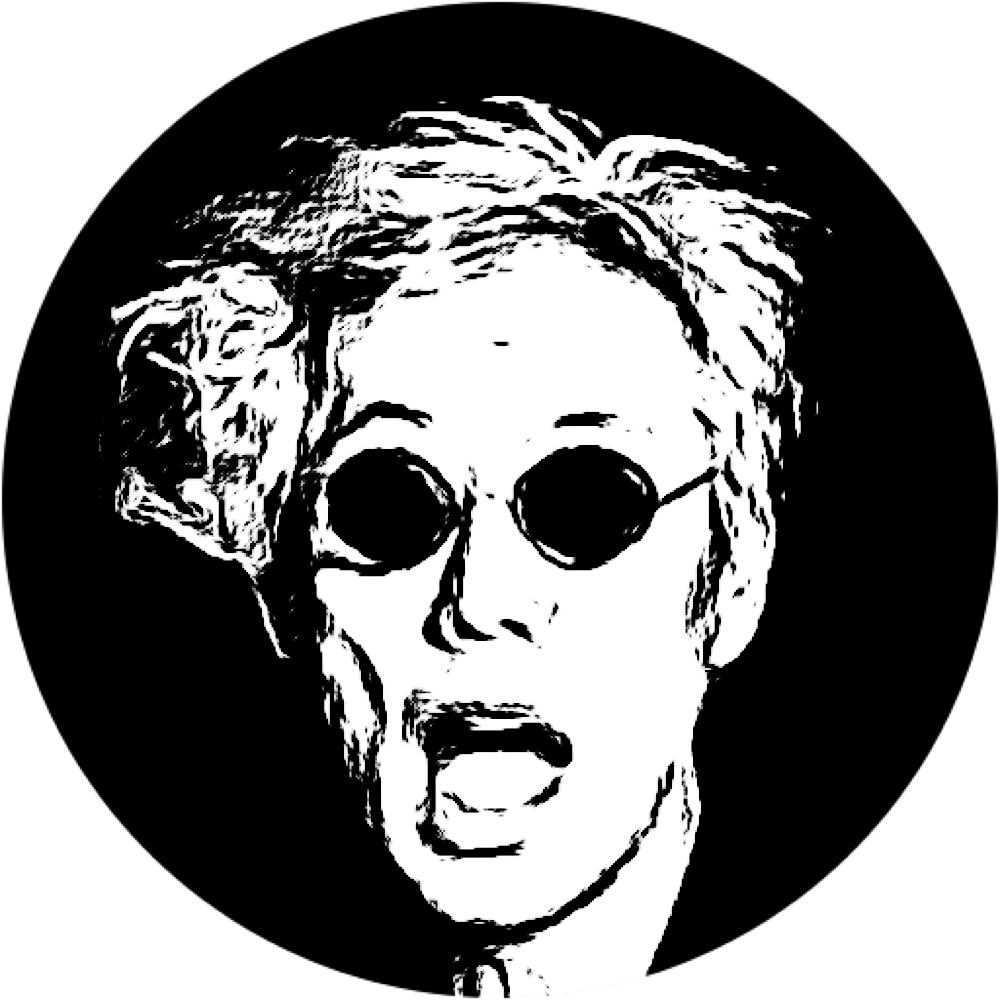2023年3月31日
Mon camarade
僕も音楽と言葉の通常の合体には耐えられない。まあ、他人がうたっている歌を聞くとき、僕はほぼ言葉の意味を無視する、というか耳にほとんど入ってこないから、別にそれほど嫌悪感はないのだが、自分でやる音楽となると話は別だ。僕は他方にあるのが「詩」であるとは今まで思えなかった。はたしてそれは詩なのだろうか。もっと別のものがあるのではないか。音楽と言葉。それらはいまだに僕のなかで互いを打ち消している。意味は違うが、その反動なのか、プレスリーとかバルバラのシャンソンとか、ポップスを爆音ノイズでやりたくなるのだが、それはそれで難しい。ところで、歌に関して、新しいニュースがある。EP-4 unitPに若い女性ヴォーカルに入ってもらうことにした。メンバーの了解はすでに取りつけてある。君の「歌」談義には考えさせられるものがあったし、感化されたのかもしれないね。森田潤との第二弾にも入ってもらおうと思っている。まだ詳細は明かせないけれど、これは新しい展開にはなるだろう。しかし妥協の産物にならないように気をつけなければならないと思っている。僕にとっても完全に未知数だ。彼女に歌の経験はない。
ランシエールを批判して、美は一つの規範だと君は前回の手紙に書いているが、僕にもそれはわかるよ。この規範には意味も意味に対する解釈もないし、その必要もない。アントン・ヴェーベルンは「生きること、それは一つの形を守ることだ」、と手紙に書いていたが、彼にとって生きることは、十二音階の音楽をつくること、彼にとっての美の破調、「ウィーンの危機」をつくり出すことだったのだから(これらは前衛主義とは何の関係もない)、似たようなことを言っているのだと思う。たとえ彼が最後はベランダでタバコを吸っているときに誤ってアメリカ兵に射殺されたのだとしても、それが生きることであり、ヴェーベルンにとって手に負えない必然だったのだろう。ヴェーベルンを聞くと、どうしても世界大戦時のヨーロッパの「塹壕」を思い起こしてしまう。
規範、形……。形というのは形態でもあるし、形式でもある。形はどこから来るのだろう。狂ってないものが狂っているものの別の顔であるように、真理に対する生の形式は、必然的に人は狂っているのだから、賭けのなかにあると言っていい。パスカルはそうも言っていた。生が強要する美はそんなやわなものじゃないし、断崖絶壁にある。いつも賭けられているものがある。ノイズが音楽や詩によって正常化され、美に変えられようとすればするほど、僕にとってノイズはパスカル的な「賭け」でもある。
マラルメが言うように、偶然はその点で廃棄されるのだろうか。そうであれば、規範、形、形式は移動を始め、別の感覚の領域に移ることになる。そうはいっても偶然と音楽の字義どおりの結合は美の硬直した形式でしかないと感じざるをえなかった。ずいぶん前、スコアどおりにジョン・ケージを弾くピアニストと二人で現代音楽の解体みたいなことをやったことがあるが、すぐに飽きてしまった。ジョン・ケージの重要さを認めるにやぶさかではないが、僕はどうもケージが好きになれなない。彼の音楽が表しているとされるように、規範、形において、純粋に偶然だけが介在できるのか。それが何かになるのか。少なくともそれは「歌」にはならない。
君の隠喩嫌いに照らせば、ますます偶然は廃棄されるはずだ。ブルトンを俟つまでもなく、現実のなかにある偶然なるものは隠喩的作用を免れない。あちらとこちらが、突然にしろ、くっつくのだから。君は隠喩を嫌悪していると言うが、君は直喩も退けているのだから、君が嫌悪しているのは隠喩だけではなく、言葉と言葉のある種の関係かもしれない。その関係はひとつの認識ではあるが、しかしその逆に、隠喩的でない関係が必ずしも現実を構成しているのではなく、言葉の関係にあって現実をつくりだしているのは、たとえ「喩え」を成立させているかのように見えるとしても、むしろそれらの言葉それぞれの独立性だと僕には思われる。そうでなければ、それがいまだに僕にとって何なのかはっきりわからないにしても、「詩」は存在できないだろう。
ランシエールを批判して、美は一つの規範だと君は前回の手紙に書いているが、僕にもそれはわかるよ。この規範には意味も意味に対する解釈もないし、その必要もない。アントン・ヴェーベルンは「生きること、それは一つの形を守ることだ」、と手紙に書いていたが、彼にとって生きることは、十二音階の音楽をつくること、彼にとっての美の破調、「ウィーンの危機」をつくり出すことだったのだから(これらは前衛主義とは何の関係もない)、似たようなことを言っているのだと思う。たとえ彼が最後はベランダでタバコを吸っているときに誤ってアメリカ兵に射殺されたのだとしても、それが生きることであり、ヴェーベルンにとって手に負えない必然だったのだろう。ヴェーベルンを聞くと、どうしても世界大戦時のヨーロッパの「塹壕」を思い起こしてしまう。
規範、形……。形というのは形態でもあるし、形式でもある。形はどこから来るのだろう。狂ってないものが狂っているものの別の顔であるように、真理に対する生の形式は、必然的に人は狂っているのだから、賭けのなかにあると言っていい。パスカルはそうも言っていた。生が強要する美はそんなやわなものじゃないし、断崖絶壁にある。いつも賭けられているものがある。ノイズが音楽や詩によって正常化され、美に変えられようとすればするほど、僕にとってノイズはパスカル的な「賭け」でもある。
マラルメが言うように、偶然はその点で廃棄されるのだろうか。そうであれば、規範、形、形式は移動を始め、別の感覚の領域に移ることになる。そうはいっても偶然と音楽の字義どおりの結合は美の硬直した形式でしかないと感じざるをえなかった。ずいぶん前、スコアどおりにジョン・ケージを弾くピアニストと二人で現代音楽の解体みたいなことをやったことがあるが、すぐに飽きてしまった。ジョン・ケージの重要さを認めるにやぶさかではないが、僕はどうもケージが好きになれなない。彼の音楽が表しているとされるように、規範、形において、純粋に偶然だけが介在できるのか。それが何かになるのか。少なくともそれは「歌」にはならない。
君の隠喩嫌いに照らせば、ますます偶然は廃棄されるはずだ。ブルトンを俟つまでもなく、現実のなかにある偶然なるものは隠喩的作用を免れない。あちらとこちらが、突然にしろ、くっつくのだから。君は隠喩を嫌悪していると言うが、君は直喩も退けているのだから、君が嫌悪しているのは隠喩だけではなく、言葉と言葉のある種の関係かもしれない。その関係はひとつの認識ではあるが、しかしその逆に、隠喩的でない関係が必ずしも現実を構成しているのではなく、言葉の関係にあって現実をつくりだしているのは、たとえ「喩え」を成立させているかのように見えるとしても、むしろそれらの言葉それぞれの独立性だと僕には思われる。そうでなければ、それがいまだに僕にとって何なのかはっきりわからないにしても、「詩」は存在できないだろう。