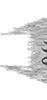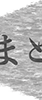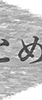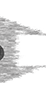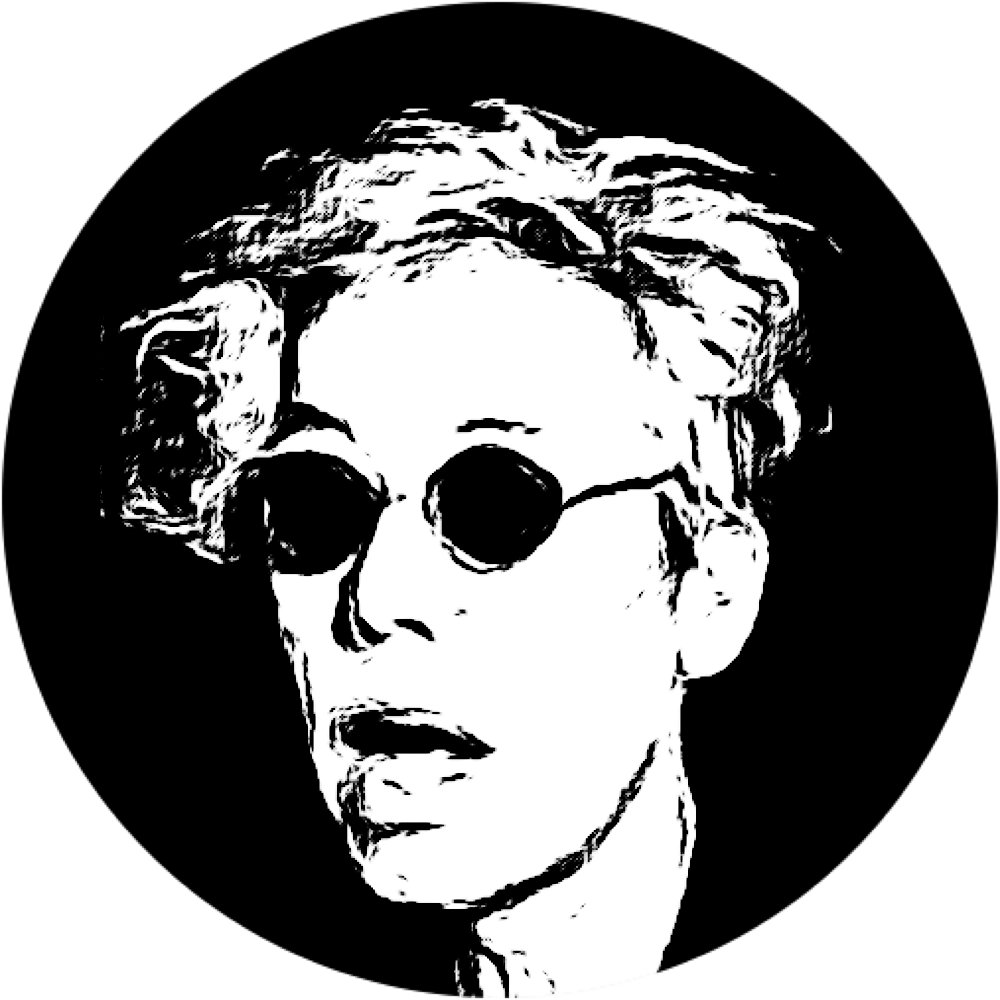2023年7月28日
親愛なる市田君、
アントナン・アルトー。ひとつの名前。単純にして同時に複雑な署名。僕が最初に書いた本は、『アントナン・アルトーの帰還』だった。小説仕立てだったが、監禁されていた精神病院を退院して、アルトーがパリへ戻ってくるところから始まる。精神病院で書かれた『ロデーズからの手紙』(その前にたらい回しにされていた精神病院では、自分が誰なのかもわからないくらい狂っていたらしく、何も書けなかった)を読めばわかるように、あれほど振幅の激しい「狂人」だったアルトーが、その直後、どのようにして晩年二年間で書いたような超明晰な作品を書くことができたのか。かつて彼は完全に彼岸の人ではなかったのか。十代の頃に読み始めて最初の衝撃を受けたが(思考の不能性、思考の中心にあいた空虚……)、それからずっとアルトーは僕にとっての「謎」だった。「生」が何であるかを考えるとき、アルトーの激しい「生」が苦しみとともに産み出した(あるいは流産した)文章を無視することはできなかった。しかしとりわけアルトーの晩年の「生」の思想は有機性としての生命を否定し、裏返すようなものだったことに留意しなければならない。彼は単に「呪われていた」だけではなかった。君が言うように、たしかにルーセルのほうが「狂って」いると僕も思う。アルトーは自殺についても否定的だ。アルトーにとって、ルーセルのように自殺はひとつの解決にはならなかった。
アルトーは僕に何をもたらしたのか? 「物を書く人間」として? 環境、教育、政治、経済、人格、性質、それらがその人をつくりあげてきたと人は言う。ルソーだってブルデューだってそれなりに正しいことを言っているのだろう。つまり「文化」? だがアルトーの生も、それを生きたアルトー自身も、はっきりと「文化」を拒否した。アルトーの母親は教育熱心だったのか? ランボーの父親は冷淡な人間だったのか? だが彼らの「作品」を前にするとき、君もそうだと思うが、作品を読み、読み解くにあたって僕はそういうことにほとんど興味がもてない。そのような「心理学」だけが結局生の問題である作家や評論家たちはいまでも大勢いるだろう。しかし心理学は最終的に「破綻」に行き着けない仕組みになっているのだから、生は非心理学的「破綻」によって別のものを別の仕方で思考する。それは形式の強要と必然、そして内容の空虚の間を揺れ動く。だから僕にとって「文学」は「実在」にほかならず、存在論、とりわけ奇妙な存在論であり、不確実性であり、(疑わしい)知覚の(未知の)ゾーンであって、この実在がどのように変化するのか、世界や世界の知覚やそれにさらされる自己に対して決定的な何かを与えるのか、そしてそれは感知できるのか、その真理と偽なるものの関係が何をもたらすのか、それだけがたぶん僕の逆説的な「数学」なんだ。だからそこには必然的にペシミズムもユーモアも発生する。そのような「真理」と格闘していたアルトーこそが、僕に大きな本質的「矛盾」をもたらした。
ところで、ご存知のとおり演劇家でもあったアルトーは、あるときエドガー・ヴァレーズとともにオペラを構想したことがあった。あの早い時期にアルトーはヴァレーズを評価していたことになる。何しろヴァレーズだぜ。オペラは実現することなく幻に終わったが、この幻がときおり僕にかなり鮮烈な合図を送ることがある。もちろん僕もアルトーが演出し出演した芝居を生で見ることはできなかったわけだし、映像もない。唯一、ラジオドラマ『神の裁きと訣別するため』の録音が残されているだけだ。だが、その録音に加えて、彼の演劇論などを読むと、生涯を通じてアルトーが音に敏感だったことが何となくわかる。それは彼の提唱する「残酷の演劇」の思想に属していたと考えることができる。時代状況を考えると、音楽の専門家でもない当時のフランス人がこのようなセンスをもつことはかなり考えにくいことだ。音楽音痴だったブルトンが目に浮かぶ。たぶんアルトーには音に対するイメージがかなりはっきりあったのだろう。僕もまたその幻のオペラやその音のイメージを想像する。いや、想像じゃない。むしろそれを勝手に、根拠もなく、自分流に「予感」すると言ったほうがいいかもしれない。とりわけ森田潤とのデュオは明らかにそのあたりから出発している。僕にとって、「音楽」と「文学」の関係はいまだそのようなものでしかないのかもしれない。
アルトーは僕に何をもたらしたのか? 「物を書く人間」として? 環境、教育、政治、経済、人格、性質、それらがその人をつくりあげてきたと人は言う。ルソーだってブルデューだってそれなりに正しいことを言っているのだろう。つまり「文化」? だがアルトーの生も、それを生きたアルトー自身も、はっきりと「文化」を拒否した。アルトーの母親は教育熱心だったのか? ランボーの父親は冷淡な人間だったのか? だが彼らの「作品」を前にするとき、君もそうだと思うが、作品を読み、読み解くにあたって僕はそういうことにほとんど興味がもてない。そのような「心理学」だけが結局生の問題である作家や評論家たちはいまでも大勢いるだろう。しかし心理学は最終的に「破綻」に行き着けない仕組みになっているのだから、生は非心理学的「破綻」によって別のものを別の仕方で思考する。それは形式の強要と必然、そして内容の空虚の間を揺れ動く。だから僕にとって「文学」は「実在」にほかならず、存在論、とりわけ奇妙な存在論であり、不確実性であり、(疑わしい)知覚の(未知の)ゾーンであって、この実在がどのように変化するのか、世界や世界の知覚やそれにさらされる自己に対して決定的な何かを与えるのか、そしてそれは感知できるのか、その真理と偽なるものの関係が何をもたらすのか、それだけがたぶん僕の逆説的な「数学」なんだ。だからそこには必然的にペシミズムもユーモアも発生する。そのような「真理」と格闘していたアルトーこそが、僕に大きな本質的「矛盾」をもたらした。
ところで、ご存知のとおり演劇家でもあったアルトーは、あるときエドガー・ヴァレーズとともにオペラを構想したことがあった。あの早い時期にアルトーはヴァレーズを評価していたことになる。何しろヴァレーズだぜ。オペラは実現することなく幻に終わったが、この幻がときおり僕にかなり鮮烈な合図を送ることがある。もちろん僕もアルトーが演出し出演した芝居を生で見ることはできなかったわけだし、映像もない。唯一、ラジオドラマ『神の裁きと訣別するため』の録音が残されているだけだ。だが、その録音に加えて、彼の演劇論などを読むと、生涯を通じてアルトーが音に敏感だったことが何となくわかる。それは彼の提唱する「残酷の演劇」の思想に属していたと考えることができる。時代状況を考えると、音楽の専門家でもない当時のフランス人がこのようなセンスをもつことはかなり考えにくいことだ。音楽音痴だったブルトンが目に浮かぶ。たぶんアルトーには音に対するイメージがかなりはっきりあったのだろう。僕もまたその幻のオペラやその音のイメージを想像する。いや、想像じゃない。むしろそれを勝手に、根拠もなく、自分流に「予感」すると言ったほうがいいかもしれない。とりわけ森田潤とのデュオは明らかにそのあたりから出発している。僕にとって、「音楽」と「文学」の関係はいまだそのようなものでしかないのかもしれない。