2024年1月28日
市田さま
君にコルトレーン役を引き受けてほしかったのは、なにも君をコルトレーンのような精神的求道者にしたいわけではないし、君のことをまったくそう思ってもいないが、たまたまコルトレーンとドルフィーの話になったので、この往復書簡をある種の市田・鈴木デュオの成果にしたいと思ったからなんだ。コルトレーンがミュージシャンとして真面目なだけでなく、宗教的であることは、君の言うとおりだと思う。僕はコルトレーンが全面的に好きではない。君にその役柄を押しつけたのではなく、この往復書簡において、僕もコルトレーン役はできそうにないからだ。ちょっとした「実験」をやってみたかったが、要するにドルフィーとコルトレーンの関係は僕たちの間では成立しそうにない。それはそれでいいし、別の道があるだろう。二人してドルフィーをやるしかない。
こんなことをあえて言うのは、君と僕は言うまでもなく書き手としても別個であるが、しかしこの「騒音書簡」を一つの全体的な「音楽」(君にとっては「哲学」かもしれないが)として考えていたからなんだ。僕が君の言うような「歌」にあやかりたい、あるいは一つの到達点にできればと思っているのは、ミュージシャンとしてだけではない。むしろ書き手としてよりそうかもしれない。この書簡を始めてますますそう思うようになった。それにこれはとりわけ「往復」書簡であって、「騒音」あるいは「音楽」によるやり取りであるし、もうすでに23回目に突入している! そして「歌」、あるいは「合唱」が、たとえ独奏をやったとしても、複数他者どうしによる思いがけない一致と懸隔、互いを知らない同一性とズレからなっていることは誰もがよく知るところだ。だから音楽を「作品」にするには、佐藤薫や森田潤のように特殊な「編集者」的能力を必要とする。それが僕にとって理想的だ。僕自身にはなかなか難しい問題ではあるけれど……。
でも、ここから少し離れよう。
最近に限らず、僕は昔からクラシック音楽を聴き続けているが、それは僕にとって、君にとっての「コルトレーン的」なものではまったくない。はっきり言うと、僕の頭のなかにある「ノイズ」的感触はむしろ「クラシック音楽」から来ている。それが言い過ぎなら、クラシック音楽を「聴いていた」ことから来ていると言っていい。モーダルなものの「外」を持ち込んだドルフィーでさえ作品としての「ノイズ」について考える完璧なよすがにはならなかった。わかりやすい例を示せと言われれば、森田潤がリリースした『GATHERING OF 100 REQUIEMS』(Wine and Dine)を聴くことを薦めるよ。これはモーツァルトの『レクイエム』の100の演奏を森田がミックス編集したものだ。すごい着想だと思うし、恐ろしい音楽だ。モーツァルトがなぜ他の作品とはまったく違う『レクイエム』を最後に書いたのか、それが本質的にどんな音の要素を含んでいたのか、何かしらのヒントを僕に与えてくれる。説明するのは非常に難しいが、僕にとって、「音」自体、音の連なり、あるいは音の「物質的」次元においてそうなんだ。それに何なら、すべての音楽に「ノイズ」を発見することができる。そもそもどんな音楽も、それが修道院から聞こえてくるものであれ、テレビやコンビニで鳴っているものであれ、「騒音」でしかない。クラシック、ジャズ、ロック、シャンソン、ポップス……。それぞれのジャンルは、それが哲学的にしろ、そうでないにしろ、「ノイズ」自体や自然の音と同じく、僕にとって一つの「世界」を形成しないし、そのようには考えられない。
エリック・ドルフィーの『アイアン・マン』かあ。『アウト・トゥ・ランチ』より好きだよ。あんな早い時期にたしかに完成された作品だと思う。リラックスして聴くことが「できる」し! でも彼のサックス演奏自体、例えば、どんな風に初期の(あるいはずっとかも)オーネット・コールマンとの決定的違いを見つけ出せばいいのか、正直よくわからない。エリックもオーネットも、別の「世界」、君の言い方では、別の「宇宙」であることはうなずけるが、僕にとって、巨大ではあるけれど、一つの音楽的「要素」みたいなものだ。それにやっぱり「ジャズ」だ。真似はしないし、できない。
こんなことをあえて言うのは、君と僕は言うまでもなく書き手としても別個であるが、しかしこの「騒音書簡」を一つの全体的な「音楽」(君にとっては「哲学」かもしれないが)として考えていたからなんだ。僕が君の言うような「歌」にあやかりたい、あるいは一つの到達点にできればと思っているのは、ミュージシャンとしてだけではない。むしろ書き手としてよりそうかもしれない。この書簡を始めてますますそう思うようになった。それにこれはとりわけ「往復」書簡であって、「騒音」あるいは「音楽」によるやり取りであるし、もうすでに23回目に突入している! そして「歌」、あるいは「合唱」が、たとえ独奏をやったとしても、複数他者どうしによる思いがけない一致と懸隔、互いを知らない同一性とズレからなっていることは誰もがよく知るところだ。だから音楽を「作品」にするには、佐藤薫や森田潤のように特殊な「編集者」的能力を必要とする。それが僕にとって理想的だ。僕自身にはなかなか難しい問題ではあるけれど……。
でも、ここから少し離れよう。
最近に限らず、僕は昔からクラシック音楽を聴き続けているが、それは僕にとって、君にとっての「コルトレーン的」なものではまったくない。はっきり言うと、僕の頭のなかにある「ノイズ」的感触はむしろ「クラシック音楽」から来ている。それが言い過ぎなら、クラシック音楽を「聴いていた」ことから来ていると言っていい。モーダルなものの「外」を持ち込んだドルフィーでさえ作品としての「ノイズ」について考える完璧なよすがにはならなかった。わかりやすい例を示せと言われれば、森田潤がリリースした『GATHERING OF 100 REQUIEMS』(Wine and Dine)を聴くことを薦めるよ。これはモーツァルトの『レクイエム』の100の演奏を森田がミックス編集したものだ。すごい着想だと思うし、恐ろしい音楽だ。モーツァルトがなぜ他の作品とはまったく違う『レクイエム』を最後に書いたのか、それが本質的にどんな音の要素を含んでいたのか、何かしらのヒントを僕に与えてくれる。説明するのは非常に難しいが、僕にとって、「音」自体、音の連なり、あるいは音の「物質的」次元においてそうなんだ。それに何なら、すべての音楽に「ノイズ」を発見することができる。そもそもどんな音楽も、それが修道院から聞こえてくるものであれ、テレビやコンビニで鳴っているものであれ、「騒音」でしかない。クラシック、ジャズ、ロック、シャンソン、ポップス……。それぞれのジャンルは、それが哲学的にしろ、そうでないにしろ、「ノイズ」自体や自然の音と同じく、僕にとって一つの「世界」を形成しないし、そのようには考えられない。
エリック・ドルフィーの『アイアン・マン』かあ。『アウト・トゥ・ランチ』より好きだよ。あんな早い時期にたしかに完成された作品だと思う。リラックスして聴くことが「できる」し! でも彼のサックス演奏自体、例えば、どんな風に初期の(あるいはずっとかも)オーネット・コールマンとの決定的違いを見つけ出せばいいのか、正直よくわからない。エリックもオーネットも、別の「世界」、君の言い方では、別の「宇宙」であることはうなずけるが、僕にとって、巨大ではあるけれど、一つの音楽的「要素」みたいなものだ。それにやっぱり「ジャズ」だ。真似はしないし、できない。
鈴木創士
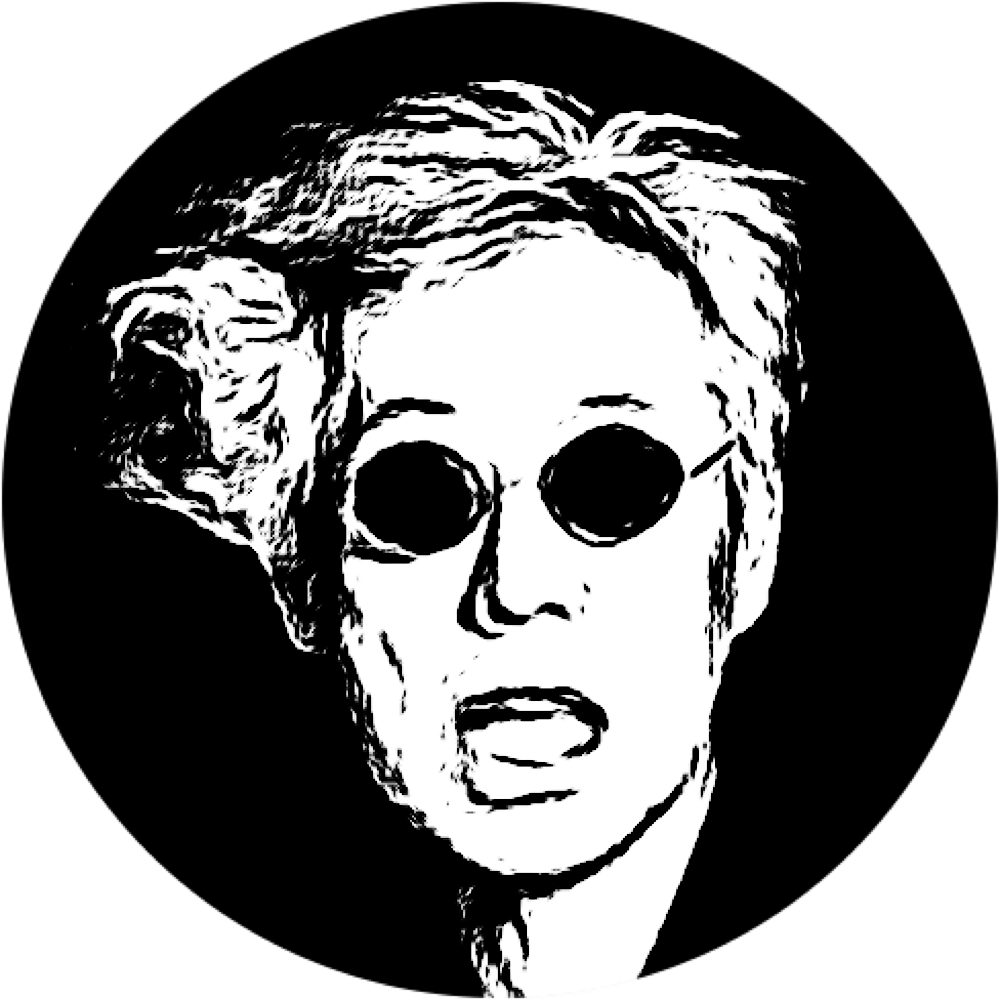
鈴木 創士(すずき そうし)
作家、フランス文学者、評論家、翻訳家、ミュージシャン──著書『アントナン・アルトーの帰還』(河出書房新社)、『中島らも烈伝』(河出書房新社)、『離人小説集』(幻戱書房)、『うつせみ』(作品社)、『文楽徘徊』(現代思潮新社)、『連合赤軍』(編・月曜社)、『芸術破綻論』(月曜社)他、翻訳監修など
【Monologue】森田潤との第二弾『残酷の音楽』を制作中です。






