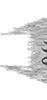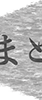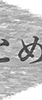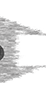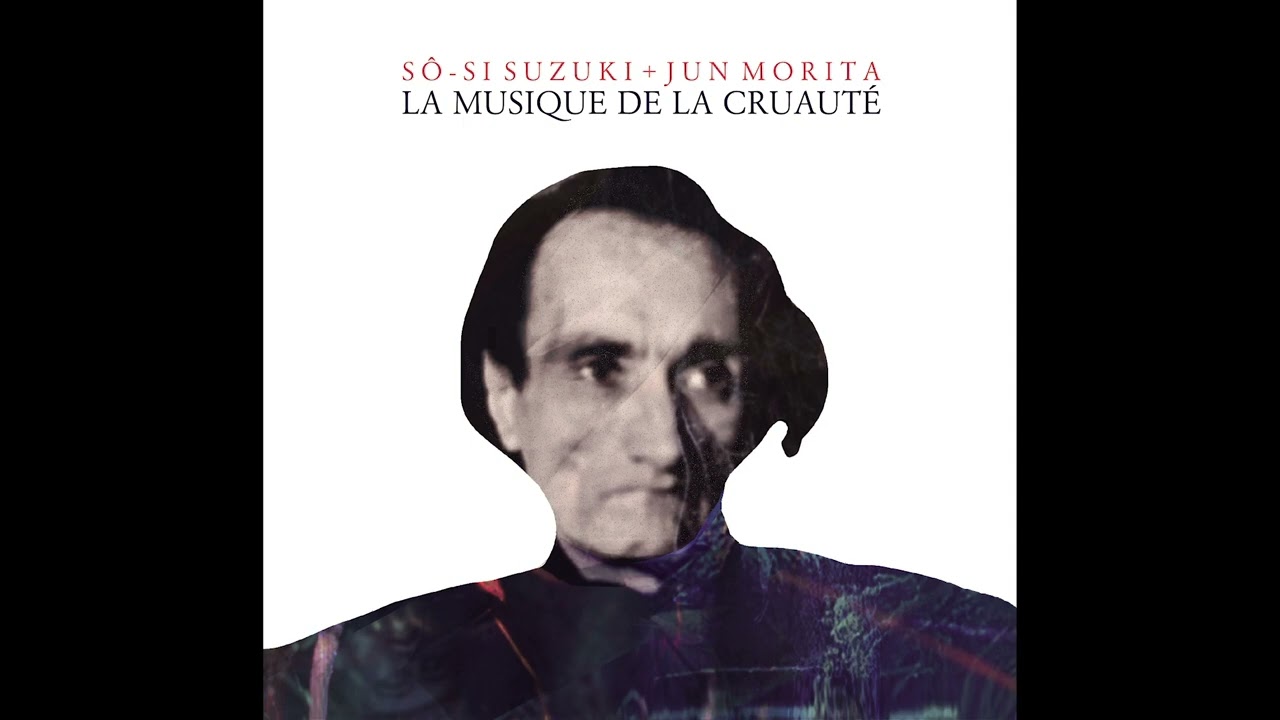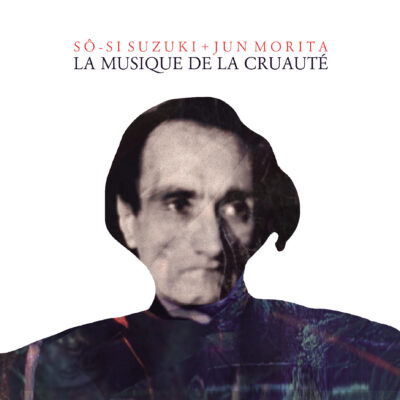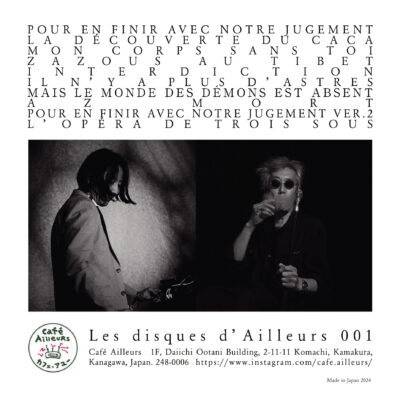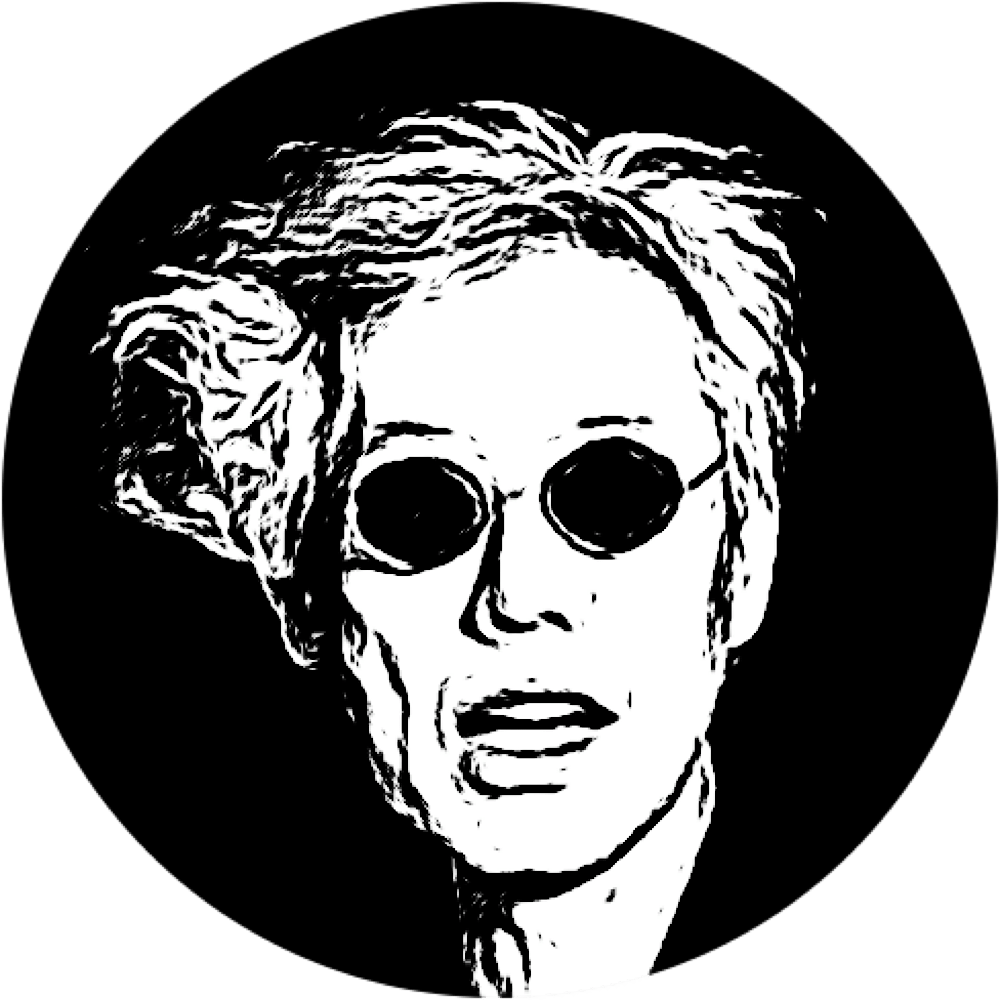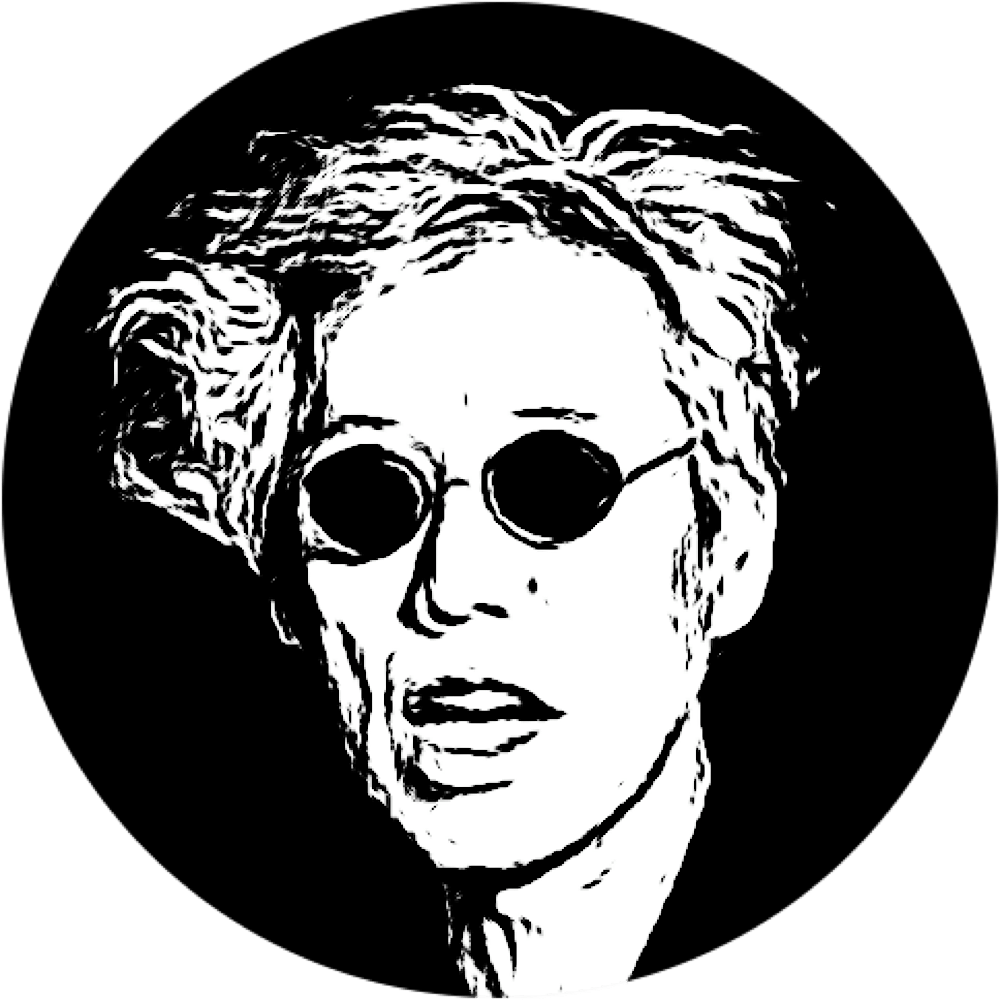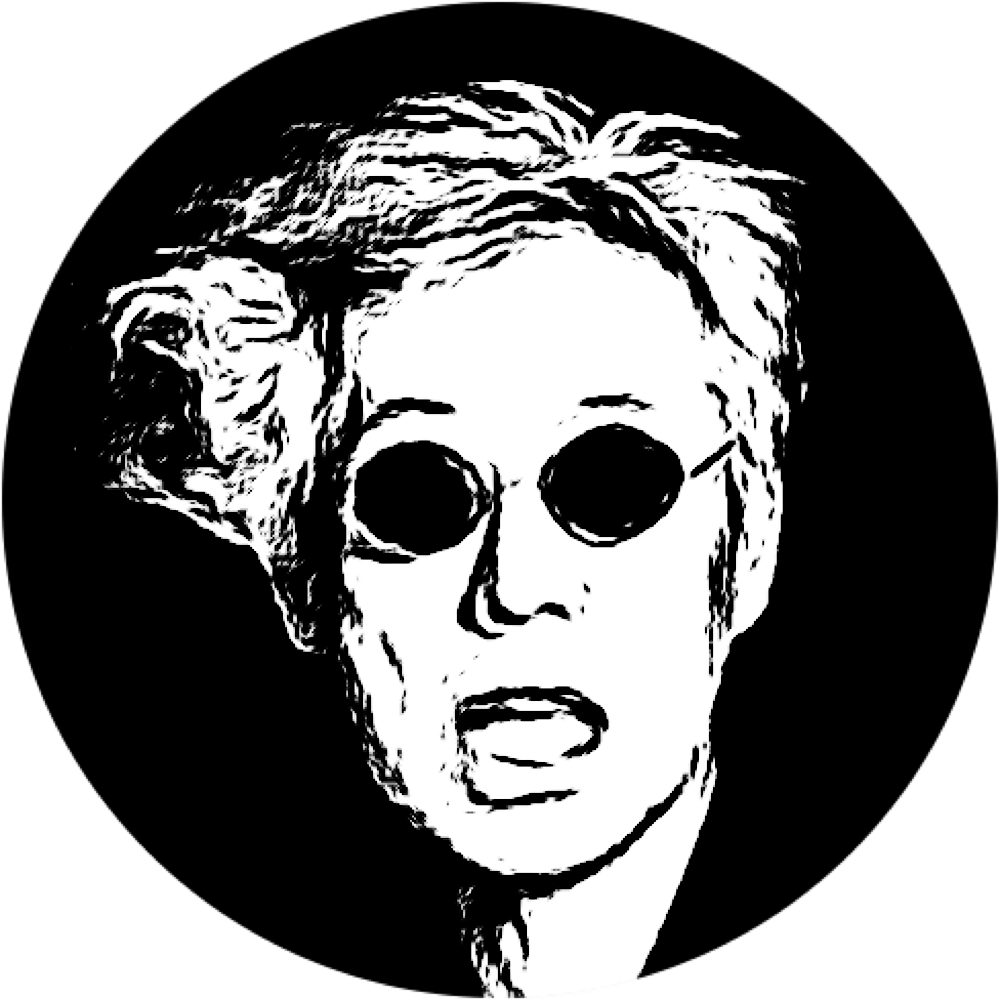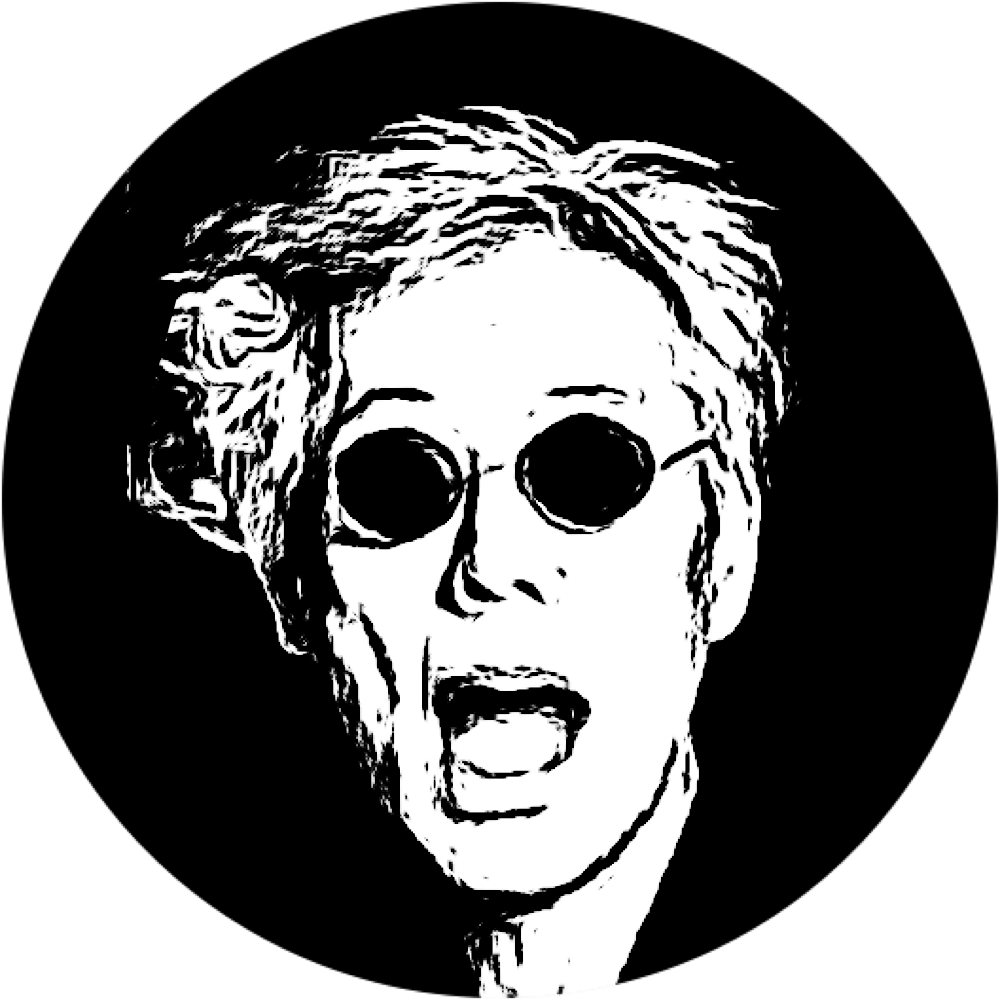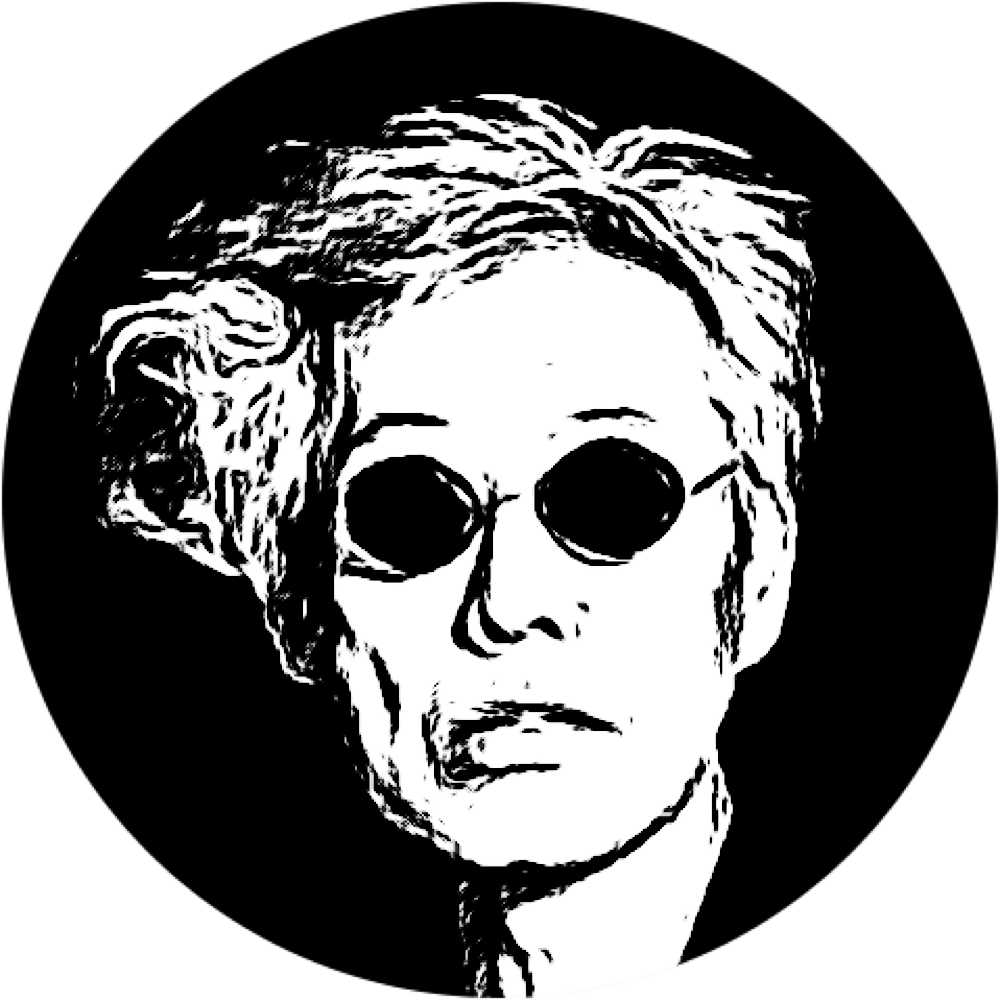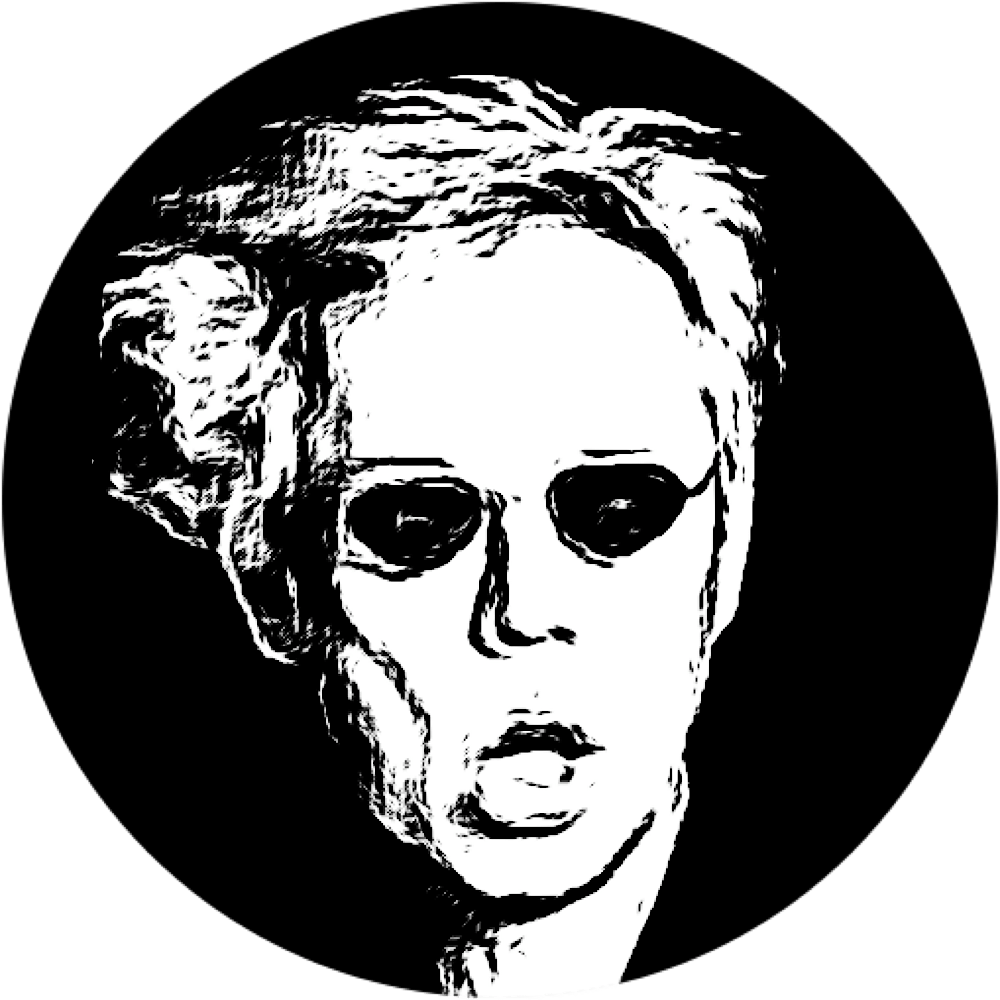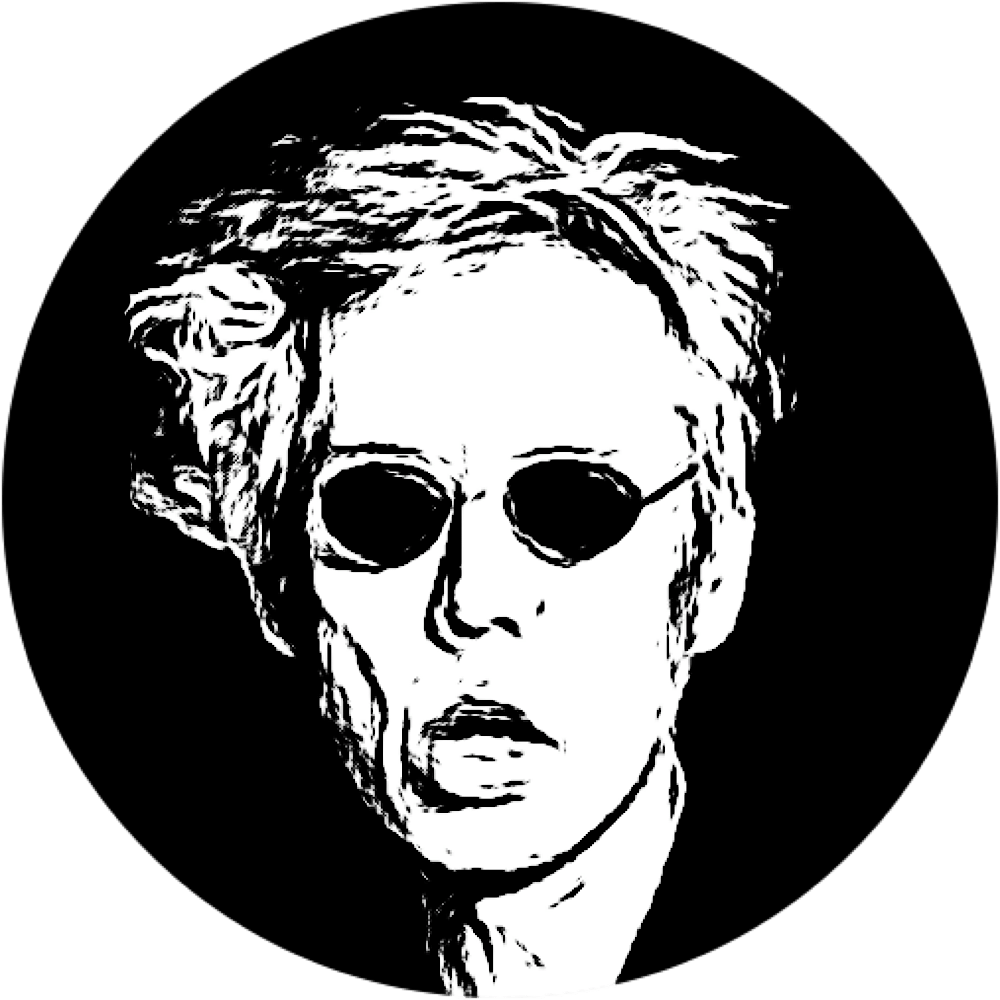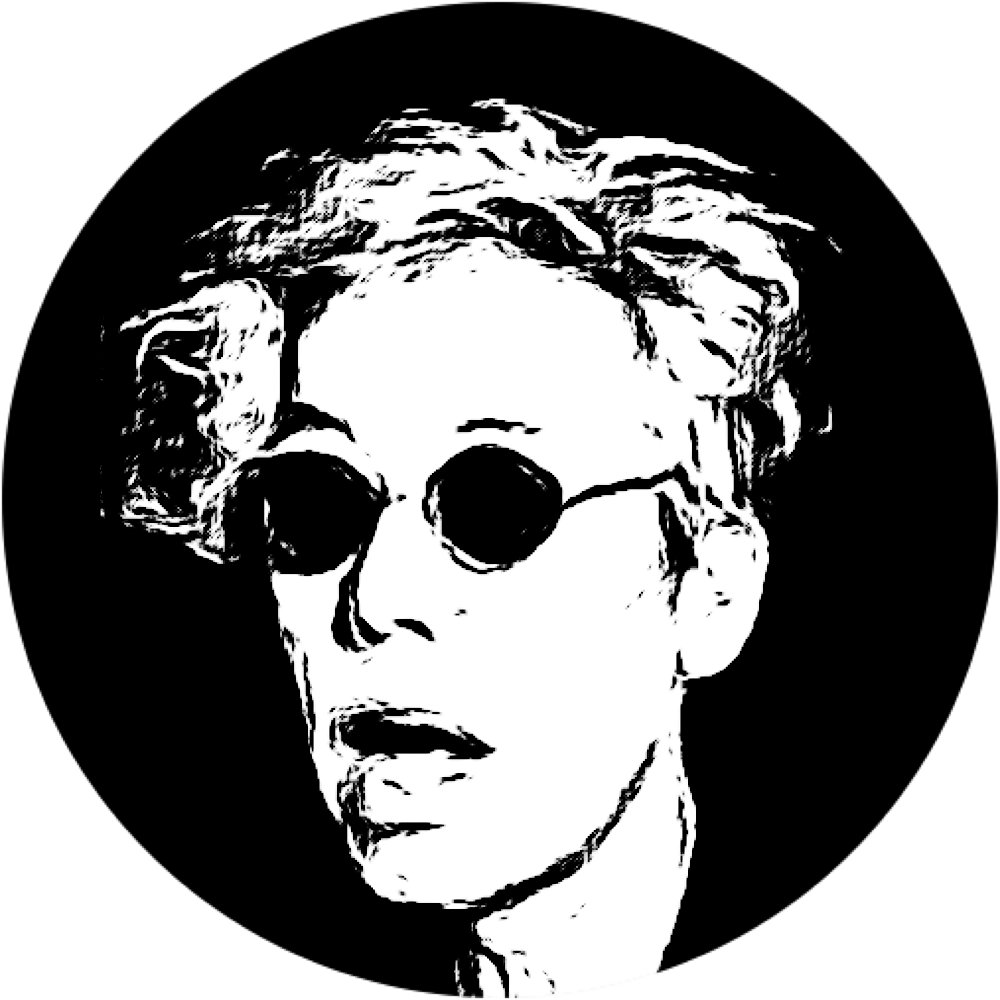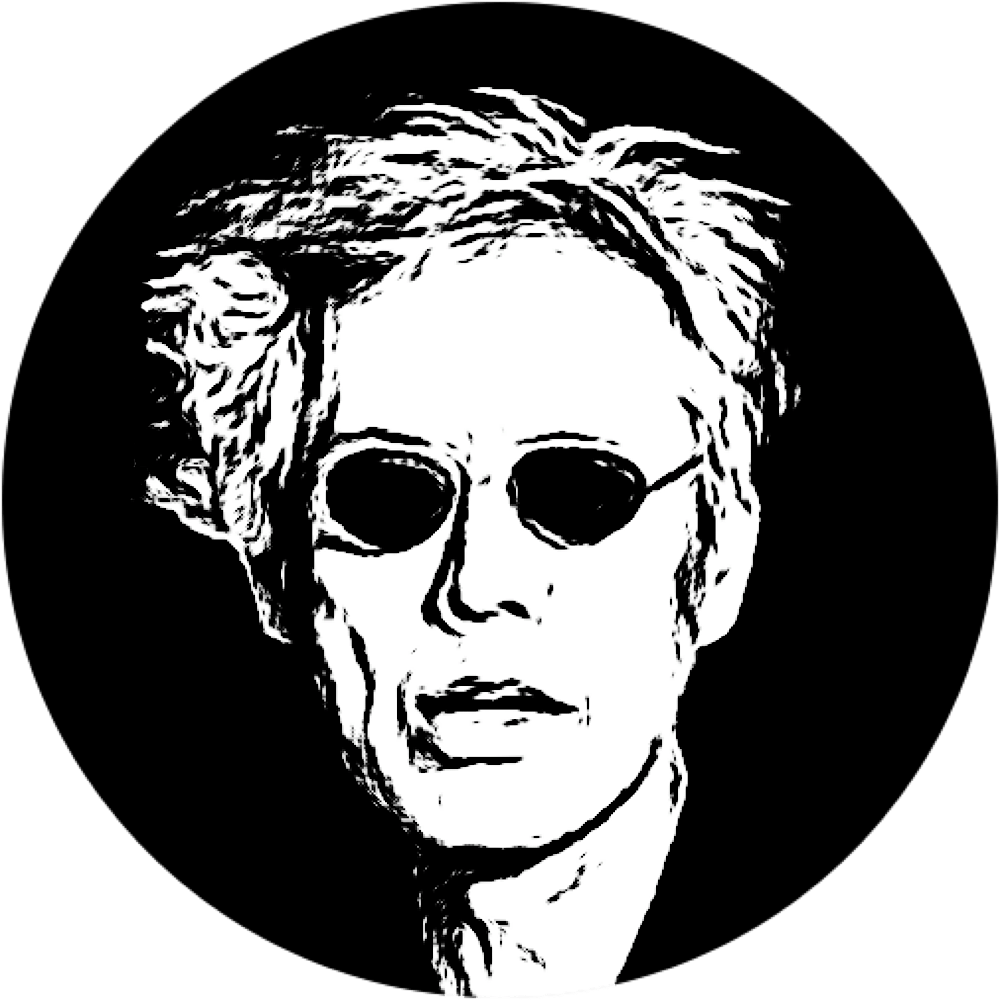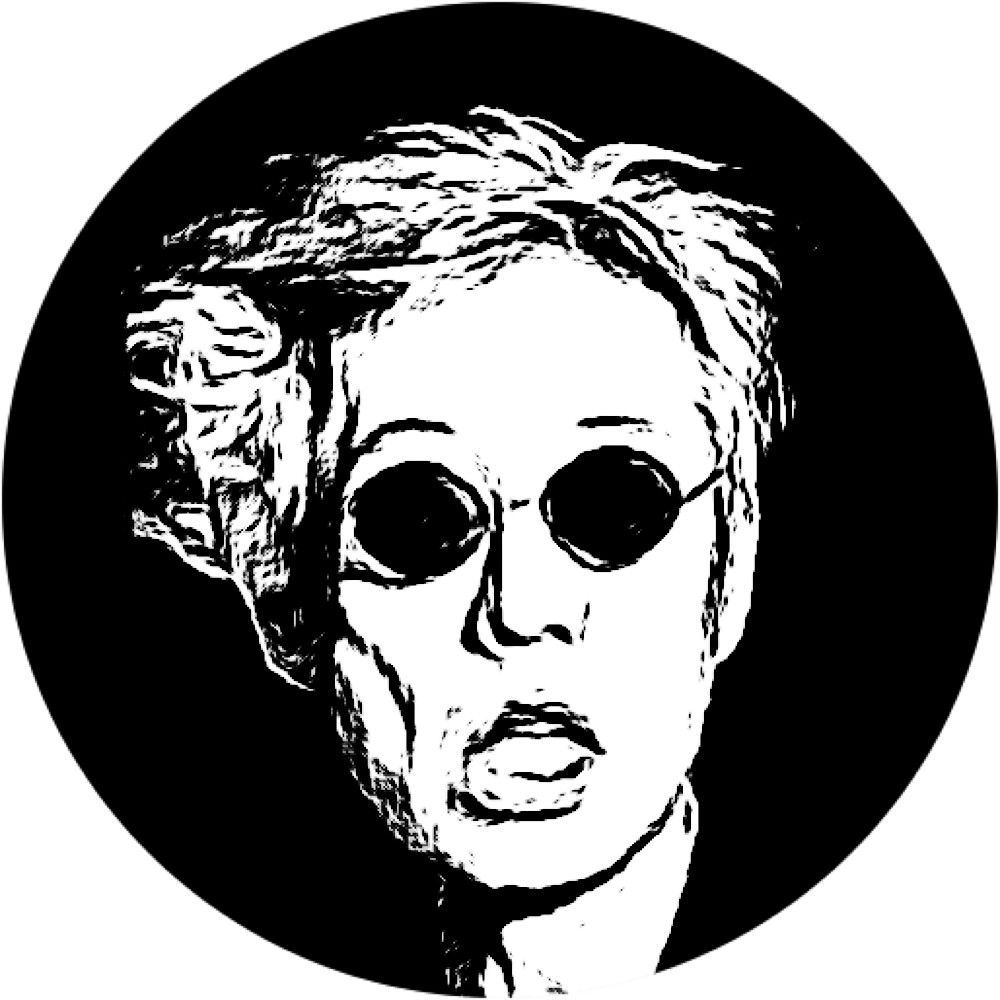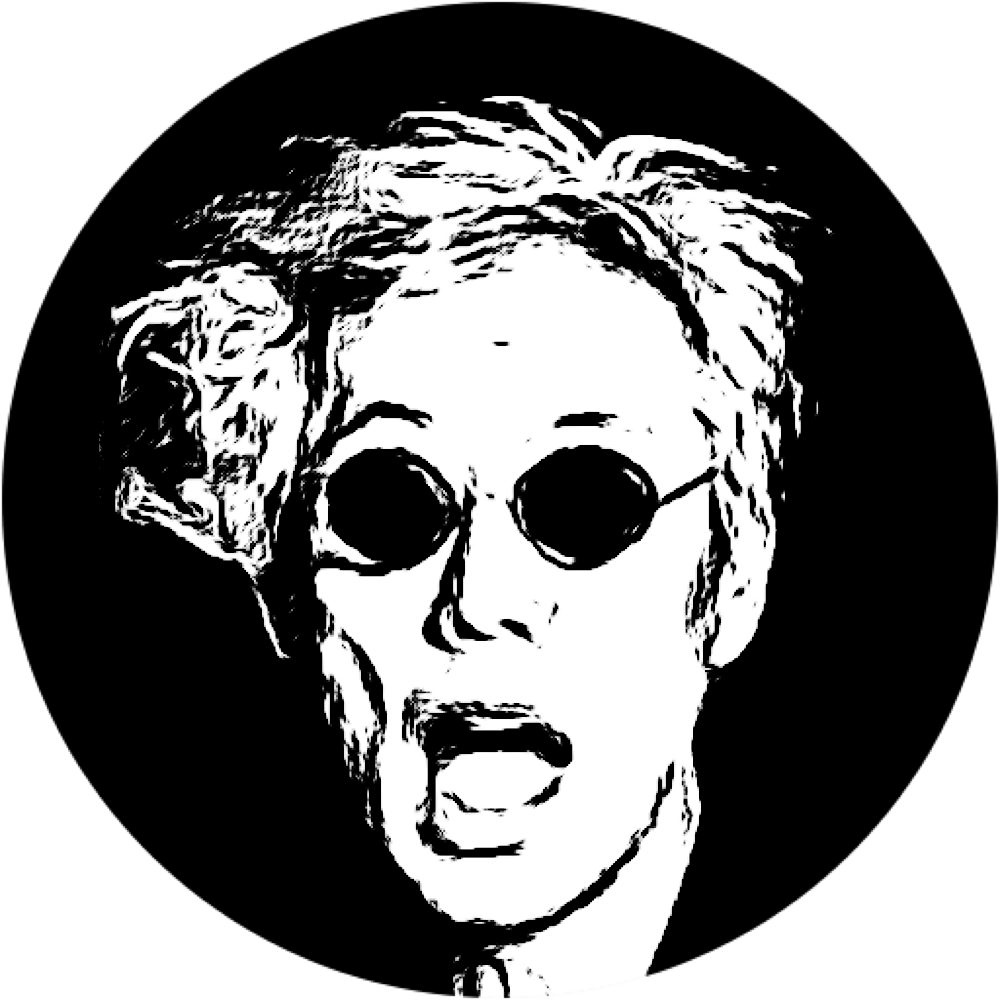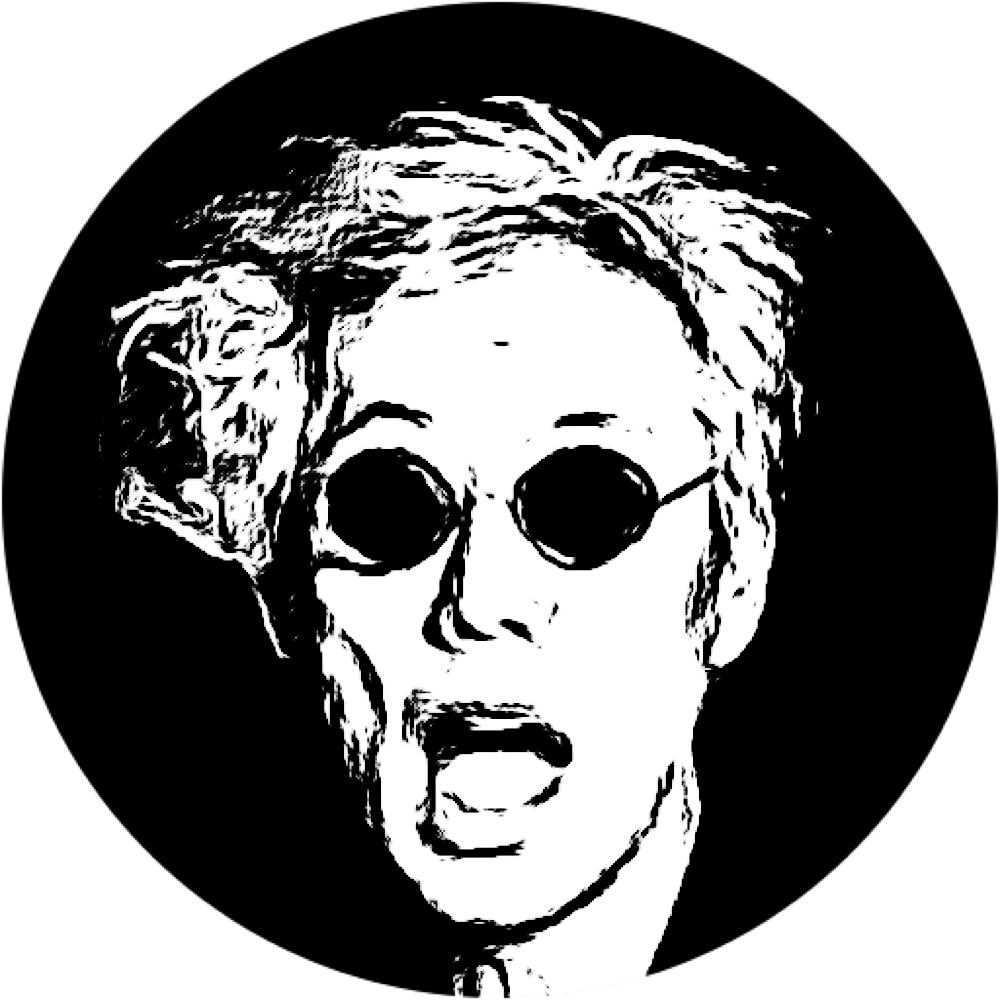鈴木創士様、
前回の貴兄の手紙に引きつけて言えば、「洗練」がよい例を提供してくれます。『ビッチェズ・ブリュー』にしても『レクイエム』にしても、私がそこに「洗練」を認めるのはひたすら「前」および「後」との関係においてのみ。モーツァルトには『レクイエム』の「後」がないのでマイルスに即して言うと、『ビッチェズ・ブリュー』の前後、いや幅をもっと大きくとっていわゆる「電化マイルス」の前後で、彼はバンドの音の作り方──特にライブにおける──をそれほど変えていないとも言えます。セッションにおけるルール設定というかフレーム──各ミュージシャンに対する「縛り」を緩くして「遊び」の妙を聞かせる手法──は50年代末から変わっていないし最後まで変わらなかったかもしれない。『プラグド・ニッケル』(1965)とワイト島ライブ(1970)の間に挟んで『ビッチェズ・ブリュー』(1969)を聞けば、サウンドの特異性は後退するはずです。そうした連続性の中で「最強ロックバンド」(本人談)の演奏──あんなロックバンドは他にないのに──を聞かせる『ジャック・ジョンソン』(1971)も可能になった。要するに様々な特異点は連続性の中に、連続性を前提に存在しています。それは一つの「曲」にあってさえ同じことでしょう。貴兄の言う「不意打ち」は、それがそこに訪れる、途切れない「流れ」があって成立するでしょう。私つまり聞き手からすれば、両方は平等です。一つの過程を構成するこの平等があって特異点は「洗練」になりえる。しかし、つねに「次の一手」を模索していなければならない演者にとっては、連続性のほうはときに積極的に忘れてしかるべきものです。通り過ぎる「同じもの」、自分がそこでジャンプしても壊れないクッション(「私」の着地を受け止めてくれる──マイルスは「電気」の音についてそう言っていた)と受け取るべきもの。そしてさらに私からすれば、それを忘れてよいのはミュージシャンにとどまらない「創作家」の特権です。羨ましい。もちろん「騒音書簡」では私もまた「創作家」なのですが。つまりここでの私はいくら理屈を並べたてようと「フィクション作家」と変わるところのない特権を享受させてもらっています。貴兄の手紙を、私のクッションにしている。
しかし音楽の創作家ではない私からすれば、「音楽の外」、音楽に「言えないこと」の大半は連続性のほうにあります。どんな連続性の中に自分がいるのかのほうが、しばしば捉え難い。なにしろ流れの只中にあってひたすら「次の一手」を考えなければいけないのですから。今この瞬間の私のように。この特殊なほとんど強いられた忘却ゆえに、自分の「つもり」と自他関係における連続性はつねにズレの可能性に晒されます。しかしそんな反省をしていれば、それこそ連続性に先を越され、呑み込まれ、結局その連続性自体を見失ってしまう。
何回か前の手紙で、貴兄は「市田良彦から教えてもらったアルチュセールの言葉」を引いていました。「ぼくは自分と直接かかわりのないことを、理論においてなにも理解できない」。これは彼が自分の「身体」に受容した「経験」を根拠に「理論的」ななにごとかを語った、あるいはその「経験」そのものを語っていたという意味にはまさに「理解できない」と思います。というのも、スピノザ主義者としての彼には「人は身体がなにをなしうるか知らない」という命題もまた胸に刻まれていたので。自分が狂っているのではないかという不安、その点をめぐる「無知」こそ、彼に「理論」においても「自分と直接かかわりのあること」に向かわせた。「私」にとっては連続しているはずの身体経験こそ、彼の「私」には「外」を成していたのだと思います。中身の定かならぬ「外」。それが特異な表現として形をもつかどうかは、「ça dépendこととしだいによる」と言うにとどめたい。『レクイエム』が「恐ろしい」かどうかと同じことです。私には少年モーツァルトの天才エピソードは、マイルスのジャンキーぶり同様、特になにも語らないので。これも忘却のなせるわざ?